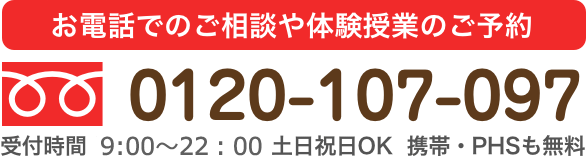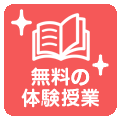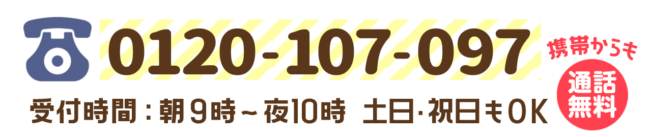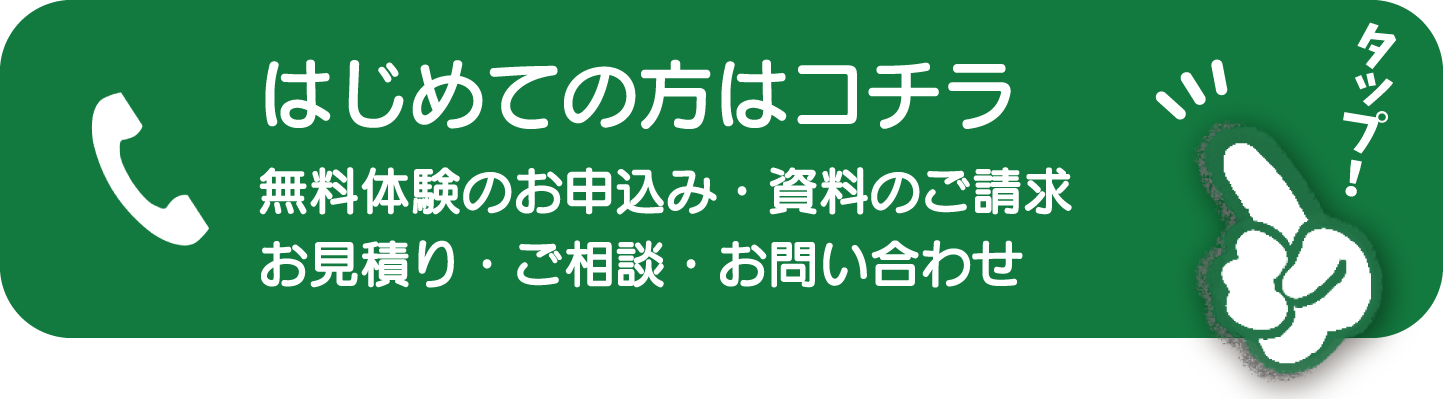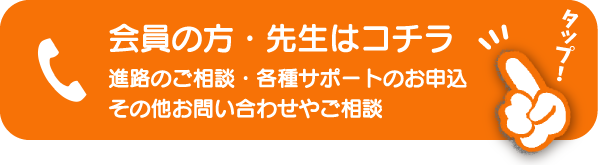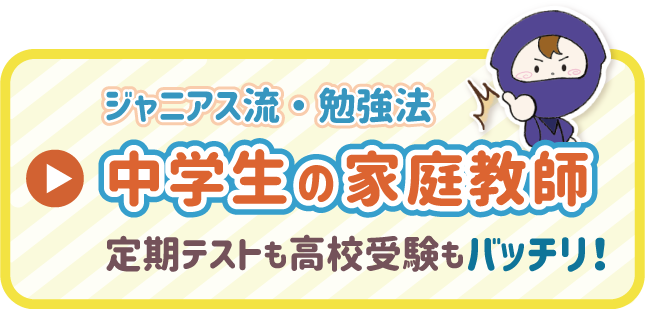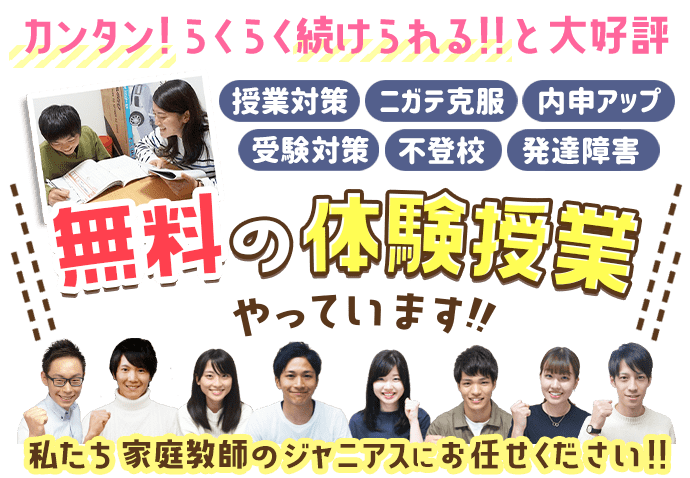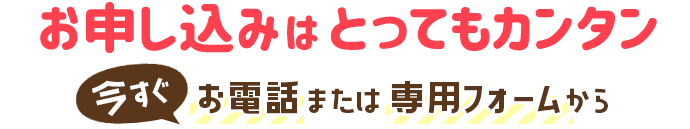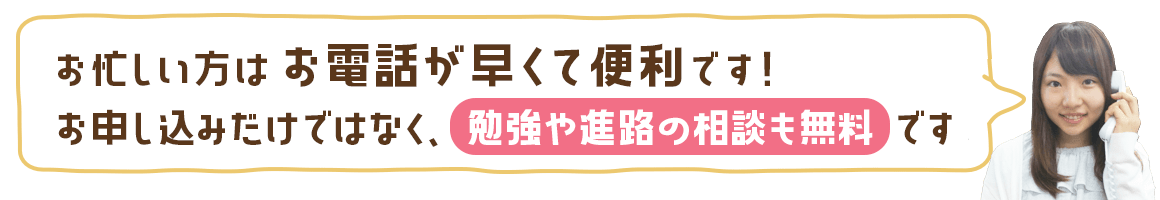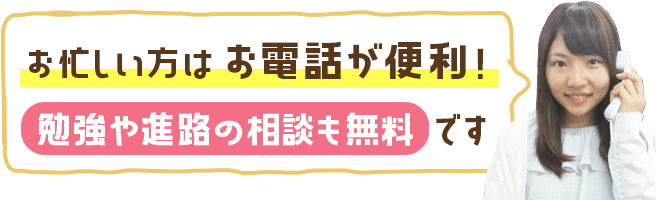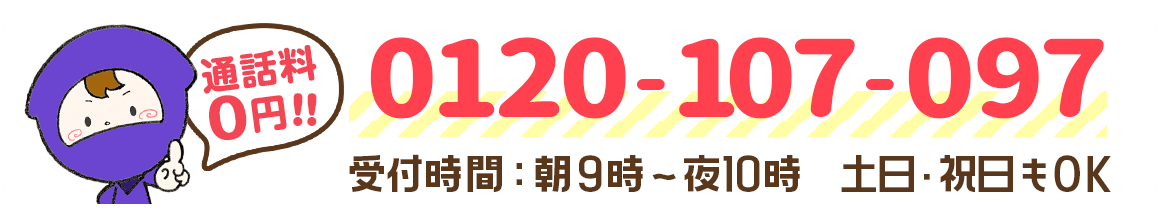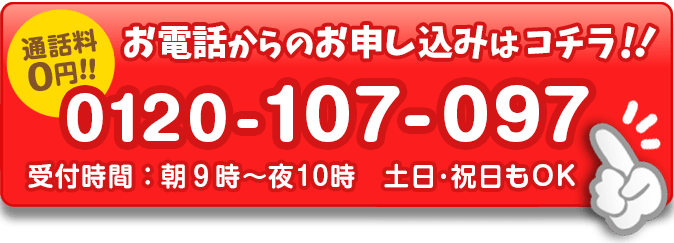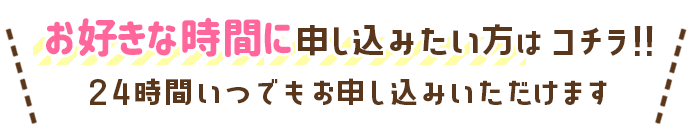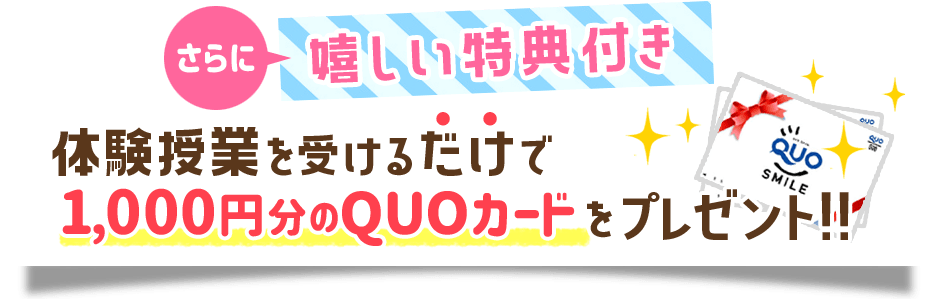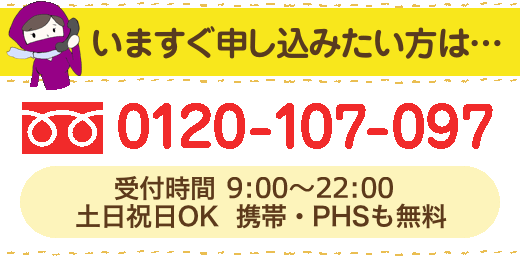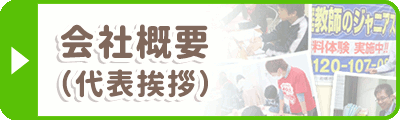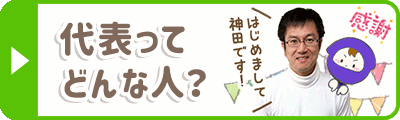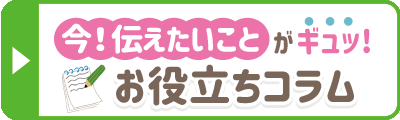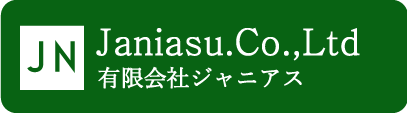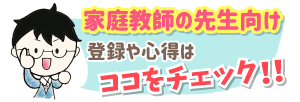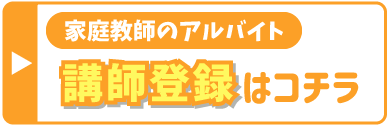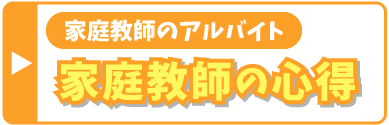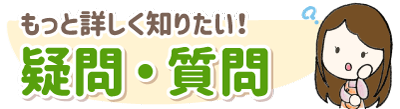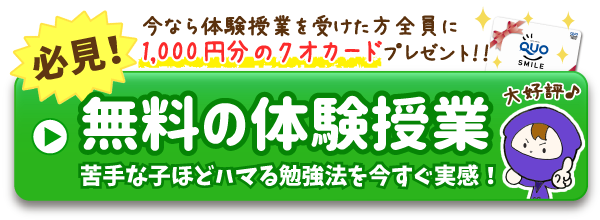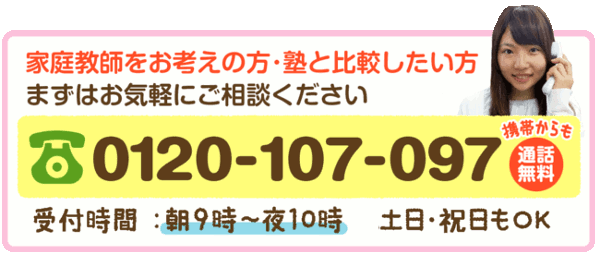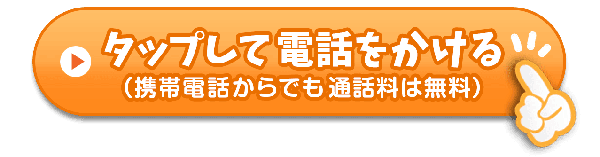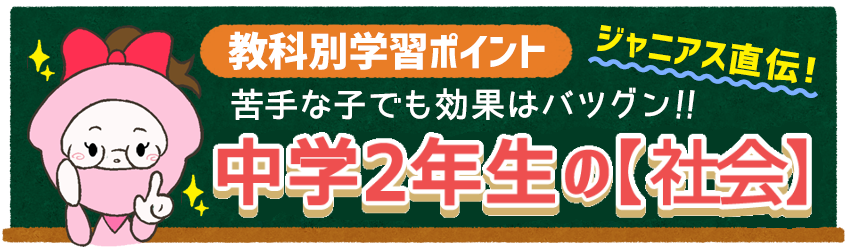
中学1年生で学習した「地理」と「歴史」はいかがでしたか?
地理も歴史も膨大な暗記量に苦労した中学生もたくさんいたと思います。

中2の社会でも地理と歴史を学習します。
もちろん「暗記科目」であることには変わりがないので、事前に正しい知識をどれだけ知っているかが重要!
社会は覚えてしまえば、定期テストは楽勝!ある意味では5教科の中で一番成績を上げやすい教科が「社会」ですので、頑張って覚えていきましょうね!
中2の地理は「日本の地理」
「世界の地理」を学習した中1に対して、中2からは「日本の地理」を学習します。身近な分野になるので聞いたことがあるワードもたくさん出てきますよ!
最低限覚えなければならない基本ワードに加えて、観光パンフレットなどから小ネタをピックアップして、少しでも楽しく覚えられるように面白ワードも工夫してみましたので、ぜひ軽い感じで読んでみて下さいね。
中2の歴史は「戦国時代」に突入!?
中2の歴史は中1の続きから始まります。
授業の進み具合や中学校によっても異なりますが、多くが室町幕府の終わりころまでが中1の範囲で、中2からは戦国時代から始めるケースが多いですね。
有名な戦国武将とかもたくさん出てくるので、歴史好きにとってはワクワクしますよね!
このページは「中2社会」で学習する地理と歴史の学習ポイントをご紹介させていただきます。
こんなページも見られています!
>>中学3年生の教科別学習ポイント
>>中学1年生の社会(地理・歴史)
>>中学3年生の社会(公民)

2021年4月から中学校の教科書が全面的に改訂され、新しい学習指導要領による授業が開始されました。歴史・地理・公民のすべての教科書に「SDGs」がモリモリ。グラフデータや資料の読み取り力も必要となり、これまでのような暗記だけでは対応できなくなりました。
もっと詳しく知りたい!
>>2021年からの社会は暗記だけじゃない!
中学2年生の【地理】
日本の姿
★日本の姿★
①世界の中での日本の位置
緯度・経度でみた日本の位置
私たちが住んでいる国は「日本」です。
日本は世界地図の真ん中に位置しているモノがほとんどですが、実は、世界地図は自分の国を中心に作られる場合が多いので、世界共通の考え方で説明する必要があります。
中1の社会でも学習した「緯度と経度」や、まわりの大陸や国との位置関係で表す方法などがあります。
緯度と経度を使って日本の位置をみてみると、緯度では、およそ北緯20度から50度の間にあり、ほぼ同じ緯度にあるのは、アメリカ合衆国、中国、アフリカ大陸北部からヨーロッパ南部などがあげられます。
また、日本は北半球にありますが、逆側の南半島でほぼ同じ緯度にある国としては、ニュージーランドやアルゼンチンなどがあげられます。
経度では、およそ東経122度から155度の間にあり、ほぼ同じ経度にあるのは、オーストラリア、ロシアの東部、韓国などがあげられます。
世界の他地域からみた日本の位置
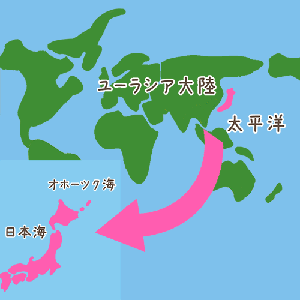
日本の位置をまわりの大陸や国との位置関係で表すと、ユーラシア大陸の東側に位置する国で、太平洋の北西部に位置する島国(海洋国)とも言い表せます。
地図の真ん中の国という表現では外国人には伝わりませんが、ユーラシア大陸や太平洋なら世界共通の考え方なので、だいたいの外国人にも伝わります。
例えば、アメリカ合衆国からみると、日本は広い太平洋をはさんで海のむこうにある島国となりますし、韓国や北朝鮮や中国からみてみると、日本は日本海をはさんで東にある隣国(りんごく)と言えます。
一方ロシアの東部からみると、日本はオホーツク海や日本海をはさんで南に位置する国ともいえます。
このように、大陸や海、国との関係からみた位置の表し方は、緯度と経度を使った絶対的な表し方と違って、どこからみるかで相対的な表現の仕方が変化します。
★日本の姿★
②時差でとらえる日本の位置
サッカーのワールドカップやオリンピック、さらにはテニスやゴルフなどの三大大会などで、日本代表や好きな選手が出る時は、LIVEでどうしてもみたくなって、夜更かしや朝早起きしてテレビなどを見る皆さんも多いのではないでしょうか?
経度15度で1時間の時差
日本では真夜中でも、試合や競技の行われる現地では昼間だったり、時差がありますよね。
こうした時差も、経度を使えば簡単に計算できるのです。
地球はほぼ24時間で1回転(360度)しているので、中1地理でも解説しましたが、
1時間あたりでは、
360(度)÷24(時間)=15度
回転していることになります。
このため、経度が15度違うと1時間の時差が生じます。
世界の国々は、それぞれ基準になる経線を決めており、その国ごとに決められた経線を標準時子午線(ひょうじゅんじしごせん)と言います。
日本では、兵庫県明石市を通る東経135度の経線を基準にして、この経線の上を太陽が通過する時刻を正午として標準時を決めています。
尚、イギリスの首都ロンドン郊外のグリニッジ天文台を通る経度0度の国際的な基準となる経線は、本初子午線(ほんしょしごせん)と呼ばれています。
本初とは「最初・首位」という意味だそうです。
外国との時差の計算方法
2つの地域の標準時の差のことを時差と呼びます。
日本(経度135度)とイギリス(経度0度)は経度差が135度あるので、9時間の時差があると簡単に計算できます。
135(度)÷15(度)=9時間
※経度15度で1時間の時差が生じます。
経度の差が大きいほど時差も大きくなります。
そのため、ロシアやアメリカ合衆国のように東西に長い国には、国内でも複数の標準時があります。
太平洋上には、日付変更線という1日の始まりと終わりを表す線が、ほぼ180度の経線上に沿って設けられていて、日付を調整する役割を果たしています。
日付変更線を西から東へ通過した場合は1日遅らせ、東から西に通過した場合は1日進めます。
日本とアメリカの位置で考えると必ず日付変更線を通過するので、日本側では1日進め、アメリカ側では1日遅らせるなど具体例で覚えると覚えやすいです。
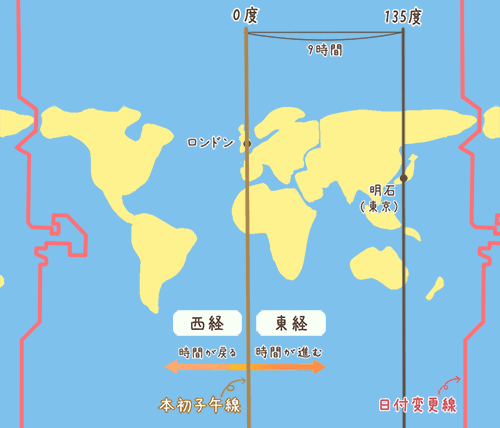
日本が1月1日の時は、アメリカは12月31日
アメリカが12月31日の時は、日本は1月1日
★日本の姿★
③日本の領域と領土問題
日本は、北海道、本州、四国、九州の4つの大きな島と周辺の島々から形成され、日本列島とも呼ばれる島国です。
国土面積は、約38万㎢。北海道から沖縄までの距離も約3,000㎞で、弓のような形で細長くのびています。
他の国との国境線はすべて海上に引かれています。
日本の領域
国の主権がおよぶ範囲を「領域」といいます。
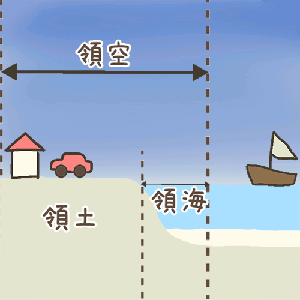
陸地・・・領土(りょうど)
海域・・・領海(りょうかい)
空域・・・領空(りょうくう)
と呼ばれ、領土・領海・領空を合わせて「領域」です。
尚、領海の範囲は国によって異なりますが、日本の領海は領土沿岸から12海里(約22km)の範囲、日本の領空は領土と領海の上空と定められています。
ちなみに前回学習した緯度と経度で、日本の位置はおよそ北緯20度から50度の間、経度ではおよそ東経122度から155度の間とざっくり言いましたが、領土の北端と南端の緯度の差は約25度、東端と西端の経度の差は約31度で、領土だけだと少し狭まります。
排他的経済水域と接続水域
日本の領海は海岸線から12海里(約22.2km)の範囲ですが、その領海の外側には、沿岸の国が魚などの水産資源や、海底にある鉱産資源を利用する権利をもつ排他的経済水域(はいたてきけいざいすいいき)があります。
排他的経済水域は、国連海洋法条約で海岸線から200海里(約370km)以内の範囲と定められています。
この海域では、船や航空機の通行、海底ケーブルやパイプラインの敷設(ふせつ)がどの国にも認められています。
また、領海の外側で、海岸線から24海里(約44.4km)の範囲を接続水域(せつぞくすいいき)と呼び、沿岸の国が密輸や密入国などの取りしまりを行っています。
各国の 排他的経済水域の面積は、領土における海岸線の形や、隣国との位置関係などで大きく異なります。
島国である日本の場合は、領海と排他的経済水域をあわせた面積が、国土面積の10倍以上にもなります。ラッキーですね。
日本近海は、世界でも有数の漁場と言われています。
さらに沿岸の海底には、天然ガスをはじめとする地下資源が豊富にあると予測されています。
これらの海域が含まれる排他的経済水域は、日本にとって重要です。
このため、水没する危険性のあった東京から約1,700km離れた日本最南端の沖ノ鳥島(おきのとりしま)に護岸(ごがん)工事をほどこしたり、無許可で漁業を行う外国の船などを海上保安庁が取りしまったりして、排他的経済水域を守る取り組みを実施しています。
移り変わってきた日本の領域
日本の領域は時代の流れとともに変化しています。
第二次世界大戦後の1951年に結ばれたサンフランシスコ平和条約では、日本の領土は本州・北海道・九州・四国とその周辺の島々にいったんは限定されました。
その後、1953年には奄美(あまみ)群島、1968年には小笠原(おがさわら)諸島などの太平洋上の島々、1972年には沖縄(おきなわ)の島々が日本に復帰し、現在に至っています。
そして、皆さんもよくニュースなどで耳にする北方領土・竹島・尖閣諸島などで、その領有をめぐって隣国との間で課題がある地域もあります。
それぞれ詳しくみていきましょう。
北方領土をめぐる問題
北方領土とは、北海道の北東にある国後島(くなしりとう)・択捉島(えとろふとう)・色丹島(しこたんとう)・歯舞群島(はぼまいぐんとう)の4島のことをいい、日本固有の領土と考えられています。
日本はサンフランシスコ平和条約において、樺太(からふと=サハリン)の一部や千島(ちしま)列島の権利を放棄しましたが、北方領土の近海は、水産資源が豊富な漁場で、多くの日本人がこれらの島に住んでいました。
しかし、第二次世界大戦後にソビエト連邦に占拠(せんきょ)され、日本人は強制的に退去させられました。
その後、現在までロシアが不法に占拠した状態になっています。
1992年からは、相互理解と友好を深めて北方領土問題の解決に貢献することをめざした「ビザなし交流」が始められ、日本人の元・島民やその家族と、現・島民のロシア人との相互訪問が行われるようになりました。
ビザとは入国先の国が自国に入ることを許可する証明書のことです。
日本は、ロシアに対して北方領土すべての返還を求め続けていますが、残念ながらいまだに実現されてはおりません。
竹島(たけしま)をめぐる問題
竹島は、1952年から韓国が一方的に自国の領土と主張し占拠しています。
ちなみに韓国名は、独島(トクト)という呼び名です。海洋警察隊をおいたり、灯台や埠頭などを建設したりしています。
日本はこれに抗議し、国際司法裁判所での話し合いを3回も提案していますが、韓国が応じず現在にいたっています。
尚、竹島は日本海にあり、17世紀には日本の人々が漁を行っていました。
1905年には、明治政府が国際法に従って島根県に編入し、日本固有の領土として再確認されているようです。
尖閣(せんかく)諸島をめぐる問題
1970年代から、中国が一方的に領有権を主張するようになりました。
中国の船が尖閣諸島周辺の日本の領海に不法に侵入してくることもたびたびあったため、日本は2012年に尖閣諸島の大半を国有地化し、領土の保全に努めています。
尚、尖閣諸島は東シナ海にあり、1895年に沖縄県に編入された日本固有の領土です。
第二次世界大戦後はアメリカ軍の占領下に一時おかれましたが、1972年に沖縄県の一部として日本に復帰しました。
尖閣諸島には、そもそも領有権の問題は存在しませんでしたが、1970年代に周辺の海域に原油などの資源が埋蔵されていることが注目されるようになったため、中国が領有権を主張しだしたきっかけとなりました。
★日本の姿★
④都道府県と県庁所在地
都道府県とは、地方政治の基本単位である地方公共団体としての地域区分です。
都道府県は47あります。
47の都道府県
1都(東京都)、1道(北海道)、2府(大阪府・京都府)、43県
これら合わせて47の都道府県です。
このしくみは1871(明治4)年に、明治政府がそれまでの藩を廃止して、「府」と「県」を置いた廃藩置県(はいはんちけん)を行ったことにより始まりました。
「府」や「都」には「みやこ」という意味があり、江戸時代以前から歴史的に重要な都市だった大阪や京都は、「府」となっています。
東京も昔は「府」でしたが、1943年に「都」に変更されました。
都道府県庁所在地
都道府県庁所在地とは、地方の政治を中心に行う県庁の置かれている都市のことです。
歴史的には城下町や港町など、それぞれの地域の政治や経済の中心であった場所が多く、現在も多くはその県で最も人口が多い都市となっています。
都道府県庁所在地の都市名は、大半が都道府県名と同じ名前になっています。
例えば、ジャニアスのある千葉県も県庁所在地は千葉市です。
宮城県の仙台市や、三重県の津市、島根県の松江市のように、都道府県名と県庁所在地の地名が異なる場合もありますので、詳しくは調べてみてくださいね。
尚、都道府県や市町村の境界線は、基本的には昔の国の境界線を利用していますが、富士山頂の境界は未確定だったり、和歌山県には飛び地もあったりします。
その他、1999年から市町村合併が進み、境界線が変化したりもしていますので、参考までに知っておいて下さい。
★日本の姿★
⑤さまざまな地域区分
47都道府県以外にも地域区分といった分け方もあります。
地域区分とは日本だけに限らず、国や世界などを共通性や関連性をもとにいくつかのまとまりのある地域にわけることをいいます。
日本の地理では7地方区分がよく使われます。7地方区分とは、都道府県をいくつかまとめて、
①北海道地方、②東北地方、③関東地方、④中部地方、⑤近畿地方、⑥中国・四国地方、⑦九州地方、の7つに分ける地域区分です。
さらに、中国と四国を別々にして8つの地方区分にする場合もあります。
7地方区分は、地理では基本的な分け方ですが、地域区分は、区分の基準や目的などによって、区分される地域の数や大きさなどが変わります。
例えばカップうどんでは、使われるだしの違いによって、北海道、東日本、西日本などの3区分にわけています。
全国中学校体育大会サッカー地区予選では、9地区に分けた地域区分もあります。
またさらに細かい区分では、中部地方を東海(とうかい)・中央高地(ちゅうおうこうち)・北陸(ほくりく)の3つに細区分したり、福島県を浜通り(はまどおり)・中通り(なかどおり)・会津(あいづ)で3つに細区分する場合もあります。
同じ一つの地方でも、地域によってその特色に違いがあることもあるので、地方をさらに二つから三つに分けた方が特色をとらえやすくなることがあるそうです。
中学2年生の【地理】
日本の地理的特色
★日本の地理的特色★
①自然環境の特徴
世界の地形
日本の地理的特徴を知るには、世界の地形を知ることが重要です。
日本では地震や火山活動がよく起こりますが、世界ではほとんどない地域もあります。どのように分布しそこではどのような地形がみられるかを考えていきましょう。
地震・火山活動が活発なところは、山地や山脈がつらなっている「造山帯」に集中しているそうです。
造山帯では、土地がもり上がったり沈んだりすることが活発におきているため、大きな山地や山脈ができます。逆に広大な平原が広がる地域では、地震・火山活動はほとんどおきません。
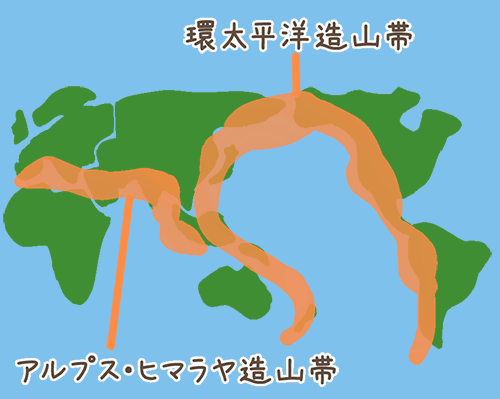
世界の造山帯としては、
「アルプス・ヒマラヤ造山帯」
「環太平洋造山帯」
の二つがあります。
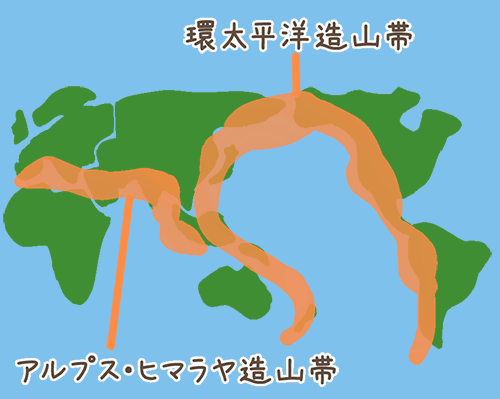
アルプス・ヒマラヤ造山帯
ヨーロッパのアルプス山脈からアジアのヒマラヤ山脈、インドネシア東部まで広がっています。
環太平洋造山帯
ロッキー山脈、アンデス山脈、ニュージーランド、日本列島など太平洋をぐるりと囲むようにつながっています。
日本は、インドネシア、ニュージーランドなどとともに環太平洋造山帯の上に位置し、世界の中でも地震や火山の活動が活発な国として知られています。
地震や噴火による災害が発生する可能性が高い一方で、観光資源や地熱発電にも利用されているといったメリットもあります。
安定した地域に広がる平原
世界には、地震や火山の活動がほとんど起こらない地域も広くあります。
安定大陸と呼ばれ、このような土地は広大な平原や高原が広がっており、長い年月をかけて、雨や風、氷河などの浸食で大地がけずられてできたので、平坦でなだらかな地形になっています。
具体的な地域としては、オーストラリア大陸の平原、北アメリカの中央平原、ロシアの中央シベリア高原などがあげられます。
日本の山地・海岸と周辺の海
日本列島の背骨をなす山地
日本の世界遺産の一つである富士山。きれいですよね。
富士山をはじめとして、日本では山地の面積が75%もあるって知っていました?
逆を言うと、国土面積25%しかない平野に人口の約8割の人々が暮らしています。
参考までに、世界の陸地にしめる山地の面積の割合は約25%なので、日本は世界全体からすれば約3倍山地が多いってことになります。
山登りやスキー・山菜などが好きな人には、3倍魅力ある国ってことですね。
富士山以外でも、日本列島には山地や山脈が背骨のようにつらなっており、本州の中央部には、ドドーンと3000m級の山々が連なる「日本アルプス」がそびえています。
日本アルプスは、次の3つの山脈(飛騨山脈・木曽山脈・赤石山脈)の総称です。
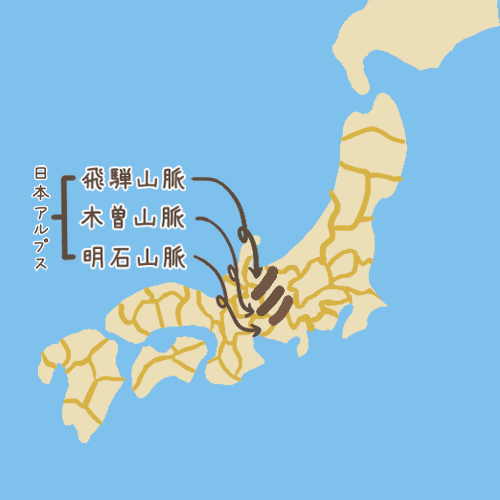
富山県・岐阜県・長野県・新潟県の4県にまたがる山脈
長野県にある山脈。
長野県・山梨県・静岡県の3県にまたがる山脈。
尚、日本アルプスは、登山やスキーによる観光はもちろん、古くから林業のさかんな地域として、木材を供給する役割も果たしてきました。
フォッサマグナ
日本アルプスの東側には、ラテン語で「大きなみぞ」という意味のフォッサマグナと呼ばれる地盤(じばん)の割れ目がずれ動いた状態である断層があります。
日本列島はここを境として「く」の字を逆にしたように折れ曲がっています。
また、フォッサマグナを境にして、日本の山地や山脈は並ぶ方向が異なっていて、東北日本ではほぼ南北に、西南日本では北東から南西方向、または東西方向に並んでいるという特徴がありますので、地図などで確認してみて下さい。
変化に富んだ日本の海岸
山の次は「海」です。
日本は、島国ですので海に囲まれています。
海岸にもさまざまな種類があり、その多くは、山地が海にせまった海岸になっています。
なかでも、小さな岬と湾がくり返す入り組んだ海岸は「リアス海岸」と呼ばれています。
リアス海岸は、波がおだやかで水深が深いことから天然の良港として使われ、貝やわかめなどの養殖がさかんに行われています。
一方、砂浜海岸やサンゴ礁に囲まれた海岸などもみられ、景色の美しさから重要な観光資源にもなっています。
また、埋め立てをして港や工業地帯がつくられたところや、干拓(かんたく)によって農地が拡大されたところなどでは、コンクリートの護岸(ごがん)で直線状の海岸線となっている人工海岸も多く存在します。
埋め立ては、川や海などに土砂(どしゃ)を入れて埋め、陸地にすること言い、干拓は、堤防を築き、内部の水を排水して陸地をつくることを言います。
日本を取り巻く海
日本列島の周辺、つまり周りの海の中には、浅くて平らな大陸棚(たいりくだな)が広がっています。
大陸棚とは、大陸の周辺にみられる海岸からゆるやかに傾斜しながら続く海底を言います。
太平洋側の大陸棚の先には、水深が8000mをこえる海溝(かいこう)があります。大陸棚の地下には鉱産資源があることが判明し、東シナ海などが注目を集めてきています。
日本の近海は、暖流の黒潮(くろしお=日本海流)と対馬海流、寒流の親潮(おやしお=千島海流)などが流れており、すぐれた漁場にもなっています。
特に黒潮と親潮がぶつかる潮目(しおめ=潮境しおざかい)となっており、海底の栄養分がまき上げられてプランクトンが集まるので、世界有数の漁場となっています。
日本の川と平野
大陸の川と比べた日本の川
山そして海の次は川を見ていきましょう。
日本の川は、6,650kmもある長さ世界一であるアフリカのナイル川や、流域面積世界一の約700万平方kmもある南アメリカのアマゾン川をはじめとする大陸の川と比較すると、長さや流域面積では残念ながら小規模です。
ちなみに日本で一番長い川は信濃川(しなのがわ)で367km。
流域面積日本一は利根川で約1万6840平方kmです。
日本の川の特色は、大陸の川と比べると標高の高いところから海まで短い距離を一気に急流となって流れているのが特色です。
このため日本では、降った雨がすぐに海へ流れてしまうのを防ぐため、川をせきとめる「ダム」をつくるなどして水を有効に利用する工夫が行われてきました。
川がつくるさまざまな地形
川はさまざまな地形をつくり出します。
川は上流で勢いよく流れて山をけずり、土砂を運びながら下流に向かい、やがて流れをゆるめていきます。
流れがおそくなったところでは、土砂がたまり、平野や盆地をつくり出します。
また、川の流れによって海まで運ばれた土砂は、波の力や海の流れによって海岸近くにとどまり、砂浜をともなった平野をつくることもあります。
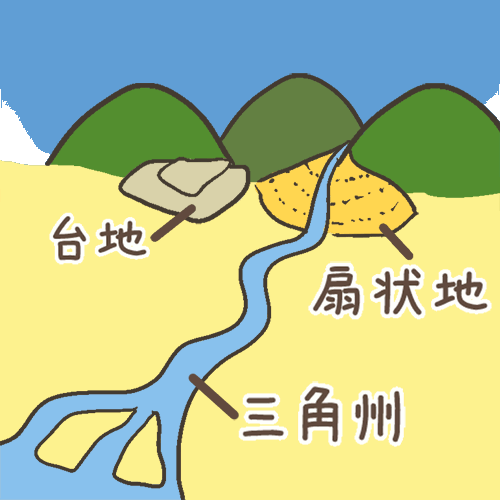
その他、川が山間部から平野や盆地に出たところでは扇状地(せんじょうち)、河口部には三角州(さんかくす)、また川や海沿いの平地よりも一段高くなっている土地は台地といい、それぞれ特色があります。
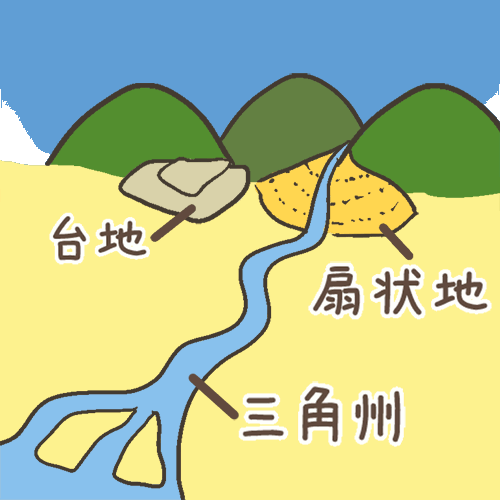
「扇状地」とは、山地から流れ出す川によって運ばれた土砂が山のふもとにたまってできた扇形、または半円形の地形をいいます。
扇状地の中央部は、ツブの大きい砂や石からできていて水が地下にしみこみやすいため、桃やぶどうなどの果樹園として利用されたりしています。
また、扇状地の末端では、地下を通ってきた水がわき出てくるため、昔から集落がつくられてきました。
「三角州」は、ツブの小さい砂や泥からなっていて水が地下にしみこみにくいのが特色で、昔からおもに水田として利用されてきましたが、近年では住宅地としても開発されたりなどしています。
「台地」は、川や海沿いの平地よりも一段高い土地となっているので、台地の上は水が得にくく、水田はつくりにくいので、畑や茶畑などで利用されたり、住宅地としても開発されています。
日本の気候
日本の気候は、四季の変化がはっきりしていることが特色です。
中学1年の地理で、世界の五つの気候帯を学びましたが、本州・九州・四国がおもに温帯、北海道が亜寒帯(あかんたい=冷帯)に属しています。
これは、夏と冬で季節風の流れが異なるため、夏には太平洋上から暖かく湿った大気が南東から北西に運ばれ、冬にはユーラシア大陸から冷たく乾いた大気が北西から南東に運ばれることによります。
そして、日本列島は南北に長くのびていることから、北と南では気温が大きく異なります。
北の北海道と南の沖縄をイメージすれば、気温は大きく違うことがわかりますよね。
また、日本列島の中央部には日本アルプスなどの山地や山脈がつらなっているため、太平洋側と日本海側では、気温や降水量の分布などにも違いがみられます。
さらに、日本は6月頃の梅雨(つゆ、ばいう)による長い雨、夏から秋にかけて多い台風、冬の雪などの影響で、世界の温帯・亜寒帯(冷帯)の中でも降水量が多い国となっています。
日本の気候区分
日本の気候は、気温・降水量とその月別の変化をもとにして、6つの気候区に分けることが可能です。
- 北海道の気候
- 日本海側の気候
- 太平洋側の気候
- 内陸の気候
- 瀬戸内(せとうち)の気候
- 南西諸島の気候
・・・の6つです。
北海道には、はっきりした梅雨が無く、1年を通して降水量は少ないという特色があります。代表的な都市は、北海道千歳(ちとせ)市などです。
これは、ユーラシア大陸から吹いてくる北西の季節風が、日本海をとおるときに水分をふくんで雲をつくり、日本の山地や山脈にぶつかって雪を降らせるためです。
逆に、夏には南東の季節風の風下となるため、太平洋側で山地や山脈にぶつかって雨が多く降り、日本海側にはほとんど水分を含んだ湿った風がこないので乾燥します。
代表的な都市は、新潟県上越市などです。
代表的な都市は、愛知県名古屋市やジャニアスのある千葉県船橋市などです。
加えて、夏と冬の気温の差、昼と夜の気温の差が大きいことが特徴です。
代表的な都市としては、長野県松本市などが該当します。
代表的な都市としては、岡山県岡山市などがあります。
夏の気温は本州とそれほど変わりませんが、沿岸に黒潮(くろしお=日本海流)が流れていて冬でも温暖な感じです。
代表的な都市は、沖縄県那覇(なは)市などがあります。
日本のさまざまな自然災害
日本に多い地震と火山
「地震、雷、火事、おやじ」って、聞いたことあります?日本で、特にこわいもの順にリズミカルにならべた言葉だそうです。
余談ですが「おやじ」は父親がこわかったという意味もあるようですが、オオヤマジ(おおきい風=台風の意味?)がなまって「おやじ」になったともいわれています。
昔から一番こわいものと考えられていた地震ですが、日本は環太平洋造山帯に位置しているため、地震が多く、各地に分布する火山も活発に活動します。
大地震が発生した場合、地震のゆれによって建物が壊れたり、山くずれや液状化(えきじょうか)の現象化などが発生し、大きな被害をおよぼすことがあります。
ちなみに液状化とは、地震の振動により水と砂を多く含む地面が一時的に液状のようになる現象です。
地震により海底の地形が変形した場合に、津波が発生することもあります。
2011年3月11日に起きた東北地方太平洋沖地震(東日本大震災)では、沿岸部に甚大(じんだい)な被害がもたらされました。
日本は、世界的にみても火山が多い国です。
火山の周辺では、噴火(ふんか)により火山灰や溶岩が噴出したり、火砕流(かさいりゅう)が発生したりして、人々や街が大きな被害にあうこともあります。
しかし一方で、火山が日本の美しい景観を生み出し観光資源となっていることも事実です。
日本のさまざまな気象災害
日本は気象災害も多い国です。
毎年のように梅雨や台風などによる大雨の時期があってうんざりですよね。
川や海のまわりの低い土地に多くの人が住んでいることも、多くの気象災害が起こる原因ともなっているようです。
台風の通り道になりやすい地域では、強風や高潮(たかしお)による被害、大雨による洪水や土石流(どせきりゅう)などが起こることもたびたびあります。
一方で、雨が十分に降らなかった年には、干ばつによる被害が発生することもあります。
干ばつとは長期間の水不足の状態をいいます。
また東北地方ではやませの影響で夏の気温が上がらず、稲などの農作物に被害が出て冷害となることもあります。
やませ(山背=偏東風)とは、東北地方太平洋側で春から夏(6月〜8月)に吹く冷たく湿った東よりの風のことを言います。
雪の降る地域では、大雪で交通網や建物への被害が起こることもあります。
特に雪に慣れない地域で大雪が降ると、交通機関などが使えなくなり、まれにまち全体の孤立を招いたりします。
自然災害に対する備え
防災への工夫
日本は自然災害の多い国ですが、地震や豪雨、台風などといった、災害を起こす自然の現象そのものを止めることは今のところできません。
自然災害によって被害をできるだけ少なくする「減災」や、被害が及ぶのを防ぐ「防災」などのさまざまな取り組みが行われています。
例として、近い将来に発生が予測されている南海トラフの巨大地震に備えた取り組みとして、建物や橋を地震のゆれに強くしたり、堤防を作って津波を防ぐなどの対策が行われてきました。
さらに、2011年に東北地方太平洋沖地震(東日本大震災)が実際に発生したことで、津波の避難場所となる津波避難タワーの設置や、日ごろの防災教育や地震情報の伝え方の見直しなどが進められています。
また、気象災害に対する対策として、ダムや河川の堤防などの設備をつくったり、災害の危険地域を指定して避難場所を決めたりする取り組みが行われています。
そして、過去の災害の記録や経験を教訓として、将来の防災や減災に生かす取り組みも最近注目を受けています。
防災への対応
実際に被災してしまったらどうなるのでしょうか?
国や市町村などの協力のもとで、被災者の救助や避難場所・仮説住宅の設置、食品・飲料水や生活用品の支給、医療活動といった支援が行われます。
被災した地域の人々だけでは救助や復旧が難しい場合は、地元の消防団や警察、自衛隊、海上保安庁の人々が被災地への救助に派遣されます。
例として、2013年に東京都の大島で発生した土石流(どせきりゅう)災害では、自衛隊や消防隊、ボランティアの人たちが多数かけつけ、救助やがれきの撤去を行いました。
このように大きな災害が発生した時には、地域や地方の枠をこえた協力体制が組まれています。
国や県、市町村などの公共機関が災害時に被災者の救助や支援を行うことを公助といいます。
公助があるといっても限界がありますので、自分や家族を自分自身で守る自助や、住民同士が協力して助け合う共助という行動をとれるようになることが求められています。
いざという時に助けてもらうためには、自分の住んでいる避難訓練に参加して、災害が起こったときにほかの住民と協力してどうやって行動するべきかを日ごろから身につけておくことも大事になります。
また、ハザードマップという地震や火山の噴火、津波や川のはんらんなどによる被害を予測した地図が、多くの県や市町村でつくられています。
万が一の災害に備え、普段から身近な地域の自然環境の特徴や起こりやすい災害を知っておくことも重要になりますので、意識して活用してみましょう。
★日本の地理的特色★
②人口の特徴
ある国や地域の人の数を「人口」と言います。
ではなんで「口」なのでしょうか?これは、古代の中国で、人の数を3人、4人と同じ感じで、三口人、四口人と呼んでいたからとも言われています。当時の王様からみて、大事なのは国民を飢えさせないことだったため、食料を必要とする者(=人)を「口」と呼んでいたようです。現在では、人口は「人の数の合計」を指すことが多いです。
今現在の世界の人口は約73億人です。
人口の分布はかたよりがあり、自然環境や産業の発達などの違いが影響しています。
日本は、人口密度が高い地域にあてはまります。
「人口密度」とは、ある国や地域の人口をその面積で割ったものをいいます。
日本を含む東アジアや南アジア、ヨーロッパも人口密度が高い地域となっており、その共通点は、農業や工業が発達していることが多く、都市部に特に人口が集中している点です。
一方、人口密度が低い地域は、世界各地にひろがる砂漠、ユーラシア大陸や北アメリカ大陸の寒冷地、高地などにみられます。
自然環境が厳しいこれらの地域は、作物の栽培や工場の立地に不向きで、人口が少なくなっています。
世界の人口の変化
先ほど世界の人口は今現在約73億人といいましたが、2050年には90億人を超えると予想されています。
これは、1950年代以降、世界の人口は急速に増加していますが、医療技術の進歩と、衛生や栄養の状態が改善されたことなどにより、死亡率が急激に下がったことが影響しています。
なかでもアジアとアフリカの増加が著しく、近い将来、現在世界No.1の人口(約14億人)を誇る中国を抜いて、インドが世界一になると予想されています。
地域によって異なる人口増加
「先進国」と「発展途上国」って聞いたことがありますよね。
日本やアメリカ、ヨーロッパ諸国のように、早くから工業が発達し、技術的にも経済的にも進んだ国を「先進国」といいます。
逆に、ヨーロッパ諸国の植民地だった東南アジアやアフリカの国々など、農業や鉱業が中心で、工業などは開発の途中にある国を「発展途上国」と言います。
中国や韓国が先進国か発展途上国かどちらに属するかは、多く議論されています。
但し、多くの発展途上国では、出生率(しゅっしょうりつ)と死亡率がともに高く、人口ピラミッド(縦軸に年齢、横軸に各年齢層の男女の割合を取り、国や地域の人口構成を示したグラフ)は、富士山型になります。
出生率が高いまま、医療の普及などによって死亡率が下がると「人口爆発」とよばれるような急激な人口増加をもたらします。
人口増加率が高くなると、食料や住宅などが不足し、農地や住宅地の拡大を目的とした環境破壊の問題が発生することもあります。
一方、日本を含む先進国の一部では、出生率と死亡率がともに低く、人口ピラミッドはつぼ型(人口減少型)となります。
これらの国の中には、子育てをしながらでも働きやすい環境をつくり、出生率を高めようとしている国もあります。
人口ピラミッドは、富士山型、つぼ型の他に、つりがね型もあります。
つりがね型(人口停滞型)は、ヨーロッパの先進国などにみられる出生率、死亡率ともに低い状態です。
日本の人口の変化
現在日本は、少子高齢社会を迎えたといわれています。
これは、高齢化とともに少子化が進み、15歳未満の年少人口が少なく、65歳以上の老年人口が多い人口ピラミッドでいえば、つぼ型の状態を指します。
日本はほかの国々と比べて急速に高齢化が進み、2015年には、総人口に対する老年人口の割合が25%(4人に1人が65歳以上)を超えて、世界でも高齢化が最も進んだ国の一つになっています。
老年人口の増加と生産年齢人口の減少により、労働力の不足や、年金や医療などの社会保障のような諸問題への対策が課題と考えられています。
尚、日本の総人口は、約1億2,615万人(2019年9月1日現在)で、世界でも有数の人口の多い国です。第二次世界大戦後、二度の「ベビーブーム」の時期には高い出生率を示し、人口は増え続けてきました。
また、食生活の改善や医療技術の進歩などによって死亡率は低下し、平均寿命は世界でも最も高い国の一つになっています。
しかしながら、出生率はしだいに低下しており、今後は人口減少が続くと予想されています。
日本の人口分布の特徴と課題
日本では、人口の大部分は平野や盆地に分布し、なかでも都市部に集中しています。
東京・大阪・名古屋を中心とする三大都市圏や、札幌・仙台・広島・福岡(頭文字を取って札仙広福(さっせんひろふく)などの地方の大都市には、大学や企業が多いことから、高度経済成長期には多くの人々が農村地域から移り住みました。
人口が集中して過密となった都市部では、住宅の不足や、通勤・通学時の電車やバスの混雑、交通渋滞が深刻な問題になっており、市街地の再開発や郊外の住宅地開発、新しい鉄道の整備、職場の郊外への移転などによって過密の解消を図っています。
一方、都市部へ若い人たちが流出した農村や山間部、離島などでは、老年人口の割合が高くなり、教育や医療、防災などの地域社会を支える活動が困難になる過疎(かそ)が問題となっている地域が増えています。
そのため、道路の整備や、若い人たちが働ける場所を増やすための企業の誘致(ゆうち)、IターンやUターンで都会から移住してくる人々への住宅の提供など、地域が一体となって多くの人々が定住できるよう努力をしています。
★日本の地理的特色★
③資源や産業の特徴
世界の資源・エネルギー
増加する資源の消費量
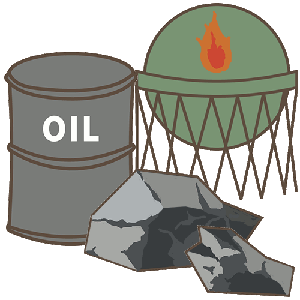
鉱産資源とは、金属の原料となる鉄鉱石や、電力や動力のエネルギー資源として利用される原油・石炭・天然ガスなどの鉱物のことをいいます。
日本やアメリカ合衆国など工業がさかんな国々では、大量の鉱産資源を消費します。また、自動車や家電製品の普及などによって人々の生活が豊かになるにつれて、1人あたりの消費量も増加します。
中国やインド、ブラジルなど新しく経済発展が進んでいる国々では、人口増加や工業化にともなって国全体での消費量が急速に増えています。
資源の生産と分布
鉱産資源の消費量については前の項でふれましたが、今度は生産量についてみていきたいと思います。
鉱産資源は、アメリカ合衆国や中国、ロシア、オーストラリアなどの国々で大量に生産されています。生産量には国土の広さだけでなく埋蔵量が関係しています。
例えば、エネルギー資源として重要な原油では、埋蔵量が多い西アジアのペルシア湾周辺に生産・輸出国が集まっています。
また、高度な工業製品の生産に欠かせないレアメタルは、採掘できる地域がさらに限られています。
このように、鉱産資源はかたよって分布していることが多く、資源を輸入に依存している国々がある一方、資源の輸出を経済の基盤にしている国もあります。
このことから、鉱産資源の生産は、国際市場の動きや国際情勢と深くかかわっており、採掘をめぐって紛争が起こることさえあります。
世界各地で進む資源の開発
資源の確保をめぐり、世界各地でさまざま開発競争が行われています。
中国では、石炭や鉄鉱石など多くの鉱産資源が生産されますが、国内の生産だけでは不足するようになったので、資源を世界各地から輸入しています。
さらに、将来の消費量の増加を予想して、アフリカでの資源開発に力を入れています。
採掘技術の発達によって、地下深くや海底など、これまで開発が難しかった場所でシェールガスやメタンハイドレードなどの資源を採掘することも可能となりました。
今後、各地でこれらの開発が始まると、世界各国の資源の生産や取引に大きな影響が出ることが予想されます。
再生可能エネルギーの活用
世界のエネルギー資源は、原油が中心的な役割を果たしています。
ただし、原油や石炭などは埋蔵量や採掘できる量が限られているので、有効に活用するための取り組みが行われています。
特に地球温暖化が問題になるなど環境への意識が高まったことで、風力や太陽光などの再生可能エネルギーの開発が進み、これらを利用した発電施設が増えています。
また、とうもろこしやさとうきびなどを原料にして生産されるバイオ燃料を自動車の燃料として使うことも多くなってきています。
日本の資源・エネルギーと電力
資源を輸入に頼る日本
1960年代までは日本国内でも石炭や銅などの採掘がさかんに行われていました。
しかし大規模な採掘が難しく、費用もかかるので、価格が安くて品質の良い外国産の資源が輸入されるようになって、国内の生産は衰退しました。
現在の日本は鉱産資源の多くを輸入にたよっています。
例えば、エネルギー資源として利用される原油や天然ガスは西アジアや東南アジアの国々、鉄鋼生産に必要な鉄鉱石や石炭はオーストラリアなどから輸入しています。
近年は、ロシアと協力して原油や天然ガスの開発を進めるなど、資源の輸入先を増やしていこうとしています。
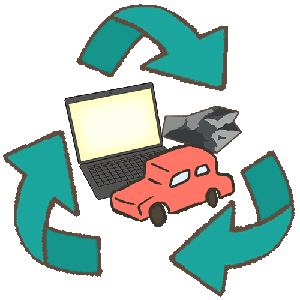
レアメタルは、生産国が少なく安定的に輸入するのが難しいので、国内で不要になった家電製品やコンピュータなどから回収して再利用(リサイクル・再資源化)するという対策もとられています。
また、資源の自給率を高めるために、日本近海では資源調査や採掘の実験が行われています。
生活を変える電力
生活のなかの身近なエネルギーである電力は、火力発電、水力発電、原子力発電などによって得られます。
水資源に恵まれた日本では、以前はダムの水を利用した水力発電も多かったのですが、高度経済成長期以後は原油や石炭、天然ガスを燃料にした火力発電が大きな割合をしめるようになりました。
その後、燃料価格の上昇や電力消費量の増加にともなって、原子力発電の拡大が進められてきました。
しかし、2011年の東北地方太平洋沖地震(東日本大震災)で発生した津波などによる、福島県での原子力発電所の事故をきっかけに、国内のほとんどの原子力発電所で一時的に運転が停止されるなど、原子力発電の利用が見直されるようになりました。
また、日本はエネルギー資源の自給率が低いという問題をかかえており、水力や風力、太陽光、地熱(ちねつ)といった再生可能エネルギーを利用した発電の拡大に期待が高まっています。
持続可能な社会の実現へ
持続可能な社会を実現するには、限りある資源と環境を将来にわたって利用できるようにすることが大切です。
資源が少ない日本では、再生可能エネルギーの活用とともに、資源の消費の見直しや、環境に配慮した省エネルギーの技術を生かした取り組みが行われています。
例えば、私たちの身のまわりでは、消費電力の小さいエアコンや冷蔵庫などの家電製品や、走行時に排ガスを出さない電気自動車の普及が進んでいます。
こうした技術は世界から高く評価され、工業化が進む発展途上国にも提供されています。
日本の農業・林業・漁業とその変化
日本の農業地域
日本の耕地の半分以上は水田で、水の豊かな平野を中心に全国各地に分布しています。
稲作(いなさく)がとくにさかんなのは、北陸や東北地方などで、各産地が競って品質のすぐれた米を生産しています。
有名どころでは、新潟県魚沼産コシヒカリや東北地方のひとめぼれ・あきたこまち等のブランド米などがあります。
山のふもとや扇状地(せんじょうち)では、日照(にっしょう)や水はけの良さを利用して、斜面での果樹栽培がさかんです。
冷涼(れいりょう)な地方のりんごや温暖な地方のみかん、雨の少ない地方のぶどうなど、各地の気候に合わせてさまざまな果物がつくられています。
大都市の周辺では、野菜生産などの近郊農業が発達してきました。
大都市からはなれた地域でも、交通の発達によって短時間で野菜や果物を市場に運べるようになったので、出荷時期にあわせて作物の生育を調整する促成栽培(そくせいさいばい)や抑制栽培(よくせいさいばい)を行っている地域もあります。
畜産(ちくさん)では、経営規模の小さな農家は少なくなっており、北海道や鹿児島県、宮城県などで大規模な畜産が行われています。
日本の農業の特徴や課題
日本では、せまい農場に肥料を効率よく使い、農作業の機械化を進めてきました。
そのため、日本は世界でも面積あたりの収穫量が多い国になりました。
しかし、国内産の農産物は生産費が高いので、価格が外国産を上まわり、農産物の輸入が増加しました。国内で行われている畜産でも、飼料(しりょう)の大部分は輸入されています。
その結果、日本の食料自給率は非常に低くなりました。
また、農業の就業人口の減少と高齢化が各地で進んでおり、農地の荒廃(こうはい)や放棄(ほうき)を防ぐために、農業の担い手を確保することが課題となっています。
一方、農産物の安全性や品質についても消費者の関心が高まっています。
農家は、農薬をあまり使わない栽培方法を採用したり、生産者についての情報を伝えたりする工夫をしています。
日本の林業と漁業の特徴や課題
森林に恵まれた日本では、日本三大美林と呼ばれるような「秋田すぎ」や「木曽ひのき」、「青森びば」などの特色ある木材が生産されています。
しかし、低価格の外国産木材の輸入が増えたことで、林業の就業人口は減り、高齢化も進んでいるようです。
また、日本は海に囲まれた島国ですが、暖流と寒流がぶつかる好漁場に恵まれ、漁業もさかんです。以前は沖合漁業や遠洋漁業がさかんでしたが、現在は多くの国が排他的経済水域(はいたてきけいざいすいいき)を設けて他国の漁業を規制するようになったので、国内の漁獲量は減って、水産物の輸入が増えています。
こうしたなかで、とる漁業から『育てる漁業』への転換が進められ、各地で養殖業や栽培漁業が行われています。近大マグロなどは、近畿大学水産研究所が2002年6月に完全養殖に成功したその代表例です。
ちなみに養殖業は、魚介類をいけす、いかだなどで人が育てて増やすことをいい、栽培漁業とは、海底に魚が集まる魚場をつくったり稚魚(ちぎょ=魚のベビー)や稚貝(ちがい=貝のベビー)を放流したりして沿岸の漁業資源を増やそうとする漁業のことをいいます。
日本の工業とその変化
日本の工業の特徴と工業地域
日本は、世界的にみても工業国の一つです。
歴史的には、繊維工業などの軽工業から始まり、外国との競争を行いながら、大きな設備が必要な重化学工業へと発展し、さらには高度な知識と技術が必要な先端技術産業へとつながってきました。
日本では、工業の発達した関東地方から九州地方北部にかけてのびる帯状の工業地域があり、太平洋ベルトといいます。
京浜(けいひん)・中京(ちゅうきょう)・阪神(はんしん)・北九州(きたきゅうしゅう)などの工業地帯を含み、早くから工業が発達してきました。
その後、自動車などの輸送機械工業やテレビ・冷蔵庫などの電気機械工業などの組み立て型の工業が発展してくると、その部品メーカーを中心に、輸送に有利な高速道路沿いにも工業団地が形成されるようになり、臨海部だけでなく内陸部にも工業地域が広がっていきました。
また、大都市の周辺には、人材や技術・市場の情報、特殊な部品などが集まりやすいというメリットから、企業が新技術の研究・開発をおこなうための研究所が建てられるようになりました。
変化する日本の工業
『ジャパン・アズ・ナンバーワン』は、戦後日本の高度経済成長の黄金期を象徴的に表す語としてしばしば用いられてきました。
そのぐらい数十年前の日本の工業は世界的にも高く評価されていたのです。
日本の工業は、原料や燃料を輸入して製品を輸出する加工貿易を通じて発展してきました。
しかし、1980年代にアメリカ合衆国やヨーロッパ諸国との間で貿易摩擦が激しくなると、自動車などの工業製品を日本国内で生産して輸出するだけでなく、海外にも工場をつくって現地向けに生産を行うようになります。
最初は、消費国である北アメリカやヨーロッパの国々を中心に進出していきましたが、その後は賃金や価格の安いアジアの国々に広がり、生産は拡大しました。
こうして、日本企業の海外工場や、低価格の外国企業からの工業製品の輸入が増えていきました。その結果、産業の空洞化とよばれる現象がみられるようになり、一部の工業では日本国内の生産が衰退しています。
特にアジアの国々の工業化がめざましく進み、家電製品などの一部の分野では韓国や中国などの企業に追い上げ、追い抜かれてきています。
一方で、日本の高い技術力やすぐれた性能が高く評価されている分野もまだ多く残されており、そのような分野では外国への技術提供などもさかんに行われています。
日本の商業・サービス業
日本の産業は商業・サービス業が中心
日本をはじめとする先進国では、生活を豊かにする第3次産業が大きな影響力をもつようになっています。
第3次産業とは、小売業・卸売業などの商業や、運輸・郵便業、さらには宿泊・飲食サービス業や医療・福祉、教育などのサービス業を指します。
ちなみに第1次産業は、農業・林業・漁業のことをいい、第2次産業は、鉱工業・建設業などのことを言います。
現在の日本では、第3次産業(商業・サービス業)の就業者の数がほかの産業と比べても多くなっています。特に、経済の中心でもある首都の東京や、観光地でもある北海道や沖縄では、第3次産業の就業割合も高くなっているようです。
日本の商業の変化
商業は、生活の変化や技術の発達により、営業の仕方や店のできる場所も変わってきています。
例として、セブンイレブン、ファミリーマート、ローソンなどのコンビニエンスストアは、今でこそ全国的に当たり前に普及していますが、その背景としては、さまざまな時間帯で生活する人々が増えたといった生活の変化や、コンピュータによる通信や商品管理、商品の配送がひんぱんにできるようになったという技術の発展も影響しています。
また、これまでは駅前や都市の中心部に古くからある商店街やデパートにおいて、多くの買い物客でにぎわいをみせていましたが、自動車の普及により、郊外の大型ショッピングセンターや専門店を利用する人も増えています。
そのため、地方の商店街には活気を失っているところもあるようです。
さらに最近では、通信販売のようなテレビやインターネットを利用したリアルな店自体をもたない商業も規模を拡大しています。
拡大するサービス業
サービス業の中でも、情報通信技術(ICT)関連産業は、とくに急速に拡大しています。
ちなみにICTとは、Information and Communication Technologyの略です。
電話やインターネットでの情報検索やメールの送受信、ニュースの配信、商品の売買、広告などはICTによって支えられています。
例を挙げればキリがありませんので、みなさんも具体的ICT企業をイメージしてみて下さい。その規模は、ほかの産業を上まわるまでになっています。
尚、大都市や観光地に多い宿泊施設、飲食店、お土産物屋さんのように、サービス業は特定の場所に集中する傾向があります。
しかし、同じくサービス業ながらも医療機関や福祉関係のようなサービス業は、人々の暮らしに直接関係するため、生活者の近くにある必要があります。
そのため、これらの暮らしに必要なサービスは、全国的に均等に分布するように配慮されています。
★日本の地理的特色★
④地域間の結びつきの特色
世界と日本の交通・通信網
交通による世界の結びつき
現在の世界では、交通網の発達により、国境を超えた物や人の移動が活発になっています。
移動手段は、陸・海・空とそれぞれ手段がありますが、島国の日本は、ほかの国との取引に陸は使えませんよね。
周囲を海で囲まれた日本は、世界でも有数の海運国です。
原油や石炭などの燃料、鉄鉱石などの原料の輸入や、大型機械などを輸出したりするときは、安く大量に輸送できるタンカーやコンテナ船を使った海上輸送が利用されています。
一方で、IC(集積回路 Integrated Circuit)などの電子装置や貴金属、鮮度を保つことが重要な魚介類・生花(せいか)など、軽くて高価なものを運ぶ航空貨物の輸送量が増えており、貿易においては航空輸送も重要になっています。
日本と世界各地の間で航空路線や便数が増えたことで、日本から海外へ仕事や観光で出かける人が増加しただけでなく、逆に日本に近い中国や韓国、結びつきの強いアメリカ合衆国などから日本を訪れる人も増加しています。
日本では、多くの空港が海外の都市と航空路線で結ばれていますが、その一方で、シンガポール、バンコク、ホンコン(香港)やソウル、などアジアの他の大規模な国際空港とのハブ空港をめぐる競争も激しくなっています。
ハブ空港とは、このような世界各地からの航空路線が集中し、乗客や貨物を目的地となるほかの空港に中継する機能を備えた地域の拠点となる空港のことを言います。
ちなみにハブの由来は、自転車の車輪の中心部にあって、スポークが取り付けられている回転体のことを言います。ハブ空港を拠点に各地へ放射線状に伸びていく航空路線網を自転車の車輪の中心にあるハブに見立てて名付けられたようです。
国内の交通網の発達と生活の変化
日本では、高度経済成長期以降、新幹線や空港の整備、高速道路の建設などが進み、都市間を結ぶ交通網が整備されてきました。
国内の地域間の移動にかかる時間が大幅に短縮され、日帰りで行き来できる地域が拡大するなど、皆さんの生活や経済活動にとっても、たいへん便利になりました。
また、高速道路網の整備によって、国内の貨物輸送にしめる自動車輸送の割合が高くなりました。1960年頃は、貨物輸送にしめる自動車輸送の割合が15%程度しかなかったのに対し、2015年には、約60%になったことを示す統計データも存在します。
製品の輸送に便利な高速道路沿いには、巨大なトラックターミナル、自動車や電気機械の工場などが立地したり、大型のショッピングセンターが開業したりして、地域経済には大きな変化がもたらされたところもあるようです。
一方で、ほかの先進国と比べると日本は、旅客輸送にしめる鉄道の割合が今もなお高いという特徴があるようです。
それは新幹線などが利用出来る近・中距離の都市間輸送と、大都市圏内の通勤・通学などの輸送において、鉄道がよく利用されているからです。
しかし、地方の過疎(かそ)地域では、利用者の少ない鉄道やバスの路線が廃止されたり、便数が減らされたりして、病院や買い物に行くのが不便になったところもあるようです。
通信網の発達と生活の変化
パソコンや携帯電話・スマートフォンなどの情報通信機器の普及によって、インターネットや国際電話の利用者は急速かつ大きく増えています。
大陸間の国際通信には、通信衛星と海底ケーブルが利用されています。
特に、海底ケーブルの設置が急速に進んでおり高速で大容量の光ファイバーケーブルなどが使われています。
実際に、海外のニュースやスポーツのテレビ放送、インターネット通信などの国際通信は、それまでの通信衛星にかわって、海底ケーブルが使われるようになってきました。
情報通信技術(ICT=Information and Communication Technology)の発達と通信網の整備にともなって、皆さんの生活も大きく変化してきています。
インターネットの普及により、山間部や離島でもインターネットを使って通信販売で商品を購入したり、お医者さんの遠隔診断を受けたりすることができるようになったりしました。
また、新聞やテレビなどによる配信が中心だったニュースや日常生活にかかわる情報も、インターネットを利用した配信が増えてきています。
たしかに、ICTの発達はみなさんの生活の向上に役立っていますが、インターネットを利用できる人と利用できない人との間で情報格差も生まれだしています。
中学2年生の【地理】
日本の諸地域
★日本の諸地域★
①九州地方
九州地方の自然環境
海に囲まれて火山が多い九州地方
九州地方には、地形や気候にどのような特色があるのかをみていきましょう。
九州地方は日本の南西部に位置し、南北に長く広がった形をしています。
中央部には、阿蘇山(あそさん)の巨大なカルデラがあります。
カルデラとは、火山の爆発や噴火による陥没(かんぼつ)などによってできた大きなくぼ地のことをいいます。
中央部の南には、九州山地のけわしい山々がつらなっています。
西部には雲仙岳(うんぜんだけ=普賢岳 ふげんだけ)、南部には霧島山(きりしまやま)や桜島(さくらじま)といった火山があり、現在も活発に活動していて、たびたび噴火しています。
九州北西部の海岸はリアス海岸で、その西に広がる大陸棚をもつ海域に面した長崎県は、日本でも有数の漁獲量をほこっています。
佐賀県の南には、日本最大の干潟(ひがた)をもつ有明海(ありあけかい)があり、養殖のりの日本一の産地として有名です。
鹿児島県と沖縄県からなる南西諸島には、数多くの島々があり、サンゴ礁の海など豊かな自然を求めて、多くの観光客が訪れる島もあります。
沖縄の南西にある宮古島などは、「宮古島バブル」というニュースをテレビなどで聞いたことがある人もいると思いますが、観光客の大幅増で家賃も高騰しているようですね。
九州北部は比較的なだらかな地形となっており、筑紫(つくし)平野などが広がり、福岡市を中心に多くの人口が集中しています。
また、東西の海岸沿いに広がる宮崎平野や熊本平野では、ビニールハウスを利用した野菜栽培などの農業もさかんに行われています。
促成栽培で生産される熊本のトマトなどは、日本一の生産量をほこっています。
温暖な気候と自然災害
九州地方は、冬でも比較的温暖です。これはともに暖流である黒潮(くろしお)と対馬(つしま)海流が九州地方の周りを東と西に流れていることと関係します。
このため毎年2月になると、多くのプロ野球(例えば宮崎では、巨人・カープ・ソフトバンク・オリックス・西武)やJリーグなどのチームが、暖かい九州南部や南西諸島で、合宿しながら練習をするキャンプを行っています。
一方、夏の九州地方は、南の太平洋上から湿った季節風が吹いて、多くの雨が降るようです。
雨は、梅雨(つゆ、ばいう)の時期から台風が通過する時期にかけてとくに多く、集中豪雨によって洪水や土砂崩れなどの自然災害が起こることもたびたびあります。
自然と共にある人々の生活
火山による温泉の恵み
九州地方の北東部に位置する大分県には、別府(べっぷ)温泉や湯布院(ゆふいん)温泉など、全国でも有名な温泉観光地がいくつもあります。
これは、火山が多い九州地方の特色で、なんと日本の温泉の源泉数の4割近くが集中しているからだそうです。
昔から温泉は貴重な観光資源として、地域経済を支えてきました。こういった温泉地などに向け、列車や観光を組みあわせた観光が栄え、九州新幹線や「ななつ星in九州」、「ゆふいんの森」など、さまざまな特色ある列車が運行されています。
由布院駅では、ホームで足湯も楽しめるなどの工夫もされています。いろいろな演出の盛り上げによって、日本国内だけでなく海外からの観光客の人気も集めているようです。
火山と共に生きる鹿児島の人々
九州地方の南部には、桜島(さくらじま)が鹿児島湾につき出すように位置しています。
桜島は、頻繁に噴火を起こす火山として有名で、2015年には1年間で1252回も噴火したようです。
鹿児島市は、この桜島から4kmほどしか離れていないため、噴火による火山灰が屋内に入らないように窓を閉め切ることも多く、市内の小中学校などではエアコンの設置が早くから進められてきたようです。
また、テレビの天気予報などで桜島上空の風向きを確かめてから、屋外に洗濯物を干してもよいかどうかを判断しているそうです。
桜島の近くでは火山灰への対応などの生活上の苦労もあるのも事実ですが、火山の周辺地には温泉地があり、観光業に生かされるなど大きな恩恵をもたらしてくれるという点も特長です。
自然の恵みをエネルギーに活かす
火山は、観光資源以外にも電力などを生み出すエネルギー産業にも活用されています。
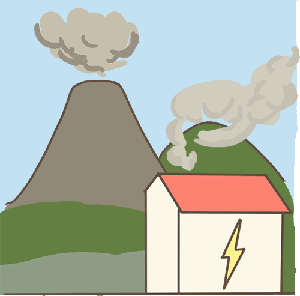
九州地方には、国内の地熱発電所の4割が集中しているなどの特色があり、地熱発電がさかんです。大分県には、地熱発電としては日本最大級の八丁原(はっちょうばる)地熱発電所などがあります。
また九州地方では、太陽光発電もさかんで、鹿児島県や福岡県などでは、メガソーラーと呼ばれる大規模な太陽光発電所が建設・運転されています。
ちなみに1メガワット(1MW=1000kW)以上の大規模な電力が出力される太陽光発電のことをメガソーラーと呼んでいます。
一方、佐賀県では、太陽光発電のパネルを付けた住宅を建てる市民に自治体が補助金を出すなど、再生可能エネルギーの積極的な導入を後押ししていて、住宅用太陽光発電の普及率は全国1位(2014年)となっているようです。
温暖な気候を活かした農業
畜産が盛んな九州南部
鹿児島県の「かごしま黒豚」、宮崎県の「宮崎牛」や地鶏(じどり)など、ブランド肉が有名ですが、九州南部は、豚や鶏、肉牛の飼育が日本で最もさかんな地域となっています。
冬でも温暖な気候というのが重要で、放牧や子豚の育成に最適な環境と言われていています。
個人の畜産農家だけでなく、ハムなどを加工する食品会社やスーパーマーケットなどを運営する会社が、牧場を直接経営したり、個人農家と契約したりして大規模な畜産を行っています。
但し、近年では、海外からも安い食肉が大量に輸入されるようになってきたので、畜産農家は効率よく安い食肉を育てるだけではなく、おいしくて安全な食肉の生産に力を入れるようになってきていて、各地で先ほど挙げたような食肉のブランド化を図る動きが強まっています。
九州南部は、温暖な気候を生かした野菜の促成栽培がさかんな地域となっています。
促成栽培とは、夏にできる作物を冬に作って出荷するなど作物の収穫期を早めて市場の経済性を高める栽培方法を言います。
宮﨑平野などではきゅうりやピーマンなど、熊本平野ではトマトやすいかなどが生産されています。
シラス台地での畑作と畜産
九州南部には、シラスとよばれる古い火山の噴出物によってできた台地が広く分布しています。シラスは50m~100mくらい厚く積もる場合が多く水分を保ちにくいので、昔からシラス台地での農業にはたいへんな苦労があったようです。
第二次世界大戦後には、このシラス台地の開発が食料を増産するために進められました。
例えば、鹿児島県の笠之原(かさのはら)では、ダムや農業用水を整備することによって、それまでの栽培の中心であったさつまいもに加えて、野菜や茶など高い収益が見込める作物の栽培や、飼料用作物の栽培とあわせた畜産がさかんに行われるようになりました。
同様に、薩摩半島南部での台地でも笠之原のように大規模なかんがい事業が行われたため、茶の生産は増加し、鹿児島県は静岡県についで国内第2位の茶の生産県へと成長するまでになりました。
稲作が盛んな九州北部
日本における稲作は、中国から朝鮮半島南部を経由し九州北部に到来したと言われています(諸説あります)。
その後、新潟県や東北地方や北海道へ徐々に最適な産地を求めながら北上していったそうです。
そのため、九州北部にあり佐賀県と福岡県にまたがる筑紫(つくし)平野は、今でも代表的な九州地方の米の産地となっています。
]
筑紫平野では、冬でも温暖な気候を利用して、コメの収穫が終わったあとの水田で小麦や大豆などの二毛作(にもうさく)が昔から行われてきました。
また、「あまおう」や「さがほのか」などのブランドいちごの名前は聞いたことがあるとは思いますが、国内だけでなく、香港や台湾などの外国へも出荷されるくらい人気があります。
大消費地である福岡市などへの地理的な近さを活かし、ビニールハウスを利用したいちごやなすなどの生鮮野菜の栽培もさかんになっています。
都市や工業の発展と自然環境
港町から発展した福岡
九州地方は地理的にユーラシア大陸に近いので、稲作もそうでしたが、昔から中国や朝鮮半島の文化の受け入れ口となってきました。
福岡市の海の窓口である博多湾は、志賀島(しかのしま)や海の中道(なかみち)に囲まれた地形となっているので、季節風による荒波がおし寄せる冬でも波がおだやかで、船が行き来しやすい天然の良港となっています。
このため福岡市は古代から大陸との貿易を行う港町として発展し続けてきました。
現在の福岡市は、150万の人口を持つ九州地方最大の都市となっています。福岡都市圏といわれるくらいまで、福岡市を中心として市街地が広がっています。
中心部には政府の出先機関や企業の支社・支店、商業施設や文化施設、大学などが集まっていて、周辺市町村から毎日多くの人が通勤・通学しています。
また、陸の窓口である福岡市の博多駅は、九州新幹線をはじめとする鉄道で、九州地方の各地とつながっています。
近接した空の窓口である福岡空港からも、国内やアジア各地へ向けて、数多くの航空路線が開設されています。
福岡市は、観光や仕事などの目的で吸収を訪れる人々の玄関口となっていて、近隣諸国との交流もさかんなまちとなっています。
資源を活かした工業の発達と変化
九州北部では地層に多くの石炭がふくまれているため、江戸時代から筑豊(ちくほう)炭田をはじめとする多くの炭田で、石炭の採掘が行われていました。
明治時代になると、筑豊炭田や鉄鋼石の輸入先であった中国にも近かったことから、現在の北九州市に官営(かんえい)の八幡製作所がつくられました。
ちなみに官営とは、民間企業ではなく、政府が経営することを言います。
この八幡製鉄所を中心として鉄鋼業が発達した地域は、北九州工業地帯とよばれています。
北九州工業地帯は、昔から九州地方の工業の中心的な役割を果たしてきました。
第二次世界大戦後は、国内の他地域や外国の鉄鋼業の発達によって北九州工業地帯の工業生産が伸び悩み、公害に苦しんだ時期もあったようです。
しかし現在では、公害を克服した経験を生かし「環境都市」を目指した環境保全の取り組みや、進んだ資源のリサイクルなどの環境技術で注目される地域になっています。
臨海部につくられた「北九州エコタウン」では、あらゆる廃棄物(はいきぶつ)を産業の原料として活用することで、最終的に廃棄物をゼロにすること(ゼロ・エミッション)を目指した事業が行われ、海外での公害対策にも積極的に協力しています。
1970年代頃の特徴としては、九州各地にIC(集積回路 しゅうせきかいろ)の工場が急増しました。ICとは、スマートフォンなど、ほとんどの電気製品に組みこまれていて、製品の「頭脳」にあたる大切な役割を担っています。
しかしながら、1990年代以降は外国企業との競争が激しくなり、組み立て作業などをアジアの国々に移転させる企業が増え、九州地方のIC生産は停滞ぎみとなっています。
一方で、九州北部の臨海部を中心として輸出に便利な点を生かし、自動車関連工場が増えてきています。生産された自動車は、アメリカ合衆国や中国などに輸出されています。
北九州工業地帯も時代や環境にあわせてその時における最適な形へと変化してきています。
南西諸島の自然環境と生活や産業
南国の自然がみられる南西諸島
九州の南端にあたる大隅(おおすみ)半島より南にある鹿児島県の島々と、沖縄県の島々からなる南西諸島は、日本の中でも他地域とは異なる自然環境が豊富にあります。
サンゴ礁がみられる暖かい海や、マングローブやハイビスカスとった南国の自然を体験できます。青い海と白い砂浜が人気のビーチリゾートなどが多数ありますが、白い砂浜は、サンゴや貝がらなどが波によってくだかれて細かくなり、海岸に打ち寄せられたものだそうです。
南国リゾートの良いイメージばかりが先行しがちですが、南西諸島は、台風の影響も多く受ける地域でもあります。
最近は、鉄筋コンクリートの住宅が多くなってきましたが、人びとは昔から家を石垣(いしがき)で囲ったり、屋根のかわらを漆喰(しっくい)でかためたりして、台風の暴風に備えてきたようです。
南国の自然を活かした産業
西諸島では、南国の自然環境を生かした特色ある産業が発達しています。
農業では、1年中温暖な気候を生かしたさとうきびやパイナップルの栽培のほか、沖縄島で栽培されている菊など、高収入が見込める花や野菜などの生産が増加していて、航空機を使って東京などへ出荷されています。
観光業も重要な産業で、とくに沖縄県では、観光収入が地域経済を支えています。
一方で、開発によって海がよごれるなどの問題も発生していて、開発と自然環境の共生が大きな課題になっています。
アジアとの交流の歴史
15世紀前半から17世紀初めにかけて、現在の沖縄県と鹿児島県の奄美(あまみ)群島は、琉球(りゅうきゅう)王国という独立国でした。
そのため、日本の九州地方とは別に南西諸島は、中国や東南アジアの国々とも黒潮の流れや季節風を利用して船で交流していました。
首里城跡(しゅりじょうあと)などの琉球王国時代の史跡(しせき)は世界遺産にも登録されています。
その他にも、織物・染め物などの伝統的工芸品、方言や郷土料理など、独特な文化が今でも色濃く残っていて、貴重な観光資源にもなっています。
また沖縄は、第二次世界大戦時に戦場となった歴史があり、現在でも、沖縄島の約15%程度の広大な土地にアメリカ軍の軍事基地がおかれています。
市街地に隣接した軍事基地では、航空機の離発着による騒音など、地域住民との間にさまざまな問題が生じています。
辺野古など沖縄基地問題に関するトピックスもよくニュースで流れていますので、皆さんも気にかけてみて下さい。
★日本の諸地域★
②中国・四国地方
中国・四国地方の自然環境
3つの海・2つの山地・3つの地域
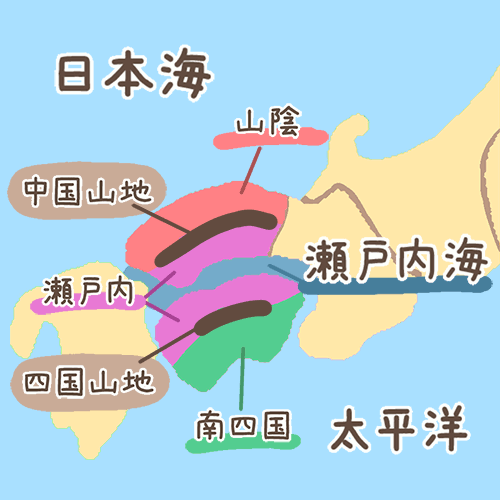
中国・四国地方の地形の特徴として「3つの海」「2つの山地」「3つの地域」をまずは覚えましょう。
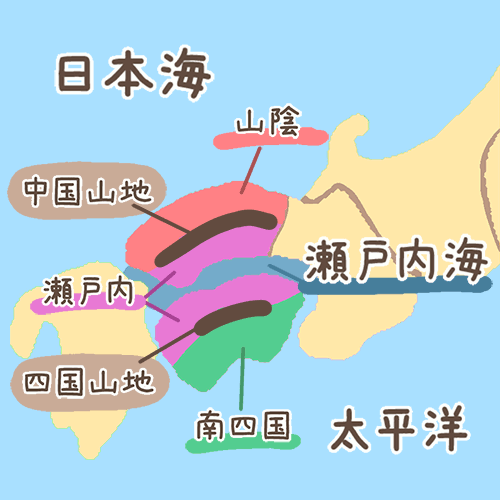
2つの山地・・・ 中国山地・四国山地
3つの地域・・・山陰・瀬戸内・南四国
尚、中国山地と四国山地の違いは以下の通りです。
中国山地は、火山である大山(だいせん)などを除いて、なだらなか山が多く、高原では肉牛の飼育や酪農が行われています。
四国山地は、中国山地よりもけわしい山が多く、吉野川や四万十川(しまんとがわ)が深い谷をつくりながら海へと注いでいます。
四国山地の南側(南四国)は、高知平野をのぞいて平野が少なく、海岸付近まで山がせまっているという特徴があります。
瀬戸内海には大小3000ほどの島々が点在し、美しい景観がみられます。
瀬戸内海は、都のあった近畿地方と、九州地方や大陸とを結ぶ重要な交通路として、昔から船を使った人や物の往来が頻繁でした。今も旅客フェリーや貨物船がさかんに運行されています。
3つの地域で異なる気候
3つの地域「山陰」「瀬戸内」「南四国」では、それぞれ気候が異なります。
「山陰」は、日本海に面しており、冬に吹く北西からの季節風の影響で、雪や雨の日が多く、山沿いを中心にたくさんの雪が積もります。
「瀬戸内」は、中国山地と四国山地にはさまれており、夏と冬の季節風が山地によってさえぎられるので、晴天の日が多く、日本の中でも降水量が少ない地域となっています。そのため、水不足になりやすく、讃岐(さぬき)平野などでは、かんがい用にため池や用水路をつくって農業が行われてきました。
「南四国」は、太平洋に面しており、沖を流れる暖流の黒潮(くろしお)の影響で、1年中温暖です。四国山地の南側では、南東からの季節風の影響で、多くの雨が降ります。また、台風の通り道となることもあり、暴風や大雨に見舞われることもたびたびあります。
交通網の整備と生活の変化
高速道路の整備と本州四国連絡橋の開通
中国・四国地方は、東西方向を中心に陸上交通が発達し、九州地方や近畿地方との間は、山陽自動車道や山陽新幹線、関門橋(かんもんきょう)・関門トンネルなどによって強く結びついています。
近頃は、米子(よなご)自動車道や浜田自動車道、高知自動車道など、南北方向への高速道路の整備が進み、人や物の移動がさらに活発になってきています。
瀬戸内海においては、昔から海上交通がさかんでしたが、本州四国連絡橋の開通によって、本州と四国、瀬戸内海の島々の間の移動時間は大幅に短縮されています。
具体例として、岡山県岡山市と香川県高松市との移動には、鉄道や自動車とフェリーとを乗りかえて2時間以上かかっていましたが、瀬戸大橋の開通後は1時間以内で移動できるようになったようです。その結果、岡山県と香川県の間では、自動車や鉄道で瀬戸内海をわたって通勤・通学する人も増えたようです。
ちなみに、本州四国連絡橋は、本州と四国を結ぶ橋の総称です。
神戸-鳴門(なると)、児島-坂出(さかいで)、尾道(おのみち)-今治(いまばり)の三つのルートがあります。
橋の開通による島での生活変化
本州四国連絡橋の開通により瀬戸内海の島で暮らす人々の生活は大きく変化しています。
島民の日常的な移動手段は、それまでフェリーでしたが、自動車へと変化し、買い物や通勤・通学などの際にフェリーの時間を気にせず移動できるようになりました。
逆に、これまでの移動手段であったフェリーの利用者が減少したため、航路の多くは廃止されたり便の数が減ったりしたので、自動車を持たない人や高齢者など、移動をフェリーに頼っていた人々にとっては生活が不便にもなったようです。
そのため、生活用品を輸送する船や、病院の役割をもつ診療船など、島を行き来する定期船は、今でも島の人々の生活に必要不可欠なものとなっています。
他の地域との結びつきの変化
交通網の発達は、中国・四国地方だけでなく他地域との結びつきにも影響を与えています。
広島県尾道(おのみち)市と愛媛県今治(いまばり)市を結ぶしまなみ海道は、徒歩や自動車で瀬戸内海の島々をわたることができ、美しい景観を見ることを目的に訪問する観光客が増加しています。
このため、しまなみ海道沿いの島々では、農業や漁業の体験、瀬戸内海をめぐる観光船など豊かな自然や水産資源を生かした観光業が発達しているようです。
四国の北東部に位置する徳島県では、大鳴門橋(おおなるときょう)と明石海峡大橋(あかしかいきょうおおはし)の開通により、神戸や大阪への移動時間が短縮されたので、高速バスを利用して日帰りで出かける買い物客が増えています。
一方で、「阿波(あわ)おどり」などの夏のお祭りや山間部での農業体験など、観光を目的に全国各地から徳島県を訪れる人々も増えており、観光業は地域を支える重要な産業の一つとなっています。
海外と結びついた瀬戸内の工業
海運と結びつく瀬戸内の工業
瀬戸内海沿岸地域では、古くから海上交通が発達していて製塩業や綿織物工業、造船業などがさかんでした。
第二次世界大戦後は、塩田(えんでん)のあと地や遠浅(とおあさ)の海岸を埋め立ててつくられた広大な土地に、阪神工業地帯などからの工場の移転が進み、瀬戸内工業地帯がつくられました。
臨海部は工場が集中し、大型貨物船で海外から鉄鉱石や原油などを大量に輸入したり、重い工業製品を国内外に輸送したりしやすいので、石油化学工業や製鉄業、自動車工業などの重化学工業の立地に適しています。
例えば、岡山県倉敷市や山口県周南市、岩国市などに石油化学コンビナートが、広島県福山市や呉(くれ)市などに製鉄所がつくられました。
倉敷市の水島地区にはさまざまな分野の工場が集まり、鉄鋼や自動車、食品なども生産されています。
国内外に輸送される工業製品
平和記念都市としても有名な広島市とその周辺には自動車関連工場が集まっています。
この地域では昔から工業が発展し、高い技術をもつ労働者が多かったことが、自動車工業の発達をプッシュしました。
自動車の組み立ては、広島市と山口県防府(ぼうふ)市の工場で行われ、完成した自動車は工場のそばにある大きな港から国内や海外にも輸出されています。
山口県下松(くだまつ)市には、造船業がさかんだった利点を生かし、造船工場の施設を利用した鉄道車両の工場があります。
工場では、国内各地を走る特急列車や新幹線、海外向けの高速鉄道などの車両がつくられており、完成した車両は大型貨物船やトラックで各地に輸送されます。
海外との競争と新しい取り組み
中国や韓国をはじめ、タイやインドネシアなどのアジア各地では、石油化学コンビナートの大規模な建設が進んでいます。
そのため、瀬戸内工業地域の化学メーカーは、外国との競争に勝ち残るために、機能や性能が高い製品の開発に力を入れています。
例えば、山口県宇部(うべ)市や愛媛県新居浜(にいはま)市の工場や研究所では、高度な技術を必要とする医薬品や化学肥料などの開発が行われています。
このほか、電気自動車用の蓄電池(ちくでんち)や航空機の機体などに使われる軽くてじょうぶな炭素繊維といった環境にやさしい製品の開発も進められています。
全国展開を進める農業
瀬戸内の果樹栽培と全国天下
全国のスーパーマーケットやデパートでは、年間を通して、愛媛県をはじめ全国各地で作られた「みかん」や「いよかん」などのかんきつ類とその加工品が販売されています。
瀬戸内の気候は、日照時間が長く、降水量が少ないという特徴があり、これらのかんきつ類の栽培に特に適しているため、日あたりの良い丘陵地(きゅうりょうち)の斜面にはみかんなどの果樹園が段々畑として広がっています。
瀬戸内で生産されるかんきつ類は、以前はみかんが中心でした。しかし国内のほかの産地との競争や、海外から輸入されるオレンジの増加などによって、みかんの価格が下がり、みかん農家は大きな影響を受けた時期がありました。
そこで愛媛県では品種改良を重ね、収穫時期をずらすことによって「いよかん」や「せとか」(みかんの大トロや最高峰と呼ばれている高級品)など、さまざまなかんきつ類が生産されるようになりました。
一方で、岡山県の丘陵地では、夏に一斉に出荷されるマスカットや白桃(はくとう)などの果物の栽培がさかんです。
これらのブランド果物は、全国のデパートなどで高額で販売されるので、病気や害虫によって実が傷つかないように手間をかけて栽培しています。
また、市場の拡大にも力を入れていて、東南アジアの国々にも輸出するなどしています。
大都市と結びつく高知平野の野菜栽培
高知平野は、南四国に位置し温暖な気候となっており、その利点を生かした野菜の栽培がさかんです。
高知平野に広がるビニールハウスでは、なすやピーマンなどの夏が旬である野菜の促成栽培(そくせいさいばい=出荷時期を人工的にずらす)が行われています。
これらの野菜は、冬から春にかけて高額で販売することができ、夏の露地(ろじ)栽培と組み合わせて、農家は安定した収入を得ることができます。
高知平野で生産された野菜は、昔は船や鉄道でおもに大阪の市場へと運ばれていました。しかし、現在は高速道路や橋が開通し、保冷トラックが普及したため、鮮度を保ったままで東京や新潟など遠くの市場にも出荷されています。
また、栽培する野菜の種類を増やし(例えば「しょうが」「おくら」「ししとう」など)、年間を通して安定した出荷を可能にしています。
観光客を呼び寄せる取り組み
山間部や離島で進む過疎化
中国・四国地方、とくに中国山地や四国山地の山間部や瀬戸内海の離島では、若い世代を中心に、進学や就職のために広島や岡山、近畿地方などの都市部へ移り住む人が増え、人口減少や高齢化が問題となっています。
このような現象を、過疎化(かそか)と言います。しかし、観光客を呼び寄せたり、定住希望者を受け入れたりするなどの地域おこしも対策の一例として各地で取り組まれています 。
一言で過疎といっても地域によって状況が異なるので、地域に応じた対策をとることが重要になります。
交通網の発達による観光地の変化
島根県東部の出雲(いずも)地域は、「神話の里」と言われています。
縁結びの神さまとして知られる出雲大社(いずもたいしゃ)など数多くの文化財や史跡(しせき)があります。
米子(よなご)自動車道や浜田自動車道など南北を結ぶ高速道路や、各地に整備された空港を利用して、この地域を訪れる環境客が増加しています。
島根県西部の石見(いわみ)地域では、神話などをもとにした伝統芸能の石見神楽(いわみかぐら)や、世界遺産に登録された石見銀山(いわみぎんざん)が注目されたことから、県外からも多くの観光客を集めるようになりました。
江戸時代に城下町として繁栄した、山口県萩(はぎ)市や島根県津和野(つわの)町、松江市などは、現在も歴史ある町なみとして武家屋敷や商家が保存されています。
その当時のようすを伝えていて、多くの観光資源となっています。
観光客を呼び寄せる地域おこし
鳥取県には、日本最大級の砂丘が広がる鳥取砂丘や、なしの観光農園など、さまざまな観光資源があります。
なかでも境港(さかいみなと)市は、「ゲゲゲの鬼太郎」の生みの親、水木しげる氏の出身地という特徴を生かし、地域おこしに取り組み「妖怪の町」とも呼ばれています。
「妖怪の町」の中心「水木しげるロード」は妖怪ブロンズ像をはじめ、お店も交番も、はたまた外灯から公園まで、何から何まで妖怪づくしの町ごとテーマパークとなっており、島根県有数の観光地となりました。
境港市の観光客が増加した大きな理由の一つとして、周辺の地域での交通網の整備があります。境港市は米子空港から近かったことに加え、周辺の高速道路が開通したことによって、観光客が遠くからも訪れやすくなりました。
また、境港市は漁業もさかんで、新鮮な魚介類や水産加工品も観光客を引きつける理由のひとつとなっています。
こうした境港市の総合的な取り組みは、産業の活性化にも役だっており、全国的な地域おこしのモデルとして注目を集めています。
★日本の諸地域★
③近畿地方
近畿地方の自然環境
南北の山地と中央部の低地
近畿地方の自然環境の特徴として、北部には中国山地から丹波(たんば)高地にかけてなだらかな山地が続き、南部にはけわしい紀伊(きい)山地があげられます。
北部や南部では山地が海岸近くまでせまっており、志摩(しま)半島や若狭湾(わかさわん)には、海岸線が複雑に入り組んだリアス海岸が広がっています。
北の中国山地・丹波高地や南の紀伊山地に囲まれた中央部は低地となっており、京都盆地や奈良盆地などの盆地、大阪平野や播磨(はりま)平野などの平野が広がっています。
これらの盆地や平野は、古代から近畿地方の人々の生活の場の中心となってきました。
また、「近畿の水がめ」とよばれる国内最大の湖である琵琶湖(びわこ)は、近江(おうみ)盆地にあります。
ここから大阪湾へと流れる淀川(よどがわ)をはじめとする水系は、近畿地方の流域の人々の生活用水として、古くから利用されてきました。
また、大阪湾と瀬戸内海を分ける淡路島(あわじしま)は近畿地方で最も大きな島となっていますが、明石海峡大橋(あかしかいきょうおおはし)を通じて本州と結ばれ、四国地方とも大鳴門橋(おおなるときょう)で結ばれています。
南北の山地を境に分かれる気候
近畿地方の気候は、北部・南部・中央部で違います。
近畿地方の北部は、冬には北西からの季節風の影響により雪が多く、山沿いには多くのスキー場があります。
一方、近畿地方の南部は、暖流の黒潮(くろしお)の影響で冬でも温暖で、みかんや梅などの果樹園のほかに、白い砂浜や温泉を生かしたリゾートがみられます(例えば、和歌山県白浜町の海水浴場などをイメージしてみて下さい)。
夏には南東からの季節風の影響で、紀伊半島の南東側では降水量が非常に多く、すぎやひのきなどの樹木を育てる林業もさかんになっています。
近畿地方の中央部は、盆地を中心に夏は暑さが厳しく、冬は冷え込み、1年の気温の差が大きいのが特徴です。
また、南北の山地にはさまれており、年間を通して降水量が少ないので、水不足を克服するために、各地でため池や用水路といったかんがい施設が整備されてきました。
とくに兵庫県には瀬戸内海に面した地域に多くのため池があり、その数は日本一となっています。日本全国のため池は、全部で約17万箇所あるそうですが、兵庫県はそのうち約15%にあたる2万4千箇所のため池があるそうです。多いですね。
琵琶湖の水が支える京阪神大都市圏
京阪神大都市圏と琵琶湖・淀川の水
京阪神大都市圏(けいはんしんだいとしけん)とは、東京大都市圏についで人口が集中している地域で、京都・大阪・神戸を中心に広がる大都市圏です。
その中でも大阪市を中心にして鉄道や道路が周辺にのび、沿線に市街地が広がっています。
大阪市の中心部では人口の増加にともなって住宅地が足りなくなったので、周辺の山をけずり、千里(せんり)・泉北(せんぼく)・須磨(すま)などのニュータウンの建設が進められました。
さらに、職住近接(しょくじゅうきんせつ)を目的とした西神(せいしん)・北摂三田(ほくせつさんだ)などのニュータウンもつくられました。
平坦な土地が少ない神戸市は、山からけずりとられた土を海の埋め立てに利用し、市街地を広げる工夫を続けています。
京阪神大都市圏では、琵琶湖から流れる淀川と、淀川に流れ込む川の水が、浄水場で安全な水道水となって流域に暮らす約1450万の人々に利用されています。
そのため、琵琶湖・淀川水系の環境を保全することは、近畿地方全体の重要な課題となっています。また、水道用水としてだけでなく、水運や水力発電などにも明治時代ころから活用されてきました。
琵琶湖の水の水質改善
琵琶湖では、1970年代からの人口や工場の増加によって、生活排水や工場廃水が流入し、赤潮(あかしお)が発生するなど、水質が低下する環境問題が起こりました。
赤潮とは、海や湖でプランクトンが大量発生し、水が赤色などに変色する現象です。
生活排水に含まれる りん や窒素などの栄養分が、発生原因の一つと言われています。
そのため、琵琶湖周辺の住民は、水質悪化の原因となる「りん」をふくむ合成洗剤の使用中止をよびかける運動を行い、滋賀県も生活排水への対策として県内の下水道を整備したり、工場廃水を制限したりしてきました。
このような取り組みの成果によって、琵琶湖では水質悪化の進行がおさえられていますが、水質の完全な改善にはいたっておりません。
そのため、琵琶湖に流れ込む川の清掃や水質検査をしたり、湖に近い水田では使う農薬を減らしたりするなど、水質を改善するために効果があると考えられるヨシの苗を植えるなどの活動が琵琶湖周辺を中心に広がってきていて一定の成果を生んでいます。
ちなみにヨシとは水辺に生育するイネ科の植物で、水中の窒素やリンを養分とすることで水質の悪化を防ぎ、さらに茎につく微生物によって水の汚れを分解する働きがあると言われています。
商業が盛んな大阪
大阪は、17世紀、江戸時代には日本国中の米や薬種、特産品が集められて売買されるなど、日本の商業の中心地として発展し、全国の経済や物流を取り仕切る場所として重要な役割を果たし「天下の台所」とよばれてきました。
江戸時代以前も淀川の下流には、いくつもの川や運河が張りめぐらされており、古くから琵琶湖や淀川、瀬戸内海を渡って船が行き来していました。
江戸時代以降、運河沿いには卸売業の問屋が数多く集まり、現在も調理器具や布・生地などを専門的に扱う問屋街が形成されました。
また大阪は「くいだおれの街(まち)」としても有名です。
食い倒れとは、飲食に対してぜいたくに金を使い、財産をなくすという意味で、昔から大阪の人たちには美食家が多く、おいしいものを追求してきたからと言われています。
近畿地方の経済や文化の中心である大阪には、周辺の府県からも多くの人々が集まります。
中心部では再開発が行われており、デパートなどの商業施設ビルや高層マンションの建設が進んでいます。
2019年時点でも日本一高いビルは、2014年に建設された「あべのハルカス」で地上300m、60階建てとなっています。(東京でも現在更に高いビルを建設計画中のようです)
臨海部の埋め立てと環境に配慮した工業
阪神工業地帯と環境問題への取り組み
阪神工業地帯は、大阪湾の臨海部とその周辺に位置し、第二次世界大戦以降、日本の工業を支えてきました。
しかし1970年代頃になると、工場が集まる大阪では工業用地や工業用水が不足し、工場の排煙による大気汚染や地下水のくみ上げすぎによる地盤沈下などの公害が発生しました。
そこで、大阪湾では埋め立てが行われ、港湾の整備や埋立地への工場の移転が進められました。
工場で利用される原料や製品を船で輸送するのに便利だったことから、臨海部である大阪市から堺(さかい)市、高石(たかいし)市にかけての埋立地がつくられ、その上には製鉄所や化学工場が並んで建てられました。
その後、化学や鉄鋼などの工業が、アジアをはじめとする外国との競争でのびなやみ、残念ながら工場の閉鎖や他地域への移転が進んだことで、阪神工業地帯の工業の規模は縮小してしまいました。
2000年以降は、臨海部にあった工場あと地や、内陸部の広い土地に、新しく太陽光発電のパネルや蓄電池(ちくでんち)の生産工場がつくられるようになりました。
とくに大型の蓄電池の生産には高度な技術が必要で、住宅向けや電気自動車の需要が高まっています。
新しい工場では、環境に配慮した工夫がされており、使用する水をリサイクルしたり、使用する電力を太陽光で発電したりするなどの環境対策が行われています。
内陸部に集まる中小企業の工場
臨海部とは異なり、内陸部にある東大阪市や八尾(やお)市などは、比較的小規模な中小企業の工場が数多く集まっています。
これらの工場では、自転車や歯ブラシ、ボタンといった生活にかかわりの深いいろいろなものがつくられています。
なかには、明石海峡大橋(あかしかいきょうおおはし)や東京スカイツリーといった建造物や新幹線の車両に使われるネジなど、精密な部品をつくる工場もあります。
これらの部品を入手しやすい門真(かどま)市や池田市などの高速道路沿いには、交通の便が良いこともあり、電気機械や輸送機械などの大きな工場が集まっています。
中小企業の工場の多くは住宅地にあることから、地域住民との間で工場から出る騒音や振動といった生活環境をめぐる問題が生じているようです。
そのため、工場と住民が共存できるまちづくりとして、地域や時間帯によって騒音や振動を規制するなどの取り組みがおこなわれています。
古都、奈良・京都と歴史的景観の保全
奈良・京都とその街並み
奈良と京都は、8世紀以降、平城京や平安京などの都(みやこ)がおかれ、長い間、日本の政治や文化の中心地であったので「古都」とよばれています。
当時の伝統は今も引きつがれており、歴史的な寺院・神社や祇園祭(ぎおんまつり)をはじめとする祭礼などの文化財(有形文化財と無形文化財の両方あります)、都のあった当時の影響が残る碁盤(ごばん)の目のような街路、昔の民家の姿を残した町なみなどがみられます。
奈良や京都には、国宝をふくむ重要文化財が多く、東大寺(とうだいじ)や清水寺(きよみずでら)のように世界遺産に登録されているものもあります。
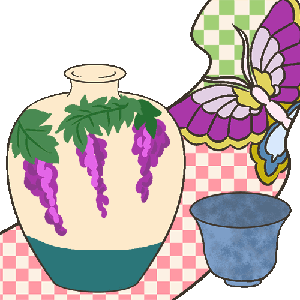
このほかにも、京都では、京焼(きょうやき)・清水焼(きよみずやき)、西陣織(にしじんおり)などの伝統的工芸品が地場産業として発達しています。
また、賀茂(かも)なすや九条(くじょう)ねぎなどは京野菜(きょうやさい)としてブランド化され、高級日本料理店などで重宝されています。
歴史的景観の保全に向けて
奈良と京都は、文化財や古都の景観、伝統的工芸品、伝統料理などが観光資源として生かされ、世界中の観光客の人気スポットとなっています。
しかし、せまい土地に多くの人が住んでいることから、歴史的な建物の近くに違和感を覚えるような現代的なビルが建てられるなど、歴史的景観は失われつつあります。こうしたことも環境問題の一つとしてとらえ、そこに暮らす住民の生活の利便性を守りながら、歴史と伝統をどのように後世に伝えていくかを考えることが重要になっています。
京都と奈良では、歴史と伝統の保全問題を解決するためのさまざまな取り組みが行われています。
例えば、奈良市では、町家(まちや)とよばれる伝統的な住居を保存するために、建物の内部を、飲食店や宿泊施設、伝統産業の体験施設などに改装して利用する取り組みが行われています。
とりわけ、町家を生かした旅館は、外国人観光客に人気があるようです。
また京都市では、建物の改修や電線の地中化など、景観を守る取り組みが行われています。
さらに、建物の高さやデザイン、屋外の広告物などに規制を設ける地域も増えてきました。これらの取り組みには、歴史と伝統を守ることを通して、古い町なみの魅力を残していきたいという想いがこめられています
環境に配慮した林業・漁業と保全活動
紀伊山地の林業の変化
紀伊山地は、古くから林業が行われてきた地域で「吉野すぎ」や「尾鷲(おわせ)ひのき」などの良質な樹木が育てられています。
森林の多くは木材として利用するために人が育てた人工林で、樹木の生長に合わせて伐採と植林がくり返し行われます。
これらの樹木は色が美しく香りも良いことから、建築材や家具などに加工され、高額な金額で取り引きされるものもあります。
しかし、山地の急斜面では機械での作業が難しく、安い外国材の輸入が増えたことなどから、林業を営む人は減少しています。さらに、高齢化も進んできているので、管理や整備が行き届かずにあれた森林も増加しています。
森林には、農業用水や生活用水を供給したり、洪水を防いだりするはたらきがあります。また、豊かな森林は川に豊富な栄養分を送って海の魚を育てたり、地球温暖化を防いだりする役割も担っています。
このような環境に対する効果を重視した「環境林」を保全する取り組みが広がっています。例えば、和歌山県や三重県の林業地域では、「企業の森づくり活動」として都市部の企業が森林経営のさまざまな仕事に参加する活動が行われています。
紀伊山地の観光と景観保全
紀伊山地には、歴史や宗教と関係が深いところがあります。
例えば、高野山(こうやさん)や熊野三山(くまのさんざん)は、古くから人々の信仰対象とされ、そこへ通じる熊野古道(くまのこどう)とともに、宗教的・文化的景観が高く評価されて、世界遺産に登録されました。
しかし、登録後の熊野古道では、観光客の増加にともなって山道が荒れたり、山道を整備したことで元の植生(しょくせい)が破壊されたりしたので、地元の住民や企業による保全活動が行われていることから、地元の住民の生活道路としての本来の使いみちを維持しながら、観光との両立も求められています。
水産資源保護への取り組み
近畿地方の南部や北部の沿岸部では、古くから漁業をさかんに行ってきました。
しかし、魚介類のとりすぎや養殖のしすぎによる水質汚濁が原因で、日本海沿岸ではズワイガニ、志摩(しま)半島の英虞湾(あごわん)では真珠をつくる貝の量が大きく減ったなど、各地で水産資源の減少が問題となりました。
ズワイガニの漁獲量が減った日本海側の地域では、とるカニの大きさや量、時期を制限し、水産資源を元通りに戻す努力を続けています。
このような環境に対する配慮を行う取り組みは、全国各地で始まっています。
★日本の諸地域★
④中部地方
中部地方の自然環境
日本アルプスを抱く中部地方
中部地方は本州の中央部に位置し、南北にも東西にも幅広く、九つの県によって構成されています。
その中央には日本アルプスとよばれる3,000m級の3つの山脈、飛騨(ひだ)山脈(北アルプス)・木曽(きそ)山脈(中央アルプス)・赤石(あかいし)山脈(南アルプス)が連なります。
アルプスの少女ハイジで有名な本場のアルプス山脈もヨーロッパ中央部の東西を横切る山脈で、イギリス人宣教師がそれに例えて日本アルプスと呼んで国内外に広めたからと言われています。
富士山や浅間山などの火山も周囲に点在しています。
日本アルプスの山々からは多くの河川(かせん)が流れ出し、日本海や太平洋へつながっています。
日本海側へは、信濃川(しなのがわ)、黒部川(くろべがわ)など、太平洋側へは富士川(ふじかわ)や天竜川(てんりゅうがわ)、木曽川(きそがわ)などが通じています。
これらの河川は、土砂を運び堆積(たいせき)させることにより、上流域では甲府盆地や松本盆地、長野盆地などの盆地を、下流域では濃尾(のうび)平野や越後(えちご)平野、富山(とやま)平野などの平野をつくっています。
濃尾平野は、昔は川の氾濫(はんらん)に苦しめられた地域でしたが、現在では治水が進化したこともあって、住宅地が増え、名古屋市をはじめとして、中部地方の中では、人口が一番集中した地域となっています。
特色ある三つの地域の気候
日本アルプスをはじめとする中央部の高い山々は、気候の地域差の原因となったり、交通網がまだ発達していなかった時代には人々の交通の大きな妨げとなってきました。
このため、中部地方では、北から北陸(日本海側の気候)、中央高地(内陸の気候)、東海(太平洋側の気候)という三つの地域で、それぞれ特徴のある生活文化や産業が発達してきました。
北陸は、冬に北西から湿気をふくんだ冷たい季節風がふく影響で、雪が非常に多いことが特徴となっています。
中央高地は、海からはなれた内陸で標高も高いので、夏と冬、昼と夜の気温の差が大きいことが特徴となっています。
中央高地の夏は、盆地は気温が上がりますが、高原はすずしくて過ごしやすいので、長野県にある軽井沢町のように、都会の人々の避暑地(ひしょち)となっているところもみられます。
東海は、夏に降水量が多く、冬は温暖な気候です。そのため、駿河湾(するがわん)沿いの日あたりの良い丘陵(きゅうりょう)などでは、みかんの栽培が盛んとなっています。
輸送機械工業が盛んな東海
自動車の生産が盛んな中京工業地帯
愛知県の内陸部には、「ジャスト・イン・タイム」という生産方式を世界に広めたTOYOTAのある豊田市を中心(注:ほかの企業の自動車工場ももちろんあります)に多くの自動車関連工場が集まっています。
この地域は、昔は綿花の生産地で、綿織物などの繊維工業が栄え、織物機械をつくる技術が発達しました。自動車の生産は、その技術を土台に戦前に始まり、戦後、大きく発展しました。
自動車工業は、約3万点もの部品を組み立てて1台の自動車をつくる、組み立て型の工業です。そのため自動車工場は、伊勢湾(いせわん)沿いの東海市などに立地する大規模な製鉄所、三重県四日市市の石油化学コンビナートなどとも強く結びついていて、これらの工場から供給される自動車用の薄くて強い鉄板やプラスチックなどの部品が自動車の生産を支えています。
完成した自動車は、高速道路と自動車運搬船を利用して、名古屋港などからさまざまな地域へ出荷されています。
このように、名古屋を中心とした工業地帯は、中京工業地帯とよばれ、伊勢湾沿いの臨海部と一体化して発達し、日本最大の工業地帯になっています。
また、新しい産業として注目されている航空宇宙産業の工場が岐阜県南部や愛知県西部に集まっています。
その他にも中京工業地帯の内陸部には、愛知県瀬戸市や岐阜県多治見(たじみ)市などで、陶磁器の生産技術を応用して、ファインセラミックスという新素材も生産しています。
輸送機械や楽器の生産が盛んな東海工業地域
静岡県西部の浜松市周辺は、中京工業地帯と同じように繊維工業がさかんだった歴史をもつことから、機械をつくる技術が早くから発達しました。
最初は、天竜川の上流から運ばれてくる豊富な木材を材料としたオルガンやピアノなどの楽器生産も発達し、国内きってのピアノ産地としての基礎が築かれました。
第二次世界大戦中は、織物機械や楽器の工場が軍用の飛行機部品工場などに変えられ、戦後はその技術を生かしてオートバイや自動車の生産がさかんになりました。具体的には、ホンダ・ヤマハ・ズズキなどの世界的企業の創業の地としても有名です。
近年は、医療機器やスマートフォンなどに利用される光学製品の世界的企業が浜松市に拠点を置いていることでも知られています。
静岡県の太平洋沿岸は、東海工業地域とよばれ、浜松市周辺の工場のほか、富士山ろくの豊かな水を利用して発達した富士市の製紙・パルプ工業など、多くの工場が集まっています。
交通網が発達した東海の農業
温暖な気候と交通の便の良さを活かした農業
愛知県南部に位置する渥美(あつみ)半島では、夜に多くの温室が照明で明るくなっている光景が見られるそうです。
温室の中では、抑制栽培(よくせいさいばい)という方法で菊が栽培されています。
抑制栽培とは、人工的に電灯の光を当てることで植物の生長をわざと遅らせる栽培方法です。菊は日照時間が短くなると開花する特性があるため、花の芽ができる前に夜も電灯を照らすことで開花を遅らせ(電照(でんしょう)栽培)、出荷時期を調整しているとのことです。
渥美半島は、園芸農業がさかんな地域へと変化しています。昔は大きな河川がなく、台地や砂丘が多い地域だったため、水不足になやまされ、作物の栽培が難しい地域でしたが、1968年に豊川用水という大規模な用水路が整備されたことにより、都市向けに野菜や花などを栽培できるようになりました。
東名高速道路という物流の大動脈が近くをはしり、名古屋や大阪、東京などの大都市への輸送の便が良いことも、渥美半島の園芸農業の発展をプッシュしました。
とくに、菊は仏壇用などに欠かせず一年中需要があるので、年間を通して電照栽培が行われ、その生産量は日本一となっています。
ほかに、メロンなども、ガラス温室やビニールハウスを利用した施設園芸農業で栽培されています。
暖流の黒潮(くろしお)が近くの海を流れている影響で、渥美半島は冬でも温暖です。
温室の暖房にかかる燃料費を節約することもできるので、施設園芸農業がさかんになりました。
東海は、太平洋に面し気候が温暖なうえに日照時間も長いため、野菜の露地(ろじ)栽培もさかんです。とくに愛知県のキャベツは全国有数の生産量があります。11月~3月に東京や大阪の市場で取り引きされるキャベツは愛知県産が中心となっています。
静岡県でも、温暖な気候を生かした施設園芸農業がさかんで、ガーベラやバラなどの切り花の生産では、全国的にも有数な産地となっています。
日本一の茶どころ、静岡
静岡県と言えば、おいしいお茶をイメージする人も多いのではないでしょうか?
静岡県の牧ノ原(まきのはら)や磐田原(いわたはら)などの台地では、明治時代から茶の栽培がさかんとなっています。
茶は、気候が温暖で霜(しも)がおりることが少なく、日あたりと水はけの良い場所(つまりは台地)が栽培に適しているからだそうです。
こうした特徴をもつ茶畑では、茶葉を霜の害から守るために、防霜(ぼうそう)ファンとよばれる地表面近くに風を送る設備が、畑のあちこちに見られます。
茶畑のそばには、デリケートで傷みやすい茶葉をすばやく乾燥するための製茶工場もつくられています。
工場で荒茶(あらちゃ)に加工された茶葉は、専門業者に買い取られ、きゅうすで入れる緑茶用やペットボトル飲料用などさらに加工され、国内だけでなく、アメリカ合衆国などの外国へも出荷されています。
内陸の中央高地の産業の移り変わり
高原を野菜産地に
長野県東部の高原にある野辺山原(のべやまはら)では、夏になると夜明け前からレタスの収穫が始まります。
収穫された新鮮なレタスは、すぐに高速道路を使って東京などの市場に届けられ、その日の夕方までには「朝どりレタス」として店頭に並べられます。
野辺山原は、標高1000mをこえるため、冷涼(れいりょう)な気候が主食の米づくりに向かなかったので、昔はそばなどの雑穀(ざっこく)や、はくさいなどの野菜をわずかに栽培する地域でした。
その後、食の洋風化の流れによってレタスなどのニーズが高まると、高原を開拓して土地を改良し、夏でも涼しい気候を利用した高原野菜の産地となりました。
今では、国内のほかの産地の野菜が少なくなる時期に出荷したり、夏場のレタス栽培が難しい台湾などに輸出したりして、高収益な農業を行っています。
養蚕(ようさん)から果樹栽培へ
甲府盆地や長野盆地は中央高地にあり、扇状地(せんじょうち)が広がっています。
扇状地は水田に適さないので、養蚕(ようさん)が盛んだった明治から昭和の初めにかけては、蚕(かいこ)のえさとなる桑(くわ)の畑として利用されていました。
しかし化学繊維の普及などによって製糸業自体が衰退すると、桑畑も少なくなっていきました。養蚕と製糸業の違いは、まゆを生産する農業のことを養蚕といい、そのまゆから生糸(きいと)をつくるのが製糸業です。

現在では、扇状地の水はけや日あたりの良さを生かして果樹栽培がさかんです。
内陸の気候は、昼と夜の気温差が大きくおいしい果物をつくるのに適していて、山梨県や長野県は全国有数のぶどうや桃などの産地へと成長しました。
甲府盆地では、明治時代からぶどうを原料としたワインの生産が行われ、果物狩りができる観光農園のほか、ワインを醸造(じょうぞう)するワイナリー見学も観光客に人気スポットとなっています。
製糸業から電気機械工業へ
長野県の諏訪(すわ)盆地においては、昭和の初期ごろから製糸業が衰え始めると、織物機械の修理をしていた技術を応用して機械工業が始められました。
第二次世界大戦中には、空襲(くうしゅう)を避けるために、製糸工場のあと地に東京などから多くの機械工場が移ってきました。
第二次世界大戦後は、機械工業の技術と部品の洗浄に適した水資源などを生かして、時計などをつくる精密機械工業が発達しました。
1980年代以降になると、高速道路の整備が進んで交通の便が良くなったため、富士山のすそ野や甲府から松本・長野にかけての高速道路沿いの地域にも、電子部品やプリンタ、産業用ロボットなどの電気機械工業の工場が進出し、製造や出荷がさかんに行われています。
また、工場内でのきのこの大量生産や、寒天(かんてん)の製造など、中央高地の気候を生かして発達した食品工場としても注目されています。
雪との関りが深い北陸の産業
豊富な雪解け水とコメ作り
北陸といえば、雪が多いイメージですよね。
北陸における農業の特色は、稲作の割合が高く単作で米をつくっていることです。
ちなみに単作とは1年間に1種類の農作物だけを栽培する方法をいい、一毛作とも呼ばれます。
春になると、北陸では大量の雪がとけて、水を豊富に得ることができます。
昔は梅雨や台風の時期に起きる洪水に悩まされていたようですが、現在はダムや堤防、放水路などの整備が進み、豊かな水を有効に利用できるようになっています。
さらに耕地整理や農作業の機械化も後押しして、今では全国有数の米の生産地になりました。
北陸で多くつくられている「コシヒカリ」は、北陸で品種改良によって開発された稲です。
開発当初は、味は良いが病気に弱く、栽培しにくい稲だったようでしたが、肥料の与え方などを工夫した結果、多くの農家で栽培できるようになりました。
今では新潟県の魚沼産コシヒカリのように、銘柄米(めいがらまい=ブランド米)として高い価格で販売されているものもあります。
また北陸では、米を原料にして米菓(べいか)やもち、本酒などをつくる食品工業も盛んで、米を精米するときに出る「ぬか」も近隣のきのこ農家が栽培に利用するなど、北陸のさまざまな産業を米が支える存在となっています。
雪国で発達した地場(じば)産業
北陸では、冬になると雪におおわれるため、冬の間の農作業が難しく、家の中で作業できる、織物・漆器(しっき)・金物(かなもの)などの工芸品をつくる農家の副業が、古くから発達しました。
つくられた工芸品は、地場産業(じばさんぎょう)として、その後の地域の工業の土台となりました。
ちなみに地場産業とは、古くから受け継がれてきた技術や、地元でとれる原材料などを生かし、地域と密接に結びついて発達してきた産業のことをいいます。
地場産業のなかでも、織物や漆器(しっき)、陶磁器(とうじき)など、現代の生活でも使われる伝統的工芸品をつくる産業は伝統産業と呼ばれます。
地場産業の具体例として、新潟県燕(つばめ)市は、江戸時代に農家の副業としてくぎづくりが始まり、金属加工の技術が発達しました。
現在では、ナイフやスプーンなどの洋食器をはじめ、台所用品や自動車部品など、さまざまな金属製品を生産する産地となっています。
また、福井県鯖江(さばえ)市では、明治時代に始まった眼鏡フレームづくりが、新しい素材や繊細な加工技術の開発により、国内生産の9割を占めるまでに成長しています。
ということは、日本製のメガネフレームはほぼ鯖江市で作られているってことになりますね。
北陸の豊富な雪どけ水は、水力発電にも利用されています。
黒部川(くろべがわ)などには多くの水力発電所が建設され、ここから供給される大量の電力が北陸地域の工業の発展を支えました。
富山県の工業は、はじめにアルミニウムの精錬とその加工が発達し、現在は輸入したアルミニウムをサッシなどの建具(たてぐ)に加工する工業へと発展を遂げています。
このように、北陸ではさまざまな特色ある地場産業が行われています。
★日本の諸地域★
⑤関東地方
関東地方の自然環境
日本で最も広い関東平野
タイトル通り、関東地方にある関東平野は日本で最も広い平野です。
北は越後(えちご)山脈、阿武隈(あぶくま)高地、西は関東山地などに囲まれています。
関東平野には、浅間山や富士山などの噴火による大量の火山灰が積もってできた赤土(関東ロームとも言います)におおわれた台地と、利根川や多摩川など多くの川沿いにできた低地が広がっています。
千葉県にある下総(しもうさ)台地などの台地は水が得にくく、畑や住宅地、ゴルフ場などに利用されています。
一方、台地に比べ低地は水が得やすいので水田に利用され、都市の中心部では高層ビルもみられます。
太平洋側に面する千葉県の九十九里浜などの海岸線は、なだらかな砂浜が続き、多くの海水浴客などでにぎわいます。しかし東京湾は自然のままの海岸線はほとんど残っておらず、海岸線の大部分が埋め立てられ、その埋立地は工業地などに利用されています。
また、最近では埋立地にタワーマンションなどの住宅用高層ビルが建てられています。
関東平野は、17世紀初めに江戸幕府が開かれてから本格的に開発が進み、人口が増えていきました。
そして現在、関東地方は約4000万の人々が暮らす、最も人口の多い地方になっています。 千葉県船橋市にあるジャニアスも、もちろん関東平野に存在しています。
内陸と海沿いで異なる気候
北関東の内陸地域は、夏と冬の気温差が大で、降水量も少ないのが特徴です。
とくに冬は、北西からふく季節風が越後山脈などにぶつかって雪を降らせたあと、乾いた風となって関東平野に吹き降りてくるため、晴天の日が続きます。
夏は、埼玉県熊谷(くまがや)市のように毎年高温になる町もみられ、山沿いでは雷雨が発生しやすくなります。
一方、南関東の海沿い地域は、黒潮(くろしお)が近海を流れるため冬でも温暖な気候がみられるのが特徴です。
千葉県の房総半島や神奈川県の三浦半島は、冬に観光農園で花摘みが楽しめることでも有名です。
東京都に属する伊豆諸島や小笠原諸島は、一年中温暖で海のレジャーがさかんです。
東京の中心部では、ビルや商業施設が集中しており、気温が周辺地域よりも高くなるヒートアイランド現象がみられます。
また近年は、「ゲリラ豪雨」とよばれる、せまい地域にとつぜん短時間の大雨をもたらす局地的大雨が、関東地方のいたるところで起こっています。
多くの人が集まる首都・東京
日本の首都・東京
2020年オリンピック・パラリンピックの会場で、日本の首都である東京の中心部は、23の特別区からなります。
ここには、日本の政治の中心として、国会議事堂・最高裁判所のほか、多くの中央官庁が集まっています。
また、日本経済の中心にもなっており、日本銀行をはじめ大きな銀行の本店や、東京証券取引所、大企業の本社などが集中しています。
さらに、大学や専門学校などの教育機関も多く立地しています。
そのため、東京やその周辺には働く人や通学する人が大勢暮らしています。
東京の中心部で働く人の多くは、その周辺地域から通勤しているため、千代田区・港区などのオフィス街では、夜間人口よりも昼間人口がはるかに多くなります。
世界の都市・TOKYO
Tokyoは世界都市と呼ばれています。

Tokyoには、日本国内だけではなく世界各地から人や物、資金、情報などが集まったり、Tokyoから逆に世界へ向けて発信もされています。
各国の大使館や国際機関、外資系企業なども集中していて、外交官、外国人ビジネスパーソンやその家族、留学生などもたくさん住んでいます。
世界各地を結んで金融や貿易などの国際的な活動が休みなく行われ、夜間でも多くの人が働いています。このような都市を世界都市といいます。
交通網の中心となる東京
東京駅のホームっていっぱいありますよね。新幹線はもちろん、山手線・京浜東北線・中央線・東海道線や地下鉄など多くの鉄道列車が、東京駅につながっています。
そのおかげで通勤・通学には、鉄道網を利用する人がほとんどです。
充実した交通網は、東京だけでなくその周辺地域にさらに人を集めることにもつながっています。
また、東京駅以外にも副都心とよばれるターミナル駅として新宿・渋谷・池袋、などがあり、都心と郊外とを結ぶ交通の拠点として多くの人が利用しています。
ターミナル駅をはじめ東京の中心部は、地下鉄が網の目のように張りめぐらされ、まわりには高層ビルが建ち並んでいます。
これは、地価が高く広さも限られている土地を有効に活用するために工夫された結果となっています。
東京は、全国を結ぶ交通網の中心でもあります。
鉄道以外にも高速道路が、東京を起点として放射状にのび、国内各地とつながっています。
また、航空路線も東京国際空港(羽田空港)を中心にして、日本各地の空港と結ばれています。東京国際空港は、成田国際空港とともに、空の玄関口として世界各地の空港とも結ばれており、日本から海外へ向かう人や日本を訪問する多くの観光客に利用されています。
これらの空港では貨物の輸送も行われ、とくに成田国際空港の貿易額は、輸出や輸入を行う日本の港や空港の中でも最大貿易額となっています。
拡大する東京大都市圏
東京大都市圏の拡大
東京は働く場所や学校が多く、1950年代後半から1970年代前半にかけての高度経済成長ともに、人口が増え続けました。
その結果、東京への人口集中が進み、住宅地が不足して地価が高くなっていくと、住宅地の開発は都心を中心に鉄道路線に沿って放射状に広がり、東京の周辺部にも人が増えていきました。
神奈川県・埼玉県・千葉県・茨城県など東京の周辺の県にかけて広がる地域は、日本の約4分の1の人口が集中する日本最大の都市圏となっていて、東京大都市圏(とうきょうだいとしけん)と呼ばれています。
東京大都市圏の中の大都市・横浜
東京大都市圏の中には、五つの政令指定都市があります。横浜市・川崎市・さいたま市・千葉市・相模原市です。
なかでも横浜市は東京についで人口が全国第2位の大都市で370万を超える人々が暮らしています。
江戸時代の終わりに開かれた港を中心に港町が形成されて以来、国際色豊かな都市として発展してきました。
現在も洋館やれんが造りの建物(赤レンガ倉庫などをメージしてください)などの歴史的な景観が残されている一方で、再開発が行われています。
「みなとみらい21」地区は、商業施設や国際会議場などが集中してつくられ、多くの人々が訪問しています。
また横浜市は、市内で暮らす人はもちろん、東京などへ通勤・通学する人の居住地にもなっています。
横浜市の都市化はもともと臨海部から進行しましたが、東京の人口が増えるにつれ、内陸の丘陵(きゅうりょう)地でも住宅地の開発がさかんになりました。
1970年代に開発が始まった港北ニュータウンのように、横浜市の中心部や東京への交通の利便性が高く、生活環境が整った住宅地区では、現在も人口が増加し続けています。
しかなしながら、東京大都市圏のニュータウンの中には、居住者の高齢化や少子化といった現象が進行しているところもあります。
都市機能の分散
東京大都市圏では、さまざまな都市問題が発生してきました。
例えば、人口が集中することで過密(かみつ)となり、通勤時間帯のラッシュやごみの増加などがあります。
なかでも東京の中心部の道路は交通量が多く、日常的に交通渋滞が発生しています。
これに対し、首都高速中央環状線・東京外環自動車道・圏央道といった道路が整備されてきており、都心部の渋滞緩和がはかられています。
これらの都市問題の原因の多くは、せまい中心部にさまざまな機能や企業のオフィスなどが集中し、その周辺地域にも人口が集中しすぎたことにあります。
その対策の一つとして、1970年代に筑波研究学園都市の建設が進められ、東京から大学や研究機関が計画的に移転されました。
また、1990年代以降は、東京湾岸の埋立地や鉄道建設のあと地で再開発が行われてきました。
千葉市から習志野市にかけての「幕張新都心」やさいたま市の「さいたま新都心」などは、企業のオフィスや商業施設などが集まり、多くの人に利用されています。
このように計画的に都市問題の解決のため、都市機能の分散が計画的に行われています。
人口の集中がもたらした産業
情報と娯楽を扱う産業の発展
首都機能を持つ東京は、世界中から多くの人や、政治・経済に関するニュースからファッションをはじめとするさまざまな流行まで、ものすごく多くの情報が集まってきます。
それらの情報を大量かつ速やかに収集・処理するために、東京には多数のテレビ局や新聞社・出版社などの企業があります。
さらに、インターネットに関連した情報通信技術(ICT)関連産業や、ゲーム・映画など映像制作に関連した産業も発達しています。
これらの産業は、制作にさまざまな工程があり、技術と独創性をもった多くの人手が必要であるため、情報と人が集まる都市で発展しました。
また、東京ディズニーリゾートに行くのが楽しみという人も多いと思いますが、東京ディズニーリゾートに代表されるテーマパークや博物館、展示場もたくさんあります。
これらの施設は、日本国内だけでなく、海外からも多くの人を引きつけています。
こうした産業の分類をサービス業と言います。「サービス業の比率が高い」ことが、東京大都市圏の大きな特徴のひとつとなっています。
活発な消費活動を支える産業
東京大都市圏は、日本最大の消費地でもあります。
そのため、大型ショッピングセンター・アウトレットモール・デパートなど、多くの商業施設が立地しています。
商業に関わる人が非常に多くなっており、東京は全国における小売業(こうりぎょう)や卸売業(おろしうりぎょう)の中で、最も割合が高くなっています。
ジャニアスのある千葉県船橋市のお隣である市川市などの東京湾岸や、神奈川県相模原市のような高速道路の近くには、交通網の発達により、国内だけでなく世界各地から集まる物資を扱う物流センターが多く建設され、商業活動を支えています。
これらの施設には、宅急便などの運送業者や通信販売を行う企業の倉庫があり、商品が各地へ配送されています。
また交通網の発達は、北関東地方の栃木県・群馬県・茨城県における大型ショッピングセンターやアウトレットモールの出店を促進しました。
これらの店は、地元や周辺の都市からの買い物客でにぎわっています。しかし一方で、もともとあった地元の商店街への客足が減ってしまう新たな問題も見られるようになりました。
臨海部から内陸部へ移り行く工場
臨海部から発達した京浜工業地帯
京浜工業地帯は、東京都・神奈川県・埼玉県・千葉県にまたがる日本有数の工業地帯です。
なかでも、多くの人口をかかえる東京では、膨大な情報が集まり新聞社や出版社が多いので、印刷業がさかんです。
また、大消費地(だいしょうひち)である東京都やその周辺の県には、ビールやジュースなど、重くて輸送費のかさむ飲料工場や、日もちのしないパンや生菓子(なまがし)などの工場が立地し、食品関係の工業もさかんです。
東京湾岸の埋立地には、海外からの原材料の輸入や製品の輸出に便利なため、製鉄所や火力発電所などが立地しています。
とくに千葉県の臨海部は京葉工業地域ともいわれ、船で輸入した原油を原料とする製油や石油化学などに関連する工業が行われています。
1960年代頃の高度経済成長期以降、これらの地域の工場や会社で働くために、多くの若い人々が日本各地から東京大都市圏に移り住みました。
こうした動きも東京大都市圏で人口が増加する要因の一つとなりました。人口増加にともない市街地が拡大すると、工場を建てるための用地が不足して、神奈川県の藤沢市などの相模湾沿いの都市にも工場が立地していきました。
さらに広い土地を求めて工場は内陸部の八王子市や相模原市などにも進出しました。
その一方で、1990年代以降、これらの地域にあった古い工場の閉鎖や移転が増え、海外に生産拠点を移す工場も出てきました。
その工場跡地は、再開発によって企業の研究所や商業施設などに現在利用されています。
北関東への工場進出と流通の変化
工場の進出は、栃木県や群馬県、茨城県を中心とする北関東にも広がりました。
北関東は、もともと繊維(せんい)工業や航空機の生産が盛んな地域でした。
その技術や広い土地があったことに加え、地域住民の働き口を確保するために、県や市町村も工業団地をつくり工場を積極的に誘致(ゆうち)しました。
これらが工場進出の原動力となり、北関東工業地域が形成されました。
現在、関越(かんえつ)自動車道や東北自動車道、北関東自動車道などの高速道路の近くには、自動車関連や電気機械などの工場が多く集まっています。
これらの工場では、作業に多くの人手が必要とされるため、外国国籍の日系人も大勢働くようになりました。
群馬県や栃木県などでつくられた工業製品は、これまで東京港や横浜港から輸出されていましたが、2011年に北関東自動車道が全線開通すると、交通渋滞の激しい都心を経由せずに、日立港や常陸那珂(ひたちなか)港など最寄りの港から輸出できるようになりました。
大都市周辺の農業と山間部の過疎問題
食糧の大消費地を支える農業
新鮮な農産物を生産し都市住民に早く届けるために、東京周辺では、近郊農業が古くから発展してきました。
近郊農業は、昔は東京23区でも盛んでしたが、都市化によりこの地域の畑が市街地に変わると、次第に郊外へと移っていきました。
関東地方では、北海道のような広大な耕地は確保できません。しかし同じ畑で何度も収穫できる農産物などを、東京や横浜といった人口の多い大消費地の近くで生産することで、輸送にかかる時間やコストをおさえることができます。
このメリットを活かし、新鮮さが要求される果物・野菜・牛乳・鶏卵(けいらん)・食肉などが盛んに生産されています。
茨城県のはくさいや栃木県のいちごなどの生産量は特に全国的にも有数で、質の良いブランド品がつくられています。
ほかにも、栃木県や千葉県では、乳牛・豚などが数多く飼育されています。
消費地から離れた地域でも、関東地方では気候の特色を生かした農産物の生産が盛んです。
道路網が整備され、保冷トラックによる長距離輸送が可能だからです。
群馬県嬬恋村(つまごいむら)は、夏でも涼しい高原の気候を生かした高原キャベツの生産地としても有名です。
また冬でも温暖な千葉県の房総半島南部では、一年中花が栽培されています。
山間部の役割と地域の再生
関東地方の山間部を中心とした地域には、豊かな自然がみられるところがあります。
尾瀬(おぜ:福島県・新潟県・群馬県の3県にまたがる高地にある盆地状の高原)・日光(栃木県の北西部にあります)・奥多摩(おくたま:東京都の多摩地域北西部)などには、観光や登山、キャンプなどを楽しむために多くの人々が訪れます。
しかしながら多くの山間部では、昔の産業の中心であった農林業が衰退し、若い世代がそれぞれの県の中心都市や東京大都市圏などに移り住むようになったので、過疎(かそ)が問題となっています。
例えば、群馬県の南西部にある上野村(うえのむら)においては、長い間、若い世代を中心とした都市部への人口流出が止まらず、人口減少と少子・高齢化が急速に進みました。
このため上野村では、地域の自然を生かした特産品の開発や働き口の確保、村営住宅の整備など、若い世代が働き、生活できる村づくりに取り組んできました。
その結果、Uターンとよばれる都市部から生まれ故郷の上野村に戻って生活する人や、Iターンとよばれるほかの地域の出身者が上野村に移り住む定住者が増えました。
現在では、これらの定住者が村の人口の1割を占めるまでになっています。
関東地方の山間部では、この上野村のように、若い定住者を増やし東京大都市圏に近い利点を生かして、都市部の人々との交流を深めながら地域の活性化をはかるところが増えています。
★日本の諸地域★
⑥東北地方
東北地方の自然環境
南北に走る山脈
東北地方は本州北部にあり南北に長く広がっています。
太平洋側には北上(きたかみ)高地や阿武隈(あぶくま)高地があり、中央には奥羽(おうう)山脈がはしり、日本海側には出羽(でわ)山地や白神(しらかみ)山地が広がっています。
火山(八甲田山(はっこうださん)、鳥海山(ちょうかいざん)、磐梯山(ばんだいさん)など)も点在し、火山の噴火でできた湖として十和田湖(とわだこ)などがあります。
火山の周辺には観光資源となる温泉地も数多くあります。
南北につらなる山脈や山地の合間には、日本海と太平洋に向かって流れる河川によって、北上盆地や山形盆地、郡山(こおりやま)盆地などの盆地が形成され、盆地を中心として市街地が発展してきました。
これらの市街地を結ぶ交通網も南北に発達しています。
仙台平野(北上川(きたかみがわ)下流部)や、庄内(しょうない)平野(最上川(もがみがわ)下流部)などは、広くて大きな稲作地域となっています。
日本海側には砂浜が続く海岸線がみられます。
一方、太平洋岸の三陸(さんりく)海岸は入り江の多いリアス海岸が続き、波がおだやかな湾では養殖業をはじめとした漁業がさかんです。
宮城県の気仙沼港では、かつお水あげ量日本一となっています。
東西で異なる気候
東北地方は本州のほかの地域と比べて緯度が高く、北にいくほど冬の寒さが厳しくなります。
日本海側では、冬になると北西からの季節風によって冷たく湿った空気が流れこむため、雪がたくさん降ります。
これに対して太平洋側では、奥羽山脈をこえて乾いた風が吹きおろすため、雪は少なくなります。
東北地方は本州のほかの地域と比べて夏も涼しくなります。
とくに太平洋側では、やませとよばれる北東の冷たい風が吹くと、曇りの日が続き日照時間が不足して気温が低くなります。
やませが吹くと、太平洋側の稲作農家はたびたび冷害に悩まされてきました。
寒い夏に対する稲作と畑作の努力
コメ作りと寒い夏の克服
東北地方の平野や盆地では、昔から米の生産がさかんです。
詩人の宮沢賢治(岩手県出身)が、著書の「雨ニモマケズ」の中で「サムサノナツハ オロオロアルキ」とうたったように、東北地方の農家は夏の低い気温に苦しめられ、自然の厳しさと戦ってきたようです。
東北地方の太平洋側では、冷害が起こることがあります。
これは、やませ(=偏東風。北日本の太平洋側で春から夏に吹く冷たく湿った東よりの風のこと)の影響を強く受けると、稲が十分に育たず、収穫量が減ってしまう現象です。
とくに1993年には東北地方の多くの地域が冷害にみまわれ、地域的に大きな被害を受けただけでなく、日本中が米不足で苦しみました。
この年をきっかけにして、当時、宮城県で開発されていた「ひとめぼれ」など、冷害に強い品種の栽培が広がりました。
現在では、水田に水を深く張って保湿効果を高める昔からの対策法に加え、情報システムを利用して、気温と稲の生育状況から冷害の予防対策をとる農家も増えてきたようです。
減反政策と銘柄米の開発
秋田竿燈(かんとう)まつりでは、稲穂をかたどった竿燈があげられます。
このように東北地方の各地でみられる祭りには、厳しい自然環境の中で、豊作への願いや収穫への感謝を表すものが多く、古くから稲作が東北地方の人々の生活を支えてきたことが伝わります。
しかし、1970年代頃から、日本人の食生活の変化によって米の消費量が減り、米が余るようになりました。
このため、政府は米の生産量を減らす減反政策(げんたんせいさく)を始めました。
東北地方の米の産地では、大豆や麦などほかの作物への転作が進みましたが、消費者に喜ばれる米づくりをめざして、冷害に強いだけでなく、よりおいしい銘柄米(めいがらまい)の開発も進められました。
宮城県の「ひとめぼれ」や秋田県の「あきたこまち」、山形県の「はえぬき」「つや姫」など、各県を代表する銘柄米があり、全国的に販売されています。
冷涼な気候を活かした農業の工夫
東北地方では、そばや小麦の栽培が昔から広く行われてきました。そばや小麦が寒さに強いことが理由のようです。
岩手県のわんこそばや秋田県の稲庭(いなにわ)うどんのように、そばや小麦を使った食文化が根づいています。
一方、米の不作に備えて「さといも」も各地でつくられてきました。
山形県や宮城県を中心とした地域では、毎年秋に季節行事として芋煮会(いもにかい)という「さといも」を材料にした食事会が行われます。
太平洋側では、冷涼な気候を生かした畑作も盛んに行われています。
岩手県遠野(とおの)市では、涼しい気候の下で育ちやすく、ビールの原料となるホップを生産していて、日本一の生産量となっています。
また青森県の三本木原(さんぼんぎはら)は、根菜類(こんさいるい)の一大産地となっています。根菜類とは、にんにくやごぼう、長芋(ながいも)などの野菜で、夏の低温の影響を受けにくいのが特徴です。
果樹栽培の発展と生活に根付いた漁業
果樹栽培における農業の取り組みと変化
東北地方は、果樹栽培が盛んです。
盆地や平野のへりにある傾斜地や、山間から川が流れ出るところにある扇状地(せんじょうち)では、日あたりの良い場所を中心に果樹栽培が行われています。
山形県は、山形盆地を中心に、夏の昼夜の気温差を活かしたさくらんぼや西洋なしなどの果樹栽培を営む農家が多く、「果樹王国」と呼ばれていいます。
なかでもさくらんぼブランドの「佐藤錦(さとうにしき)」や「紅秀峰(べにしゅうほう)」は、全国各地に出荷されています。
さくらんぼを生産する農家には、1年を通して西洋なしやぶどう、いちごなど、さまざまな果物を並行して栽培しているところもあります。
また、出荷用果物の栽培だけでなく、観光農園として観光客を呼びこむ取り組みも行われるようになりました。観光農園とすることで、農家は収穫や出荷の手間も省け、観光客が多く訪れることは地域の活性化にもつながっています。
青森県では、国内生産量の半分以上を占めるぐらいりんごの栽培が盛んです。
夏の涼しい気候を生かして、津軽平野を中心に栽培されています。
最近では、国内販売はもとより、台湾など海外への輸出にも力を入れています。
福島県では桃が日本有数の生産量をあげています。
盛んな漁業と生活とのかかわり
三陸(さんりく)海岸の沖合いは、良好な漁場となっています。
寒流の親潮(おやしお)と暖流の黒潮(くろしお)が出会う潮目(しおめ=潮境 しおざかい)があり、かつおやさんま、いわしなどたくさんの魚が集まるからです。
また、リアス海岸が続く三陸海岸は、入り江が多く漁港に適しており、気仙沼(けせんぬま)港や八戸(はちのへ)港など水あげ量の多い漁港が点在しています。
また、湾の内側は養殖業もさかんです。波がおだやかで、三陸海岸では、牡蠣(カキ)やワカメ、陸奥湾(むつわん)では、ホタテなどが養殖されています。
漁港に近い地域では、生活と漁業が密接に結びついています。例として学校の運動会は、漁の合間にあたる5月に行われ、競技や応援には大漁旗(たいりょうばた)も使われます。
漁港の周辺には、豊かな水産物を食品に加工する工場が多く存在しています。
かまぼこや、フカヒレ、ワカメなどの加工品を生産しています。
東北地方太平洋沖地震(=東日本大震災)により、漁港や水産加工場は大きな被害を受けました。しかしながら、かつおの水あげ量や養殖によるワカメの生産量などは震災前に戻りつつあるところもあり、工場も再建が進んでいます。
工場ができると働き手が必要になるので、地域の復興にもつながっています。
伝統文化を活かした観光業の発展
地域の農業と深く結びついた祭り

東北地方の祭りや伝統行事の中には、地域の農業と結びついたものが多くあります。
秋田市の竿燈(かんとう)まつりは米の豊作への願いをこめた祭りで、岩手県滝沢(たきざわ)市のチャグチャグ馬(うまっ)コは農作業に欠かせない馬の労をねぎらうための祭りです。
このように、東北地方で生産が盛んな米などの作物への豊作の願いが込められた祭りや伝統行事が行われています。
また、祭りの時期が、夏から秋の稲の収穫期前にとくに集中していることも関係の深さを表しています。
交通網の整備と共に発展した観光業
東北地方の祭りで「ラッセラー・ラッセラー」の特徴的なかけ声で有名な青森ねぶた祭などの夏祭りは、全国各地から多くの観光客を集めています。
これは、1950年代に国鉄(今のJR)が各地の祭りをめぐる周遊券を売り出したのをきっかけに全国的に知られるようになりました。
もともと、各地の祭りは同じ日に重なるものもありましたが、観光客がいくつかの祭りを見てまわれるように日程調整がなされました。東北地方の夏祭りをめぐるツアーは、全国的な人気となっています。
東北地方では、はじめに東北自動車道や東北新幹線といった南北方向の交通網が整備され、その後、山形・八戸(はちのへ)・磐越(ばんえつ)・秋田自動車道や、山形新幹線・秋田新幹線といった東西方向の交通網が発達していきました。
結果的に、関東地方などからの交通の便が良くなり、観光や仕事で東北地方を訪れる人が増えていきました。
多彩な魅力をもつ東北最大の都市・仙台
仙台市は人口が100万をこえる東北地方で唯一の政令指定都市です。
江戸時代の城下町から発展した「杜(もり)の都」とよばれる緑が豊かな町で、東北地方の行政・経済などの中心的な役割を担(にな)い、政府の出先機関や企業の支社・支店、大型の商業施設が集まっています。
仙台市は、高速道路や新幹線の開通にともない、東北地方のほかの各都市との結びつきを強めてきました。
東北各地を短時間で結ぶ高速バスの便数も増え、仕事や買い物などの目的で山形や福島などの隣県から訪れる人も増加しています。
また、郊外には仙台空港があり国際線で海外ともつながっています。
仙台市では、仙台七夕まつりをはじめとする季節のイベントや、地元のプロ野球チーム(楽天さん)やプロサッカーチーム(ベガルタさん)の試合も数多く開催されており、県内外から多くの人々へ東北最大の都市としての多彩な魅力を提供しています。
発展する工業と生活の変化
現代生活に合わせて進化する伝統工芸品
東北地方には、さまざまな伝統的工芸品があります。
例えば、漆器(しっき)の津軽塗(つがるぬり)や会津塗(あいづぬり)、木工品の天童将棋駒(てんどうしょうぎこま)などです。
これらには、地元でとれる材料が使用されていて、江戸時代以前から職人が育成されたり、農家の副業としても発達してきました。
なかでも岩手県の南部鉄器(なんぶてっき)は、古くから地元に豊富にあった砂鉄(さてつ)や漆(うるし)、燃料にする木材といった資源を活用してつくられてきました。
しかし、安くて軽い調理器具が普及したことにより鉄器の生産量は減少しました。
その一方で、伝統的な質感を好む人や、現代風にデザインされた製品を求める人が増えてきており、これらの要望にこたえるために工夫をこらした鉄器は、国内だけでなく海外でも人気を得るようになりました。
色やデザインが工夫された岩手県の南部鉄器は、パリの茶の専門店でも販売され、人気を呼んでいます。
工業の発展による人々の生活の変化
高度経済成長期には、太平洋ベルトを中心に日本の工業化が進みました。
そのため、東北地方から仕事を求めて関東地方へ集団で就職する人びとや、積雪によって農業ができない冬の間だけ出かせぎに行く人が大勢いました。
しかし、1970年代から1980年代にかけて東北地方で高速道路や新幹線が整備されだしたころから、岩手県北上(きたかみ)市や福島県郡山(こおりやま)市などに電気機械のような労働力を多く必要とする工場を誘致(ゆうち)するために工業団地がつくられました。
その結果、地元で働く場所が増え、出かせぎに行く人が減り、農業と兼業(けんぎょう)する人も増加しました。
工業の発展と環境へ配慮したエネルギーの活用
現在では、東北地方はハイブリッドカーをはじめとする自動車生産の一大拠点に成長しつつあります。
1990年代頃から、東北地方へ大規模な自動車工場が進出し、それに関連する部品工場も増えていきました。岩手県から宮城県にかけての高速道路に沿った地域が中心です。
また、2011年の東北地方太平洋沖地震(=東日本大震災)による福島県の原子力発電所の事故をきっかけに、東北地方では原子力発電にかわる新しいエネルギー源として、再生可能エネルギー(風力・地熱(ちねつ)・太陽光・バイオマスなど)を活用する動きがさかんになっています。
例えば、福島県の猪苗代湖(いなわしろこ)の南側には、日本最大級の発電力をもつ風力発電所がありますし、広野町(ひろのまち)や楢葉町(ならはまち)などの沖合いでも風力発電所の建設が進んでいます。
ちなみにバイオマスとは、木材や牛のうんちなど、生物由来の資源の総称で、これらを発酵させてガス化し、そのエネルギーで発電を行います。
★日本の諸地域★
⑦北海道地方
北海道の自然環境
雄大な地形と景観
北海道は日本の北端に位置しています。
「北海道はでっかいどー」というだけあって、面積は、九州地方のなんと約2倍で、日本の総面積の約5分の1を占めています。
本州の青森県とは、津軽海峡(つがるかいきょう)をはさんで向きあい、樺太(からふと =サハリン)とは宗谷(そうや)海峡をへだてて向き合っています。
北海道の東部には、北方領土(ほっぽうりょうど)の島々があります。
北方領土とは、現在ロシア連邦が実効支配している択捉島・国後島・色丹島・歯舞群島の島々のことを言います。
また、北海道の中央には、標高2000mをこえる石狩(いしかり)山地がそびえ、その南には日高(ひだか)山脈が、北には北見(きたみ)山地が、それぞれ南北方向につらなっています。
北海道の気候や土地利用は、これらの山々を境に東と西で大きく異なります。
石狩川は、石狩山地を源流として日本海にそそぐ川です。
その石狩川の下流に広がる石狩平野は、農地の開発によって大規模な水田地帯となっています。
北海道には、火山もあり、有珠山(うすざん)や十勝岳(とかちだけ)などが有名です。洞爺湖(とうやこ)は、有珠山の火口と火山の噴火でできた湖で、周辺では温泉もわきだしており、温泉街があります。
火山はたびたび噴火して災害を引き起こしてきました。
しかし、火山がつくり出した美しい景色や、そのまわりに湧く温泉は、観光地としても活用されています。
また、東側に広がる十勝(とかち)平野や根釧(こんせん)台地は、火山灰が厚く積もっているうえ夏でも涼しいので、日本の中でも畑作や酪農に適しており、最も盛んな地域のひとつになっています。
亜寒帯に属する北海道
北海道の気候は、寒帯(冷帯)に属しています。
冬の寒さがとても厳しくて梅雨がないのが特色です。
日本海側の地域は、冬になると湿った北西の季節風が吹きつけるので、たくさんの雪が降ります。
太平洋側の地域は、雪はあまり降りませんが、夏でも気温が上がりにくいという特色があります。
夏は太平洋から吹きつける南東の季節風が、寒流である親潮(おやしお)によって冷やされ、濃霧(のうむ)を発生させることがその理由です。
また、オホーツク海の沿岸には、冬になると流氷(りゅうひょう)が多くみられます。
流氷の上には、アザラシなどが見られることもあり、船から流氷を間近で見ることのできる観光も人気となっています。
厳しい環境を克服した稲作の歴史
農地開発から始まった稲作への挑戦
現在の石狩(いしかり)平野は、全国有数の米の生産地になっています。
「ゆめぴりか」や「ななつぼし」などの品種がおもに栽培されています。
これらの北海道産米は、全国に出荷されており、飲食店などでの使用も広がっています。
これは、石狩平野の気候が、北海道の中では夏の気温が比較的高く、日照時間も長いという特色が理由となっています。
しかし、昔の石狩平野は、泥炭地(でいたんち)とよばれる農業に適さない湿地が広がっていました。
大規模な排水路を整備して水はけをよくしたり、農業に適した土をほかの場所から運び込む「客土(きゃくど)」を行ったりして、土地改良が進められ、今では全国有数の米の生産地へとなったのです。

北海道にはもともとアイヌの人々が住んでいました。
開拓使(かいたくし)が明治時代の初めにできたことで、石狩平野の土地改良が始まりました。
開拓使とは、北海道の開拓を本格的に進めるために明治政府がおいた役所のことです。
そのほか、北方(ほっぽう)の警備の役割をかねた屯田兵(とんでんへい)や、全国各地から北海道に移住する人々が大勢集められました。
本州からの移住者による血のにじむような努力の結果、厳しい自然環境を克服していきました。
同時に石炭を運ぶために、鉄道や道路も建設されたことも、開拓を後押ししました。
このようにして、未開拓の原野や森林が次々と切りひらかれ、稲作地帯に姿を変えていきました。
「寒さに強い米」から「美味しい米」へ
稲は、もともと暖かい地方が原産です。
そのため、夏でも涼しい北海道で稲を栽培することは、とても難しいことでした。
冷害の年には、夏に気温が上がらず、収穫がわずかなこともありました。
そこで、寒さに強く短い生育期間で実る稲をつくるために、長期間にわたって品種改良が積み重ねられてきました。
その結果、稲作が可能な範囲は北へと広がり、稲作農家の経営規模も大きくなって、大量の米を効率的に生産できるようになったのです。
それと同時に、味の良い米づくりの研究も行われました。先ほどでてきた「ゆめぴりか」や「ななつぼし」などが有名です。
残念ながら1970年代以降は、国の減反政策(げんたんせいさく)によって転作(てんさく)を行う農家が増えて、田んぼの面積は減り続けています。
石狩平野においても、小麦・そば・大豆など、多くの畑作物を栽培し、稲作にたよらない農家が増加してきました。
また、本州と比べて冷涼(れいりょう)な気候を生かし、野菜や花の栽培も盛んになっています。
大規模化してきた畑作・酪農・漁業
広大な土地を活かした畑作
十勝(とかち)平野や北見盆地(きたみぼんち)は小麦、てんさい、じゃがいも、豆類など、寒さに強い作物がおもに栽培される日本有数の畑作地帯となっています。
農家1戸あたりの耕地面積は広大で、農作業には大型農業機械を必要とします。農家の多くは、耕地をいくつかの区画に分けて、その年ごとに栽培する作物をかえる輪作(りんさく)がおこなわれています。
1980年代以降、アスパラガスやだいこん、ほうれんそうなど、新鮮さが重視される野菜の栽培も盛んになりました。交通網や保冷輸送技術の発達したことがその理由です。
また、農産物を原料として加工食品をつくる工場も増えました。
高品質の農産物を安定的に手に入れるために、生産農家と直接契約する食品メーカーや個人取引も増加しています。
涼しい気候のもと発展した酪農
北海道の東部と北部では、夏でも気温が上がらないうえに、濃霧(のうむ)の影響を受けます。そのため残念ながら、稲作や畑作に適していません。
逆に、寒い地域でも栽培できる牧草と広い土地を生かして酪農(らくのう)を営んできました。
特に東部の根室半島近くにある根釧(こんせん)台地とその周辺では、国の政策として、1950年代に酪農の村ができ、徐々に規模を拡大させていきました。
むかしは、北海道で生産される生乳(せいにゅう)の大部分が、牛乳と比べて日もちする粉乳(ふんにゅう)・バターなどの乳製品に加工されていました。
しかし、現在では、輸送網の発達や保存技術の高度化などのおかげで鮮度を保ったまま、全国に生乳を出荷可能になりました。
北海道で生産される生乳のうち牛乳として消費される割合は、4分の1程度となっています。
また、北海道の酪農家は、乳牛の飼育頭数を増やしたり、乳を自動でしぼる機械を導入したりして、高品質な生乳の大規模化・大量生産化に取り組んでいます。
豊かな漁場に恵まれた漁業
北海道の水産物の漁獲量は全国1位となっています。周辺の海が、豊かな漁場に恵まれているからと言われています。
以前は、遠くのロシア沿岸やアメリカ合衆国のアラスカ沿岸の海で、「さけ」や「すけとうだら」などをとる北洋漁業がさかんでしたが、各国が排他的経済水域(はいたてきけいざいすいいき)を設定したため、北洋漁業としての水あげ量は大きく減りました。
1970年代以降になると、近くの沿岸漁業や沖合漁業のほか、養殖業(ほたて貝やこんぶを育てる)、栽培漁業(さけを人工的に卵からかえして川へ放流する)が中心的に行われるようになりました。
大きな漁港の周辺には水産加工場が集中しています。水産加工品は、日本国内各地に送られるほか、世界各国(アメリカ合衆国や中国など)にも輸出されています。
歴史や北国の自然を活かした観光業
歴史ある街並みを活かした観光業
北海道には国内外から観光客を引きつける歴史的な町なみが数多く残っています。
日本で最初の開港地の一つで、外国文化の玄関口として栄えた函館(はこだて)市には、江戸時代末期から明治時代にかけて港の近くに建てられた倉庫や教会が今なお残り、人気の観光地となっています。
また小樽(おたる)市には、大型の船が出入りできる大きな港や倉庫群があり、明治時代から昭和時代初期にかけて北海道最大の商業都市としてさかえたおもかげが、今も色濃く残されています。
計画的につくられた都市・札幌
現在、北海道の人口の約3分の1が札幌市に集中しています。
実は、札幌は北海道開拓の中心地として計画的につくられた都市です。
中心部の街路は碁盤(ごばん)の目のように規則正しく区画され、歴史的な建物も残されています。とくに1960年代以降、北海道内で炭鉱の閉山があいついだので、職探しのため札幌に移住する人たちが増えました。
また、札幌は北海道の中でも観光客が多い都市で、北海道観光の拠点となっています。
とくに、2月におこなわれる大小の雪像・氷像が大通公園などに立ち並ぶ「さっぽろ雪まつり」には、寒さが厳しい時期にもかかわらず、国内外の多くの観光客からの人気を集めています。
豊かな自然を活かした観光業
行ったことある人も多いかもしれませんが、ニセコは、日本を代表する冬の観光リゾートとして有名です。北海道西部にあり、同じ地域の札幌や小樽よりやや南西にあり、室蘭の北西に位置しています。
カタカタなのは、もともと住んでいたアイヌ語に起源を持つ地名で、今も使われています。ちなみにニセコは、「切り立った崖の下を流れる川」を意味するアイヌ語「ニセイコアンペッ」に由来しています。
世界有数の豪雪(ごうせつ)地帯であるうえ、気温が低く空気が乾燥しているので、パウダースノーとよばれる良質な雪でスキー・スノーボードといったウインタースポーツを楽しむことができます。
冬になると、日本とは季節が逆になるオーストラリアや、温暖な東南アジアの国々などから、多くの外国人観光客が訪れます。現在では、北海道を訪れる観光客の約3分の1が外国人とも言われています。
そのほかにも、知床(しれとこ)半島や釧路湿原(くしろしつげん)なども豊かな自然の見られる観光地として有名です。
知床とは、アイヌ語でシリエトク「地の果て」を意味するようです。オホーツク海に細長く突き出た知床半島は、人を寄せ付けない地形と環境から「日本最後の秘境(ひきょう)」と呼ばれてきました。手つかずの大自然と希少な動植物の宝庫である知床には、クジラやシャチ、トド、アザラシなどの海洋生物や、エゾシカ、キタキツネ、ヒグマなどの野生動物も見られるだけでなく、世界的に絶滅危惧種(ぜつめつきぐしゅ)に指定されているシマフクロウ、オオワシ、オジロワシなどの希少な動物も生息しています。
2005年には、多くの野生動物が生息する貴重な生態系として、世界遺産に登録されました。
しかし、観光客の増加による影響で、ほかの地域と同様に自然環境の破壊が問題となっています。
知床では、野生動物や植物の観察などのために、森の奥深くまで観光客が入りこむようになった結果、生態系の乱れがめだつようになりました。そのため、知床五湖(ごこ)周辺では、植物を踏み荒らすことなく、安全に散策できるように高架木道(こうかもくどう)を設けるなど、生態系の保全と観光の両立をめざしたエコツーリズムの取り組みが進められています。
釧路湿原は、日本最大の湿原・湿地です。
その大きさは、全国の湿原の3割を占めとも言われており、東西約25km、南北約36kmに及びます。
広大な湿原には、さまざまな植物や動物が生息していて、それらが四季折々の美しい景観をみせてくれます。湿原の中には勝手には立ち入ることはできませんが、いくつかの施設では周囲に遊歩道がありますので、少しだけなら湿原の雰囲気を楽しむことができます。
釧路湿原のシンボルといえば、アイヌの人々からサルルンカムイ(湿原の神)として崇められ、国の天然記念物にもなっているタンチョウ(ツル)です。釧路湿原では1年中暮らしていて、美しい姿を見に国内外から観光客が訪れます。
中学2年生の【歴史】
近世の日本
中学2年の社会の歴史分野で、最初に学習するのは、「近世の日本」です。
近世というのは、現代に近い時代という意味を持つ時代区分の一つで、だいたい15世紀~19世紀を指すのが一般的です。
西洋では、15~16世紀ルネサンス以降の絶対主義・重商主義の展開した17~18世紀、市民革命の生成の頃までをいいます。
日本では、安土桃山時代・江戸時代を主に指し、その前の室町幕府の滅亡からその後の明治維新にいたる時代を指します。
明治時代~第二次世界大戦前までを近代といい区別されることが多いので、近世→近代→現代のような感じで覚えておいて下さい。
それでは、まずは、近世の時代へタイムトリップしていきましょう。日本を見ていく前に、特にヨーロッパでの近世の大きな動きをみていきたいと思います。
★近世の日本★
①ヨーロッパ人との出会いと全国統一
キリスト教世界とルネサンス
中世ヨーロッパ
]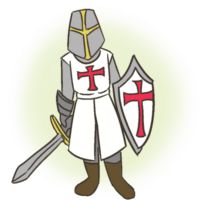
中世とは歴史時代の区分で、古代よりも後、近代又は近世よりも前の時代を指します。
4世紀に古代のローマ帝国は東西に分裂しました。
東ローマ帝国(ビザンツ帝国)は15世紀まで続きますが、西ローマ帝国は5世紀に滅ぼされ、西ヨーロッパでは小国が分裂していました。
全体を支配する国がなくなった一方で、キリスト教が各地に広まり、人々の考え方や生活に大きな影響をあたえていました。
キリスト教は、東ヨーロッパの正教会(せいきょうかい)と西ヨーロッパのカトリック教会に分かれていました。
特にカトリック教会は、ローマ教皇(きょうこう)が大きな権威を持っており、西ヨーロッパ諸国の王や貴族、都市は、カトリック教会と結びついて力を伸ばしました。
中世はキリスト教が栄えていたという特徴を理解しましょう。
その時代、東ヨーロッパにあたるビザンツ帝国のさらに東方には、イスラム教の国々が急速に勢力を拡大していました。
東はインド、西は北アフリカやイベリア半島に至る広い範囲の地域を支配していました。
キリストの聖地でもあるエルサレム(現在のイスラエルにある都市)がビザンツ帝国からうばわれると、キリスト教世界には危機感が高まりました。
そして、ローマ教皇の呼びかけに応じた西ヨーロッパ諸国の王や貴族は十字軍(じゅうじぐん)を組織して、エルサレムを目指しました。
残念ながら十字軍は、最終的にエルサレムの奪回(だっかい)に失敗してしまいます。
ローマ教皇の権威は弱まりましたが、当時としては進んでいたイスラム世界と接したことで、ヨーロッパには紙・火薬・占星術(せんせいじゅつ)、錬金術(れんきんじゅつ)などの新しい文化がもたらされたようです。
その後、ビザンツ帝国は、15世紀にオスマン帝国にほろぼされ、東ヨーロッパの南部はイスラム教の国々に支配されるようになりました。
近世にいたる前の中世は、十字架とキリスト、十字軍とキリスト教を関連付けて覚えましょう。
ちなみにエルサレムは、キリスト教だけでなくイスラム教やユダヤ教などの聖市となっていて、現代でもたびたび紛争もおきていますので、興味がある人は歴史的背景も調べてみて下さい。
ルネサンス
西ヨーロッパでは、古代ギリシャの文化はキリスト教との関係が弱かったため忘れられていましたが、イスラム教世界やビザンツ帝国で受け継がれており、東方との交流が盛んになるにつれて再び持ち込まれました。
西ヨーロッパの人々は、こうした古代の文化を手がかりに、人間についての新しい考え方を探り、また人間の活き活きとした姿を文学や美術で描き始めました。
こうした動きをルネサンス(文芸復興)と言います。
ルネサンスの動きは、14世紀から16世紀にかけてイタリアから西ヨーロッパ各地に広がり、多くの作品が作られました。
代表作は、レオナルド・ダ・ビンチの「モナ・リザ」や、ミケランジェロの「ダビデ」像などが有名です。
宗教改革
ルネサンスの頃、西ヨーロッパではキリスト教にも新しい動きが起こります。
16世紀に教皇が免罪符(めんざいふ)を売り出すと、これを批判してルターやカルバンが宗教改革を始めました。
かれらは、カトリック教会ではなく聖書に信仰のよりどころを置き、プロテスタントと呼ばれました。
国王の中には、教皇の権威から脱するために宗教改革を支援する者もいて、西ヨーロッパのキリスト教は、カトリックとプロテスタントに分かれました。
カトリック教会も、プロテスタントに対抗して改革を始めました。
その中心になったイエズス会は、日本史にも登場するフランシスコ・ザビエルなどの宣教師を派遣してアジアへの布教も行いました。
尚、プロテスタントとは、「抗議(こうぎ)する者」という意味で、抗議する対象が、カトリック教会の免罪符になります。
当時のカトリック教会は、人が罪を犯しても、懺悔(ざんげ)して教会に献金(けんきん)すれば許されるとされていたようです。おかしな話ですよね。
次回は、大航海時代へ突入です。ヨーロッパの人々がどのようにして世界進出していったかみていきましょう。
ヨーロッパと外の世界
大航海時代
15世紀後半に大航海時代が始まりました。
目的は大きく2つです。
一つはキリスト教を世界に広めること。もう一つは高価だったアジアの物産、特に香辛料を直接手に入れることでした。
大航海時代以前はイスラム商人が仲介していたため、香辛料は非常に高価でした。
こしょう、クローブ、ナツメグなどの香辛料は、調味料や薬として使われ当時のヨーロッパの人々にとってはとっても貴重だったのです。
大航海時代を本格化したルネサンスの時期のヨーロッパでは、テクノロジーの進歩も世界進出を下支えしました。
羅針盤(らしんばん)が実用化され、航海術も進歩し、世界地図も造られました。この発明により、ヨーロッパ人は、大西洋に乗り出すことができるようになったのです。
大航海時代の先がけとなった国は、ポルトガルとスペインです。2つの国の世界進出の特徴を見ていきましょう。
ポルトガルとスペイン
ポルトガルは、アフリカ大陸南端からインドやアジアにいたるルートを開拓しました。
1488年にアフリカ南端(なんたん)の喜望峰(きぼうほう)に到達し、1498年にはバスコ・ダ・ガマの船隊がインドに到達して、ヨーロッパとインドが初めて海路で直接つながりました。
16世紀には、それまでイスラム商人が支配していたインド洋や東南アジア海域で中継(なかつぎ)貿易を行うようになり、さらに中国や日本とも貿易を始めました。
一方スペインは、大西洋を横断するルートでアジアに向かおうとするコロンブスの計画を援助しました。
コロンブスは1492年に現在の西インド諸島のカリブ海の島に到達し、そこをインドだと考えました。
ところが、その近くには、それまでヨーロッパ人の知らなかったアメリカ大陸が広がり、北アメリカのアステカ文明や南アメリカのインカ帝国など独自の文明が栄えていました。
未開の地だったので、勘違いしちゃったんでしょうね。
アメリカの植民地化
スペインは、コロンブスなどの活躍によりアメリカ大陸にわたった後、マチュピチュ遺跡に代表されるインカ帝国などの先住民の文明が栄えていましたが、武力により制圧してしまいます。
銀の鉱山を開発したり、農園を開いてさとうきびを栽培するなど開発を進めていきます。
銀は、いったんヨーロッパへ運ばれた後、アジアの物産(香辛料など)との交換のために輸出されました。
アメリカ大陸からパスタとの相性抜群の「トマト」などがヨーロッパに持ち込まれたのもこの大航海時代と言われています。
トマトだけでなく、砂糖やジャガイモなどもアメリカ大陸からヨーロッパに運ばれ、ヨーロッパ人の食生活を豊かに変えていきました。
このようにして、アメリカ大陸は、ヨーロッパの植民地となっていき、スペイン人やイギリス人など、本国の人々が移り住み、先住民を支配していきます。
しかし、労働力の担い手となったアメリカの先住民が伝染病や厳しい労働で激減していきます。
労働力不足を補うため、今度はアフリカ大陸の人々を奴隷(どれい)として船でアメリカ大陸に連れてくるようになりました。
こうして始められた三地域間(アメリカ大陸・ヨーロッパ・アフリカ)で行われた交換取引を大西洋の三角貿易と呼んでいます。
それぞれどのようなものが取引されたかに注意してみていくとより理解が深まります。
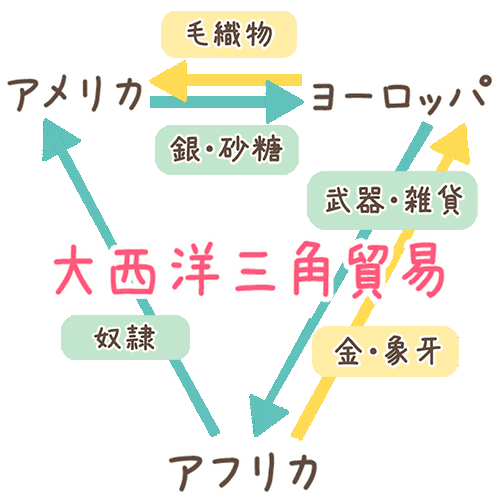
<参考>
大西洋の三角貿易で主に取引されたもの
アメリカ→ヨーロッパ・・・銀・砂糖
アメリカ→アフリカ・・・(該当なし)
ヨーロッパ→アメリカ・・・毛織物
ヨーロッパ→アフリカ・・・武器・雑貨
アフリカ→アメリカ・・・奴隷
アフリカ→ヨーロッパ・・・金・象牙
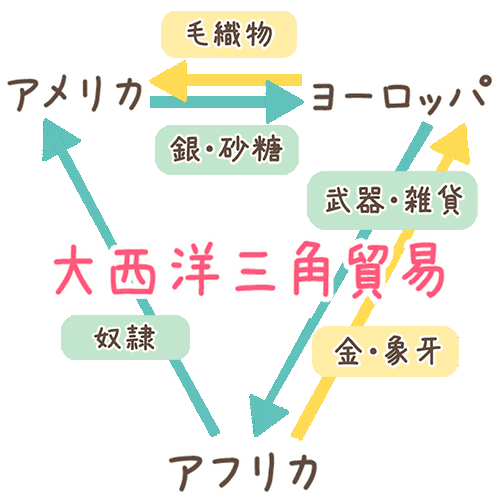
オランダの台頭
16世紀になるといよいよ世界一周も達成されるようになります。
世界一周を達成したと言われているのは、(ポルトガル人でしたが、)スペインの援助を受け艦隊を率いたマゼランさんです。
かれの名前を取った南米最南端のマゼラン海峡という地名もあるので、地図でも場所を確認してみてね。
スペインは、一時は「日のしずむことのない帝国」と呼ばれるくらい繁栄し、主にアメリカやアジアに植民地を広げていきます。
しかし、16世紀末になると、プロテスタント(宗教改革による新教徒のカルヴァン派)の多いオランダが、スペインがカトリックを強制したことに反発し、独立を宣言します。
その後、オランダは17世紀に東インド会社を設立し、ポルトガルにかわってバタビア(ジャカルタ)を本拠地にしてアジアへ進出します。
オランダは、日本とも貿易するなど、ヨーロッパの貿易・金融の中心として栄えました。
大航海時代は、スペイン・ポルトガルにはじまり、その後オランダが加わったことは覚えておきましょう。
さて次回は、大航海時代の頃の日本の様子を見ていきましょう。
ヨーロッパ人との出会い
鉄砲の伝来
ヨーロッパが大航海時代を迎えていたころ、日本は戦国時代と呼ばれる時代でした。
日本各地で勢力争いの戦いが行われ、民衆も数多く動員され戦っていました。中世の社会は、この戦国時代を経て大きく変化し、全国を統一する強い政権が誕生します。
大きな変化点として鉄砲が日本へ広まります。
きっかけは、ポルトガル人を乗せた中国人の倭寇(わこう)の船が、鹿児島県にある種子島に流れ着いたところから始まります。
このポルトガル人により日本に鉄砲が伝来されました。
鉄砲は戦国大名に注目され各地へ広まります。堺(さかい)<大阪府>や国友(くにとも)<滋賀県>などでは、刀鍛冶(かたなかじ)の職人によって鉄砲が造られるようになります。
鉄砲は、先から火薬とタマを入れ、火を着けた縄を使って火薬を爆発させたので「火縄銃(ひなわじゅう)」と呼ばれました。
こうした鉄砲による戦い方の変化や、対応する築城技術の向上もあって、全国統一の動きが加速していきます。
キリスト教の伝来と南蛮貿易
1549年になると、アジアで布教していたイエズス会(カトリック系の改革派)の宣教師フランシスコ・ザビエル(特徴ある髪型で皆さん大好きな方も多いようです?)さんが、日本へのキリスト教の布教に訪れます。
ザビエル自身は、キリスト教の布教のため鹿児島、山口、京都、豊後府内(ぶんごふない)<大分県>などを訪れ、2年余りで日本を去っています。ただし、その後も残った宣教師が布教に努めました。
その頃、マカオを根拠地として活動していたポルトガル商人たちも、日本を貿易の相手として注目します。平戸(ひらど)<長崎県>や長崎などで貿易が始められました。
ポルトガル人やスペイン人は南蛮人(なんばんじん)と呼ばれたので、この貿易を南蛮貿易(なんばんぼうえき)と呼んでいます。
尚、南蛮貿易の輸入品としては、生糸(きいと)や絹織物など中国産の品物が中心でしたが、毛織物・時計・ガラス製品など、ヨーロッパの品物もふくまれていました。
日本からの主な輸出品は、銀となっています。
そのほか大航海時代をへて作成された地球儀(ちきゅうぎ)なども南蛮貿易を通じて日本へもたらされました。
キリスト教の広まり
南蛮船と呼ばれた貿易船に乗って、イエズス会の宣教師も続々と日本にやってきました。
貿易の利益に着目した九州各地の戦国大名の中には、領内の港に南蛮船を呼びこむため、自らキリスト教徒(キリシタン)になる者も現れました。
こうした戦国大名をキリシタン大名と言いました。
1582(天正10)年、イエズス会は、布教の成果を示すため、豊後の大友宗麟(おおともそうりん)などのキリシタン大名が派遣した使節として、四人の少年をローマ教皇のもとへ連れていき、ヨーロッパ各地で熱烈な歓迎を受けました。
四人の少年の名前は、伊東(いとう)マンショ、千々石(ちぢわ)ミゲル、中浦(なかうら)ジュリアン、原マルチノです。(めったにテストにはでないので、無理して覚えなくても大丈夫とは思います。)
天正遣欧少年使節(てんしょうけんおうしょうねんしせつ)と呼ばれましたが、1590年に日本に帰国した際は、豊臣秀吉がバテレン追放令を出し、すでにキリスト教の布教は禁止されていたようです。
なお、宣教師は、長崎や豊後、京都などの各地に教会、学校、病院、孤児院(こじいん)などを建設し、布教や慈善(じぜん)事業を行いました。
そのため、民衆の間にもキリスト教の信仰が広まり、江戸幕府が開かれた直後の17世紀の初めには、信者が30万人を上回っていたと言われています。
織田信長・豊臣秀吉による統一事業
織田信長の統一事業
織田信長は、尾張(おわり)<愛知県>の小さな戦国大名でしたが、「天下布武(てんかふぶ)」をかかげ、武力による全国統一を目指した戦国武将です。
駿河(するが)<静岡県>の有力大名今川義元(いまがわよしもと)を桶狭間(おけはざま)の戦い<愛知県>で破って勢力を広げ、足利義昭(あしかがよしあき)を援助して京都に上りました。
信長は朝廷への働きかけにより、足利義昭を第15代将軍にすることで実権をにぎりました。
しかし、1573年には、敵対するようになった義昭を京都から追放し、室町幕府は滅亡しました。
織田信長は、鉄砲を有効に使って戦いました。
甲斐(かい)<山梨県>の大名武田勝頼(たけだかつより)を長篠(ながしの)の戦い<愛知県>で破り、翌年から、5層の天守を持つ安土城<滋賀県>を築きました。
城下町には楽市(らくいち)・楽座(らくざ)の政策によって商人を招き、座や各地の関所を廃止し、自由な商工業の発展を図りました。
一方で、従来から勢力をもっていた堺などの自治(じち)都市や比叡山延暦寺(ひえいざんえんりゃくじ)、一向一揆(いっこういっき)などの抵抗仏教勢力は武力により制圧しました。
豊臣秀吉の統一事業
2020年のNHK大河ドラマ「麒麟(きりん)がくる」の主役は、本能寺(ほんのうじ)の変をおこした明智光秀(あけちみつひで)です。
京都でおこった本能寺の変とは、織田信長が全国統一を目前にしながら、家臣の明智光秀が謀反(むほん)を起こし襲撃された事件です。
信長は寝込みを襲われ、包囲されたのを悟ると、寺に火を放ち自害したそうです。
1582年の出来事でした。
しかし、光秀は同じく信長の家臣であった羽柴秀吉(はしばひでよし<後の豊臣秀吉>)に山崎の戦いにて敗れてしまいます。
信長の後継者争いに勝利した秀吉は、 本拠地として壮大な大阪城を築きあげました。
秀吉は、朝廷から関白に任命され、豊臣の姓を与えられ全国に停戦を命じました。
1587年には、九州を統一しようとしていた島津氏を降伏させます。
さらに1590年に、関東の北条氏をほろぼすと、奥羽の大名も秀吉に従い、全国統一を完成させました。
信長や秀吉の活躍した時代を、安土桃山時代と呼んでいます。
豊臣秀吉は、重要な都市<大阪、京都、堺など>や重要な鉱山<新潟県の佐渡(さど)金山、兵庫県の生野(いくの)銀山、島根県の石見(いわみ)銀山など>は直接支配しました。
鉱山開発を進め、統一的な金貨として大判などを発行しました。
豊臣秀吉は、それ以外にも征服した土地など約200万石の領地をもち、さらに、ほかの大名の領地にある金山や銀山から税を徴収していました。
大阪城の天守は、秀吉の富の象徴として、うるしと金でかざられ、非常にきらびやかだったようです。
豊臣秀吉は、甥(おい)の豊臣秀次(ひでつぐ)に関白を譲った後は「太閤(たいこう)」と呼ばれました。
太閤は、摂政または関白の職を退いたあとに、子が摂政の職に就いた者や、摂関辞職後に内覧(ないらん)の宣旨(せんじ)を受けたものを指す称号で昔からありましたが、秀吉の死後も太閤といえば秀吉を指すことが多くなっています。
宣教師の追放
秀吉の主君であった信長は、仏教勢力には厳しい態度をとる一方、キリスト教の宣教師は優遇しました。
秀吉も当初はその路線を継承していましたが、九州の大名を従えた後、長崎がイエズス会に寄進されていることを知り、日本は「神国(しんこく)」であるとして、バテレン追放令を出し、宣教師の国外追放を命じました。
キリスト教の布教が、スペインやポルトガルの軍事力と結び付いていることが危険だと考えたようです。
しかし、実際には宣教師の一部は日本にとどまって布教活動を続けていたり、南蛮貿易自体は推奨されていたため、貿易が盛んだった長崎では、秀吉が直接支配していたにも関わらず、キリスト教徒は逆に増えていったようです。
兵農分離と朝鮮侵略
検地と刀狩(かたながり)
豊臣秀吉の国内統治の新政策として「検地」と「刀狩」も重要です。
検地は、太閤検地(たいこうけんち)ともよばれ、それまで地域によって異なっていた、“ものさし”や“ます”を統一し、全国の田畑の面積や土地の良し悪しを調べ、予想される収穫量を、全て米の体積である石高(こくだか)で表しました。
ちなみに米1石(こく)は、重さでは約150kgだそうです。
太閤検地以降、武士の領地は石高で示されるようになり、年貢(ねんぐ)を徴収する一方、石高に応じた軍役を果たすことが義務化されました。
また、武士はそれまで自分の領地にいましたが、大名の城下町に集められました。
さらに秀吉は、公家(くげ)や寺社などの荘園(しょうえん)領主や有力な農民がそれぞれもっていた土地の複雑な権利を認めず、検地帳に登録された農民だけに土地の所有権を認め、耕作をやめて土地を離れることを禁止しました。
さらに、武力一揆の予防策として、刀狩を命じて、農民や寺社から刀・やり・鉄砲などの武器を取り上げました。
これらの国内の政策は、兵農分離(へいのうぶんり)といい、武士と農民の身分の区別が明確になりました。
兵農分離といえば検地や刀狩、という感じで覚えておきましょう。
こうして、近世の社会のしくみが固まり、武士・百姓・町人などの身分に応じた職業によって生活するようになり、社会的にも安定していきました。
海外貿易と朝鮮侵略
秀吉は、海外との貿易に積極的でした。
京都や長崎、堺などの商人が東南アジアへ渡航することを奨励(しょうれい)し、倭寇(わこう)などの海賊を取りしまる命令を出して貿易船の安全を図りました。
朝鮮、高山国(たかさんこく、こうざんこく)<現在の台湾>、ルソン<現在のフィリピン>などには手紙を送り、服属を求めました。
秀吉は、明の征服を目指して、2回にわたる朝鮮侵略を行います。
1回目の文禄の役(ぶんろくのえき)は、1592年。2回目の慶長の役(けいちょうのえき)は、1597-98年です。
秀吉は、備前(びぜん=今の佐賀県)に名護屋城(なごやじょう)を築き、朝鮮に送った軍を指揮しました。
文禄の役では、諸大名に命じ、15万人の大軍を朝鮮に派遣します。
いったんは、首都漢城(かんじょう=ソウル)を占領して朝鮮北部まで軍を進めましたが、救援に来た明軍に押し戻されました。
ちょうどその頃、各地で朝鮮の民衆による義兵が抵抗運動を起こし、朝鮮南部では、李舜臣(りしゅんしん、イスンシン)の水軍が日本の水軍を打ち負かしました。
朝鮮軍は、李氏朝鮮時代の軍艦である亀甲船(きっこうせん)を利用し、亀の甲のような屋根を持ち、周囲の穴から大砲をうって攻撃してきたと言われています。
そのような状況で、明との間で講和交渉が始まり、明からの使節が来日しましたが、講和は成立されませんでした。
秀吉は2回目の慶長の役という朝鮮侵略を1597年に再び開始します。
日本の軍は苦戦し、翌1598年に秀吉が病死したのをきっかけに、全軍が引き上げました。
こうして7年におよぶ長い戦いの戦場になった朝鮮は荒廃し、日本に連行された者もいました。
日本も、武士や農民も重い負担に苦しみ、大名の間の対立をもたらして、朝鮮侵略が豊臣氏の没落する原因になりました。
尚、この時代に大名が朝鮮から連れてきた陶工は九州地方や中国地方で焼き物を作り、有田焼(ありたやき)<伊万里(いまり)焼>に代表される現在も続く陶器や磁器の名産品になっていたりします。
桃山文化
豪華で壮大な文化
信長と秀吉の時代を「安土桃山時代」といいますが、この時代の文化はどのような特色を持っていたのでしょうか?
全国を統一政権が出現することで、これまでの中世の社会の仕組みがこわされ、社会に活気がみなぎった時代だったようです。
商業や貿易が盛んになり、金・銀の産出も増加し、下剋上(げこくじょう)で成り上がった大名や大商人たちは、権力と富を背景に<豪華>な生活を送りました。
このころ栄えた文化を桃山文化(ももやまぶんか)と呼んでいます。
桃山文化の代表格は、なんといっても「お城」です。 安土城や大阪城の壮大なお城や、世界遺産に登録されている姫路城(ひめじじょう)などたくさんのお城が建てられました。
姫路城は、美しい白壁(しらかべ)から、白鷺(はくろ)城とも呼ばれ、5層の大天守と3つの小天守が結ばれています。天守は、支配者の権威を示すために、高くそびえるように建設されました。
城の室内は、寺院の部屋の様式を住居に取り入れた書院造(しょいんづくり)が採用され、柱や欄間(らんま)には豪華な彫刻がなされ、ふすまや屏風には画家によってはなやかな絵が描かれました。
有名な画家に、唐獅子図屏風(からじしずびょうぶ)という代表作を持つ狩野永徳(かのうえいとく)や弟子の狩野山楽(かのうさんらく)がいます。

茶の湯は、大名や大商人たちの交流の場になり大流行しました。
中国から日本に渡ってきた茶道具で高い評価のものは、大名の領地とも同じくらい価値あるものとされたぐらいもてはやされました。
豊臣秀吉(その前は、織田信長にも)に仕えた千利休(せんのりきゅう)は、禅宗(ぜんしゅう)の影響を受け、名誉や富よりも内面の精神性を重視し、質素なわび茶の作法を完成させました。
利休は、東南アジアで日用品として使われていた壺(つぼ)を茶壺(ちゃつぼ)として珍重するなど独創的な評価も行ったようです。
「茶聖」と呼ばれ権力をもつようになった千利休は、最後は主君の秀吉より自害を命じられ、これをスンナリ受け入れたようです。権力を持ち過ぎるようになったからではとも言われていますが、ハッキリとした原因は今も謎のままです
全国統一後の安定した桃山文化では、社会全体に現実の生活を楽しむ風潮が強まり、恋愛などをうたう小歌が流行します。
また、室町時代に琵琶(びわ)などにあわせて恋物語などを語った浄瑠璃(じょうるり)が、琉球(沖縄県)から伝わった三線(さんしん)を基に創られた三味線(しゃみせん)に合わせて語られるようになりました。
三線は中国の弦楽器が起源といわれ、高級なものにはヘビの皮が張られました。
三味線(しゃみせん)は、ねこや犬の皮が張られました。
17世紀初め、出雲(いずも)の阿国(おくに)という女性が始めた「かぶき踊り」も人気を集めました。出雲の阿国は、日本の伝統芸能の一つである「歌舞伎(かぶき)」の祖と言われる人物です。
ややこ踊りを基にしてかぶき踊りを創始したことで知られており、このかぶき踊りが様々な変遷を得て、現在の歌舞伎が創られたとされています。
衣服では、着物の下に着ていた小袖(こそで)を日常的に着るようになり、それまでの麻に変わって木綿が庶民の衣料として広がり出しました。
南蛮文化
パン、カステラ、カルタ、時計などは、南蛮(なんばん)貿易がさかんだった戦国時代から安土桃山時代にかけて日本にもたらされました。
布教活動をするキリスト教の宣教師によって、天文学や医学、航海術など、新しい学問や技術も日本に伝わりました。
絵画では、狩野派の画家によって長崎の南蛮船入港の様子が描かれたほか、ヨーロッパ風の絵画も描かれ、宗教画なども制作されました。
活版(かっぱん)印刷術も伝えられ、聖書など布教に必要な書物や、『平家物語』などの日本の書物が、ローマ字で印刷されました。
金のくさりやボタン、ひだのあるえりが付いたヨーロッパ風の衣服や装飾品を身に着けることが流行しました。
こうしたヨーロッパの文化から影響を受けて成立した芸術や流行の風俗(ふうぞく)を南蛮文化(なんばんぶんか)と呼んでいます。
★近世の日本★
②江戸幕府の成立と鎖国
江戸幕府の成立と支配の仕組み
江戸幕府の成立
1598年の豊臣秀吉の病死以降、関東を領地としていた徳川家康(とくがわいえやす)が勢力をのばしました。
1600年、秀吉の子、豊臣秀頼(とよとみひでより)の政権を守ろうとした石田三成(いしだみつなり)は、毛利輝元(もうりてるもと)などの大名に呼びかけ、家康に対して兵を挙げました。
家康も三成に反発する大名を味方に付け、全国の大名はそれぞれ三成と家康を中心とする西軍と東軍とに分かれて戦いました。
関ケ原の戦いのことで、別名「天下分け目の大合戦」とも言われています。
この戦いに勝利した家康は全国支配の実権をにぎりました。
1603年、家康は朝廷から征夷大将軍に任命され、江戸に幕府を開きました。
江戸幕府は、260年余りも続く戦乱のない平和な時代を作り上げました。
この時代を江戸時代といいます。
家康は、その後、1614年の「大阪冬の陣」、1615年の「大阪夏の陣」という二度にわたる合戦で豊臣氏をほろぼし、幕府の権力を固めました。
幕藩(ばくはん)体制の確立
徳川家康が開いた江戸幕府は、幕府直接の支配地として約400万石を占めました。
幕府直接の支配地は幕僚(ばくりょう)と呼ばれ、当時の全国の石高は約3,000万石でしたので、全国の約16.6%を支配していました。
旗本(はたもと)や御家人(ごけにん)といった家臣の領地も含めると約25%にもなったようです。
そして、京都、大阪、奈良、長崎などの重要都市や主要な鉱山を直接支配し、貨幣(かへい)を発行する権利を独占しました。
さらに、江戸を中心に道路を整備し、街道には宿場を、重要な場所には関所を置きました。主な関所は、東海道の箱根関所などです。
大名とは、もともと地方で勢力をふるう者のことを言い、武家社会においては、多くの所領や部下を所有する武士を意味する語でした。
室町時代には「守護大名」、戦国時代には「戦国大名」と、時代に合わせて変化していきます。
江戸時代の大名は、主に石高1万石以上の領地を幕府から与えられた武士を指すようになりました。
大名は、藩主(はんしゅ)、大名の領地やその支配の仕組みを藩(はん)といいます。
幕府と藩の力で全国の土地と民衆を支配する政治制度を幕藩体制と呼びます。
江戸時代の大名にも種類がありました。親藩(しんぱん)・譜代(ふだい)大名・外様(とざま)大名に分けられました。
親藩は将軍家の親戚です。「御三家」と呼ばれた尾張・紀伊・水戸で、たいへん重んじられました。
水戸黄門は、「御三家」の水戸藩主・徳川光圀(みつくに)の別称です。
譜代大名は関ケ原の戦い以前から徳川家に従っていた大名、外様大名は関ケ原の戦い以降に徳川家に従った大名です。
幕府は、藩を取りつぶしたり領地変えを行う力をもっていて、外様大名を江戸から遠い地域に移すなど、大名の配置も工夫したようです。
幕府の政治は、将軍が任命した老中が行い、若年寄(わかどしより)が補佐しました。
老中や若年寄のほかにも、三奉行(ぶぎょう)<寺社奉行・町奉行・勘定(かんじょう)奉行>をはじめとする多くの役職が置かれ、譜代大名や旗本を任命しました。
外様大名が幕府の役職に就くことはほとんどなかったようです。
余談ですが、水戸黄門の水戸は水戸藩の水戸ですが、なぜ黄門なのかというと、古代中国の唐の官位に「黄門侍郎」<皇帝の側近の役職>に由来するようです。
日本では大納言、中納言の役職名がありますが、昔の日本では唐風の官職を使う事があり、中納言の事を「黄門」と呼ぶ事があったようです。
そのため水戸の中納言の言い方として「水戸黄門」となったそうです。
大名や朝廷の統制
武家諸法度(ぶけしょはっと)は、将軍職を退いていた徳川家康が1615年に定めた法律です。
江戸幕府が諸大名の統制のために制定した基本法で、大名が幕府の許可なしに城を修理したり、大名どうしが幕府の許可なしに縁組(えんぐみ)をしたりすることを禁止しました。
以降、将軍の代が変わるごとに出されました。
また、第3代将軍の徳川家光(とくがわいえみつ)は、大名の参勤(江戸に来ること)は主従関係の確認という意味があり、これを参勤交代(さんきんこうたい)制度として定めました。
これ以後、大名は1年おきに領地と江戸とを往復することになり、その費用や江戸での生活のため多くの出費を強いられたようです。
参勤交代制度の真の目的は、するどい皆さんならわかると思いますが、外様大名を経済的に弱らせるためでした。
また幕府は、外様大名の弱体化だけでなく、京都所司代(きょうとしょしだい)を置いて朝廷を監視(かんし)し、禁中並公家諸法度(きんちゅうならびにくげしょはっと)という法律で天皇や公家の行動を制限し、政治上の力を持たせませんでした。
こうして、大名や朝廷の統制により江戸幕府は大きな力を持っていきました。
さまざまな身分と暮らし
武士と町人
豊臣秀吉時代の太閤検地(たいこうけんち)や刀狩(かたながり)などの兵農分離によって定まった身分は、江戸時代になってさらに強まりました。
武士・百姓・町人に大きく分かれ、江戸や大名の城下町には、武士と町人が集められました。
武士は、主君から領地や米で支給される俸禄(ほうろく)を代々あたえられ、軍役(ぐんやく)などの義務を果たしました。
武士は、名字・帯刀などの特権を持ち、支配身分として名誉や忠義を重んじる道徳意識を持つようになりました。これは「武士道(ぶしどう)」とも呼ばれます。
町人は、幕府や藩に営業税を納め、町ごとに名主(なぬし)などの町役人(ちょうやくにん)が選ばれて自治(じち)を行いました。
町の運営に参加できるのは、地主や家持(いえもち)に限定されていました。
多くの借家人は日雇いや行商などで暮らし、商家(しょうか)の奉公人(ほうこうにん)や職人の弟子は、幼いときから主人の家に住みこんで仕事を覚え、独立を目指しました。
丁稚奉公(でっちぼうこう)という言葉を聞いたことがあるかもしれませんが、丁稚(でっち)とは、商家に年季奉公する年少の者を指す言葉で、職人の場合は、徒弟、弟子、子弟のニュアンスです。
現代風では新入の平社員のような意味合いです。
村と百姓
江戸時代の百姓は、どのくらいの割合だったと思いますか?
江戸時代中期から江戸時代後期の総人口は、約3200万人で、百姓は、だいたい全人口の約85%(ざっくり2720万人)だったようです。
武士は約7%で、町人は約5%でしたので、ほとんどが百姓ということになるかと思います。
また、当時の百姓の生活は自給自足に近いものでした。さらに百姓の中でもランクがあり、土地を持つ本百姓(ほんびゃくしょう)と土地を持たず小作(こさく)を行う水のみ百姓との区別がありました。
有力な本百姓は村役人になり、庄屋(しょうや)<または名主(なぬし)>・組頭(くみがしら)・百姓代(ひゃくしょうだい)などとして村の自治を行い、年貢を徴収して幕府や藩に納めていました。
納めた年貢は主に米でした。
幕府や藩は、村の自治にたよって年貢を取り立て、財政をまかないました。
幕府は安定して年貢を取りたてようと土地の売買を禁止したり、米以外の作物の栽培を制限したりするなどの規制を設けました。
また、五人組の制度を作り、犯罪の防止や年貢の納入に連帯責任を負わせました。
百姓は、林野や用水路を共同で利用し、田植えなどもお互い助け合って行い、村八分(むらはちぶ)という罰を作って、村のしきたりや寄合(よりあい)で定められたおきてを破る者には、葬式など以外には協力しないなどの独自のルールをつくったりしました。
ちなみに村八分の「八分」とは、十分ある交際のうち、葬式と火事の際の消火活動の二分以外は付き合わないという意味からきたようで、のけ者にすることを「八分する」とも言ったことからのようです
厳しい身分による差別
百姓、町人以外にも、えた・ひにんといった身分の人々がいました。
「えた」と呼ばれた身分の人々は、農業を行って年貢を納めたほか、死んだ牛馬の解体や皮革業、雪駄(せった)作り、雑業などをして生活していたようです。
また、犯罪者を捕らえることや牢番(ろうばん)などの役人の下働きも、役目として務めました。
「ひにん」と呼ばれた身分の人々も、役人の下働きや芸能、雑業などで生活していたようです。
えた・ひにんの身分の人々は、他の身分の人々から厳しく差別され、村の運営や祭りにも参加できなかったようです。
さらに幕府や藩は、えた・ひにんの住む場所や職業を制限し、服装などの規制を行いました。
この制限や規制によって、えた・ひにんの身分の人々に対する差別意識が強まったそうです。
ちなみに「えた」と「ひにん」は、漢字で書くと穢多(えた)・非人(ひにん)と書きます。それぞれの意味を考えると、差別されていたことが伝わる漢字ですよね。
貿易の振興から鎖国へ
朱印船貿易と日本町
徳川家康は、渡航を許す朱印状(しゅいんじょう)を発行して貿易の安定と発展に努めました。
ルソン<フィリピン>・安南(あんなん)<ベトナム>、カンボジア、シャム<タイ>などに、朱印状を持った船(朱印船)の保護を依頼しました。
京都や堺(さかい)<大阪府>、長崎などの商人や西日本の大名の中には、この朱印状をもとに朱印船貿易(しゅいんせんぼうえき)を行う者が現れました。
そして、東南アジアへ多くの日本人が移住し、各地に日本町(にほんまち)<日本人町>ができるようになりました。
また家康は、オランダやイギリスなど新しく来航した国との貿易も許可しました。
長崎県の平戸には商館が設けられ、オランダ・イギリスとの貿易が開始されました。
江戸時代初期の輸入品は、主に中国産の生糸(きいと)や絹織物が中心で、東南アジア産の染料(せんりょう)や象牙などもあったようです。
逆に日本からは銀を中心に、刀や工芸品が輸出されました。
禁教と貿易統制の強化
家康は、貿易の利益を最優先に考え、当初はキリスト教の布教に関しては黙認していました。
そのためキリスト教に対する信仰が日本全国に広まっていくようになってしまいました。
こうした事態を踏まえて、1612年に幕府は、キリスト教への信仰を抑えるため、まずは直轄地(ちょっかつち)の幕僚(ばくりょう)にキリスト教禁止令(禁教令)を出し、翌年には全国に広げました。
キリスト教の神への信仰を領主への忠義よりも重んじるという教えが、幕府の考えに反していたためです。
家康の次の第2代将軍である徳川秀忠(とくがわひでただ)も、この禁教令をさらに強化し、多くのキリスト教徒を処刑していきました。
1635年になると、第3代将軍である徳川家光(とくがわいえみつ)は朱印船貿易を停止しただけでなく、日本人の海外への出国と帰国を一切禁止しました。
さらに長崎の海に出島(でじま)を築き、ポルトガル人を移して、日本人と交流できないようにしました。また中国船が長崎以外の港に来ることも禁じてしまいました。
島原・天草一揆と鎖国
禁教令の強化に伴うキリスト教徒への迫害や、幕府の重い年貢の取り立てに苦しんだ島原<長崎県>や天草<熊本県>の人々は、1637年になると、天草四郎(あさくさしろう)<益田時貞(ますだときさだ)>という少年を大将にして一揆を起こしました。
この一揆を島原・天草一揆(しまばらあまくさいっき)といいます。
翌1638年、幕府は一揆を鎮圧(ちんあつ)しましたが、1639年にはポルトガル船の来航を禁止したうえ、大名には沿海の警備を指示しました。
さらに1641年には、平戸のオランダ商館を長崎の出島に移しました。
こうして、ポルトガル船は排除され、中国船とオランダ船だけが、長崎で貿易を許可されることになりました。
この体制を鎖国(さこく)と呼び、幕府による禁教、貿易統制、外交独占が行われるようになりました。
鎖国は、後には「祖法(先祖伝来の法律)」とされ、昔からそうだったと言い伝えられるようになりました。
補足ですが、当時の人々が鎖国といっていたわけではなく、実際に鎖国という言葉が用いられるようになったのは、19世紀初めのことのようです。
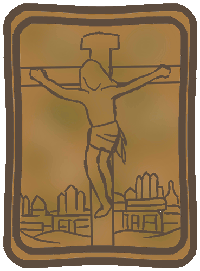
幕府は、改宗したキリスト教徒を監視し、キリスト教徒を発見するために絵踏(えふみ)を行いました。
踏絵(ふみえ)とも呼ばれ、役人の前でキリストや聖母マリアの像の絵を踏まさせ、毎年正月の行事として、江戸時代末期まで行われたようです。
また、仏教徒であることを寺に証明させる宗門改(しゅうもんあらため)や、葬式も寺で行われるようになりました。
鎖国下の対外政策
中国とオランダ
江戸時代の鎖国下において長崎で貿易を許されていたのは、中国とオランダだけでした。
このころ中国では、17世紀半ばに、明が国内の反乱によってほろび、清(しん)という中国東北部の女真族(じょしんぞく)が建国した国が、中国全土を支配するようになっていました。
日本人は鎖国によって海外に行くことができなくなり、東南アジア各地にあった日本町はなくなってしまいました。
ちなみに中国とオランダの貿易が許された理由は、日本が中国の上質な生糸や絹織物、東南アジアの品物を必要としていたことと、オランダ人はキリスト教の布教を行わなかったためで、長崎で貿易を行ないました。
江戸幕府は、当時最大の輸出品だった金や銀が大量に海外へ流出することを国の損失だと考えて次第に制限するようになります。
金や銀のかわりに銅や俵物(たわらもの)を輸出するようになりました。俵物とは、いりこ<なまこを煮て乾燥させたもの>、干しアワビ、ふかひれなどの中国料理の高級食材を俵の中に詰め込んだもののことを言います。
また幕府は、ヨーロッパやアジアの情勢を報告するようオランダ人に義務付け<オランダ風説書(ふうせつがき)>、中国人にも唐船風説書(とうせんふうせつがき)を提出させることにより、海外の情報を独占しました。
ヨーロッパの書物に関しては、輸入が許可されませんでした。
朝鮮と琉球(りゅうきゅう)王国
江戸時代において、朝鮮は対馬藩<長崎県>、琉球王国<沖縄県>は薩摩藩<鹿児島県>をそれぞれ窓口としてつながっていました。
朝鮮は、対馬藩の努力の甲斐あって国交が回復し、将軍が変わるごとなどにお祝いとして使節<朝鮮通信使(ちょうせんつうしんし)>が日本に派遣されるようになりました。
通信使の一行は、300人から500人にもおよび、その中には一流の学者や芸術家もいて、各地で日本の学者と交流しました。
対馬藩は、朝鮮の釜山(ぶざん、ブサン)に設けられた倭館という居留地に役人を派遣し、朝鮮との連絡や貿易を行いました。
朝鮮からの輸入品は木綿(もめん)や朝鮮にんじん、絹織物などで、輸出品は銀や銅などでした。
琉球王国<沖縄県>は、薩摩藩<鹿児島県>に攻められ服属はしましたが、江戸幕府は琉球を異国と位置付け独立国のままとしました。
そのため、国際的にも独立国で、独自で明や清に朝貢(ちょうこう)し、貿易も行っていました。
そのかわり薩摩藩は役人を琉球に派遣し、間接的に中国との貿易を行って利益を得ました。
また薩摩藩は、将軍や琉球国王に代わりがあると、琉球からの使節を江戸に連れてきて、将軍に面会させました。これを琉球使節といいます。
アイヌ民族との交易
江戸時代の蝦夷地(えぞち)<北海道>には、アイヌ民族が暮らしていました。
アイヌの人々は、漁業などを行いながら、和人とだけではなく、千島(ちしま)列島や樺太(からふと)<サハリン>、中国大陸の黒竜江(こくりゅうこう)流域の人々とも独自交易していました。
松前藩は、蝦夷地の南部に領地(現在の北海道松前町)を持っていた地理的利点を生かし、幕府からアイヌの人々との交易の独占を許され、米や食器などの日用品を、さけやこんぶなどの海産物と交換して大きな利益を得たようです。
こうした取引が不平等だとの不満もあって、アイヌの人々は17世紀後半に首長のシャクシャインを中心に松前藩との戦いをおこしましたが敗れました。
「松前藩を追い払え」を合言葉に徐々に拡大されたこの戦いは、シャクシャインの戦いといいます。
アイヌの特徴ある民族衣裳として、蝦夷錦(えぞにしき)もこのころ北海道に伝えらえました。
★近世の日本★
③産業の発達と幕府政治の動き
農業や諸産業の発達
農業の進歩
皆さんのお父さんやお母さんも消費税やほかの税金が上がったというような話をしているかもしれませんが、江戸時代も同じような苦しみがありました。
取り立てる側の幕府や藩は、年貢(現代の税金にあたる年貢米)の収入を増やすため、用水路を造ったり、海や広い沼地を干拓(たんたく)したりして、大きな新田を開発していきました。
また、少しずつ荒地(あれち)を開墾する農民の努力もあって、農地の面積は、18世紀の初めには、豊臣秀吉のころの約2倍に増えたようです。
「農業全書」という生産性を高める技術・ノウハウ本がつくられた事によって近畿地方の進んだ農業の技術が各地に伝わり、深く耕すことができる備中ぐわや、脱穀(だっこく)を効率的にする千歯こきなどによって生産力があがりました。
都市では、織物や菜種油(なたねあぶら)しぼりなどの手工業が発展したことによって、農村では、その原料となる麻・綿・あぶらな・こうぞ・みつまたなどの商品作物の栽培が広がりました。
関連して、布や紙を着色するための染料としては、阿波(あわ)<徳島県>のあいや出羽村山(でわむらやま)地方<山形県>の紅花、宇治(うじ)<京都府>の茶、紀伊(きい)<和歌山県>のみかん、備後(びんご)<広島県>のいぐさ、薩摩(さつま)<鹿児島県>のさとうきびなどが生産され、地方の特産物になっていきました。
諸産業の発達
江戸幕府は、流通貨幣の整備を行いました。
ちなみに、それまで主に使われていたのは、中国で造られた明銭(みんせん)などが使われていましたが、使われなくなりました。
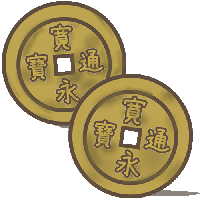
江戸(東京都)や京都に設けた金座や銀座で、幕府が定める品質の小判などの金貨や丁銀(ちょうぎん)、豆板銀(まめいたぎん)などの銀貨を造ったほか、銅貨として寛永通宝(かんえいつうほう)を各地の銭座(ぜにざ)で大量に造らせ、全国に流通させました。
この背景として、貿易で輸出したり貨幣を造ったりするため、鉱山での採掘や精錬(せいれん)の技術が発達したことが大きいです。
佐渡金山<新潟県>、生野銀山<兵庫県>、石見銀山<島根県>などの金山・銀山の開発が進んだほか、別子銅山<愛媛県>や足尾銅山<栃木県>などの銅山が新たに開かれました。
江戸時代には、林業や水産業もさかんになりました。
林業は、都市の発展に伴い建築用の木材が大量に使われたため、木曽(きそ)<長野県>、秋田などで発達しました。
水産業は、網を使った漁が全国に広まり、千葉県の九十九里浜では大規模な”いわし漁”が行われるようになりました。
いわしは肥料<干鰯(ほしか)>に加工され、近畿地方などの綿の生産地に販売されたようです。
また、紀伊<和歌山県(一部、三重県)> や土佐<高知県>では、捕鯨(ほげい)やかつお漁が盛んになりました。
蝦夷地(えぞち)<北海道>では、にしん漁やこんぶ漁も盛り上がりました。
17世紀末からは、この蝦夷地の俵物(たわらもの、ひょうもつ)が輸出品になり、中国料理の主要な食材になりました。
俵物とは、いりこ(干しなまこ)・干しアワビ・フカのひれを俵につめたものです。俵に詰められて輸出された事から、この名があります。
これらは高級な中国料理の食材として需要がとても高かったのです。
田沼意次(たぬまおきつぐ)は長崎貿易をさかんにするため、この俵物の輸出を奨励しました。輸入品の対価として金銀銅の流出をふせぐためというのが大きな目的だったようです。
江戸時代には、お酒をつくる酒造業も発達しました。
伊丹(いたみ)<大阪府>や灘(なだ)<兵庫県>では、江戸に送るお酒を大量に生産していたようです。
近い製造方法で同じ醸造業(ぞうじょうぎょう)のしょうゆは、当時主に関西にたよっていましたが、関東でも千葉県の野田や銚子などで大規模なしょうゆの生産が始まりました。
そのほか、瀬戸内海沿岸で塩田が発達し、製塩業の生産量が増大しました。
伝統工芸品としては、金沢(かなざわ)<石川県>や有田(ありた)<佐賀県>の磁器、輪島(わじま)<石川県>や会津(あいづ)<福島県>の漆器(しっき)、南部<岩手県>の鋳物(いもの)、越前(えちぜん)<福井県>や美濃(みの)<岐阜県>の紙など、各地に特産物が生まれ諸産業が発達しました。
交通路の整備と都市の繁栄
交通路の整備
幕府は交通路として、五街道(ごかいどう)や、脇(わき)街道と呼ばれる主要な道路を整備しました。
五街道とは、江戸と京都とを結ぶ①東海道のほか、②中山(なかせん)道、③甲州道中(こうしゅうどうちゅう)、④日光道中、⑤奥州(おうしゅう)道中のことです。
東海道の箱根や新居(あらい)、中山道の碓氷(うすい)などには人々の通行や荷物の運送を監視するため、関所を設けました。
「入り鉄砲に出女」という言葉がありますが、関所では江戸方面への鉄砲の持ち込みと、江戸に住む大名の妻がひそかに領地にもどることを特に警戒していたようです。
街道には宿場が置かれ、運送用の人や馬を置けることが義務付けられ、幕府の用務に使われました。
宿場にもランクがあり、主に本陣(ほんじん)と旅籠(はたご)に分かれていました。
本陣は幕府の役人や大名が宿泊し、旅籠は庶民が宿泊し、参勤交代の行列や旅人が利用しました。
今でいう郵便屋さんのような存在の手紙や荷物を運ぶ飛脚(ひきゃく)も盛んに街道を行き来しました。
ちなみに江戸から京都までは約492kmで、普通に歩くと2週間ほどかかるようですが、飛脚はわずか3~4日で走ったようです。
諸産業の発達にも支えられ、陸上や海上の交通路が全国的に整備され、港町や宿場町、門前町などの都市が栄えました。
江戸が大都市として発展していくにつれ、生産力の発達していた近畿地方の物資を、大阪から江戸に大量に運送するため、海路が運送の中心になっていくようになります。
17世紀中ごろからは、定期船が往復するようになりました。
菱垣廻船(ひがきかいせん)という木綿(もめん)や油、しょうゆを運ぶ船や、樽廻船(たるかいせん)という酒を運ぶ船などがありました。
また、江戸の町人であり政商であった河村瑞賢(かわむらずいけん)は、東北地方や北陸地方の年貢米を大阪や江戸に安全かつ効率的に運送する新しい海運ルートとして西廻り航路や東廻り航路を開き、海運の発展に貢献しました。
三都の繁栄
江戸時代の17世紀後半において、三大都市の三都(さんと)とは、江戸・大阪・京都の三つの都市を指します。
現代においては、三大都市圏の中心都市を指し、東京・大阪・名古屋を指す場合や、JR西日本の観光キャンペーンで、京都・大阪・神戸を指す場合などがありますので、江戸時代の三都は、江戸・大阪・京都と覚えて下さい。
「江戸」は「将軍のおひざもと」と言われる将軍の城下町(じょうかまち)でした。18世紀の初めには人口が約100万人にのぼる世界最大級の大都市に発展しました。
江戸に設けられた諸藩(しょはん)の江戸屋敷(やしき)には、全国から多くの武士が集まり、その生活を支える商人や職人も増加しました。
「大阪」は「天下の台所」と言われる全国の商業の中心地でした。
北陸や西日本の諸藩は大阪に蔵屋敷(くらやしき)という倉庫を備えた邸宅(ていたく)を置き、年貢米や特産物を販売していました。
「京都」は「古都」といわれる朝廷や大きな寺社がある古くからの都で、学問や文化の中心でもありました。
また、手工業も盛んで、西陣織(にしじんおり)、京焼(きょうやき)など、高い技術で優れた工芸品を生産していました。
都市では、問屋(といや)や仲買(なかがい)などの大商人がいましたが、株仲間(かぶなかま)という同業者組織を作り、幕府の許可を得て営業を独占するようになりました。
そのころ流通していた貨幣は、主に東日本では金、西日本では銀と別々に流通していたため、両替商(りょうがえしょう)が金銀の交換や金貸しによって経済力を持つようになりました。
江戸の三井(みつい)家や大阪の鴻池(こうのいけ)家のように有力なものは、大名にも貸し付けを行い、藩の財政にも関わるようになりました。
幕府政治の安定と元禄文化
綱吉の政治と正徳の治
第5代将軍の徳川綱吉(とくがわつなよし)は、儒学(じゅがく)を学ぶことをすすめ、なかでも身分秩序(ちつじょ)を重視する朱子学(しゅしがく)が広く学ばれました。
また綱吉は、人々に慈悲(じひ)の心を持たせるため、極端な動物愛護政策である生類憐みの令(しょうるいあわれみのれい)を出しました。
綱吉が戌年生まれだったことから特に犬を保護したことが有名で、「お犬様」「犬バカ将軍」という良くないイメージが強いようですが、当時は、犬だけでなく姥捨て山や捨て子、病人や牛馬などを山野に捨てたりするといったことが普通に行われていたので、これを禁止した名君という良い見方もあるようです。
そのような中で綱吉は、寺院などの建設で幕府の財政が苦しくなると、貨幣にふくまれる金銀の量を減らし、質を落として発行する量を増やし、幕府の収入を増やそうとしましたが、物価の上昇を招き人々の生活は苦しくなっていったようです。
こうした人々の苦しかった時代背景もあって、今の綱吉の良くない方のイメージ像が出来上がったのかもしれませんね。
綱吉の後、18世紀初めの正徳年間には、儒学者の新井白石(あらいはくせき)の意見が政治に取り入れられました。
新井白石は幕府の儀式を整え、将軍を朝鮮王国と対等にするため日本国王という呼び方に改め、朝鮮通信使の待遇を簡素にするなどの政策を行いました。
また、綱吉が下げた貨幣の質を元に戻す一方、金銀が海外に流出することを防ぐため貿易額を制限しました。
こうした新井白石の行った政治改革を正徳の治(しょうとくのち)と言います。
正徳は江戸幕府の第6代将軍の徳川家宣・第7代将軍の徳川家継の治世の年号で、文治主義と呼ばれる諸施策を推進しました。
尚、次の第8代将軍・徳川吉宗が行った享保の改革により相当部分は修正されますが、継続された政策も数多くあります。
元禄の学問と文化
幕府の政治が安定すると、日本の歴史や「万葉集」(まんようしゅう)、「源氏物語」(げんじものがたり)などの古典に関する研究が進みました。
御三家(ごさんけ)の水戸藩主であった徳川光圀(とくがわみつくに)は、「大日本史」を作成するため、全国から学者を集め作成を命じました。
綱吉や新井白石が儒学と関係が深かったように中国の儒学の古典を研究する学問も始まりました。農学・天文学・数学においても、独自の発展が見られました。
京都や大阪を中心とする上方では、都市の繁栄を背景に、経済力を持った町人をにない手とする新しい文化が栄えました。
これをこの時期の年号から、元禄文化(げんろくぶんか)といいます。
井原西鶴(いはらさいかく)は、武士や町人の生活を基に浮世草子(うきよぞうし)<小説>を書き、人形浄瑠璃(にんぎょうじょうるり)においては、近松門左衛門(ちかまつもんざえもん)が心中など現実に起こったリアル事件を基に台本を書き、庶民の共感を呼んだようです。
歌舞伎(かぶき)は演劇として発達し、上方に坂田藤十郎(さかたとうじゅうろう)、江戸に市川団十郎(いちかわだんじゅうろう)などの名優が出ました。
ちなみに上方(かみがた、かみかた)とは、江戸時代に京都や大阪を始めとする畿内を指した呼称です。また広義では、畿内を始めとする近畿地方一帯を指す語としても使われる場合があります。当時の天皇の住む都(すなわち京都)を「上」とすることから用いられ、政治の中心である江戸に対し、古くからの経済・文化の中心地を指す語として用いられてきました。

俳諧(はいかい)<俳句(はいく)>では、松尾芭蕉(まつおばしょう)が自己の内面を表現する新しい作風を生み出しました。
俳句は全国的なブームとなり、芭蕉は全国を歩いて「奥の細道」などを執筆しました。
絵画では、大和絵(やまとえ)も盛んになりました。
17世紀前半に、俵屋宗達(たわらやそうたつ)が始めた大胆な構図の新しい装飾画(しょうしょくが)が発展し、元禄の時期には尾形光琳(おがたこうりん)が、独自の構図と色彩ではなやかな装飾画を完成させました。
菱川師宣(ひしかわもろのぶ)は、都市の町人の風俗(ふうぞく)を基に浮世絵(うきよえ)をえがき、版画も制作されたようです。
庶民の衣服は、木綿が一般的になり、絹の小袖(こそで)には優美な友禅染(ゆうぜんぞめ)がトレンドになりました。
菜種油(なたねあぶら)を使う行灯(あんどん)が広まって夜おそくまで起きているようになり、食事は1日3食が普通になったようです。
また、今では日本における一般的な季節イベントですが、正月の雑煮(ぞうに)や七草・節分の豆まき・ひな祭り・こいのぼり・盆踊りなどの年中行事が庶民にも広まったのも元禄文化の時代と言われています。
享保の改革と社会の変化
享保の改革
1716(享保元)年に徳川吉宗(とくがわよしむね)が御三家の一つであった紀伊(きい)<和歌山県>藩主から第8代将軍になりました。
幕府は、第5代将軍の綱吉のころから財政難に苦しんでいたため、吉宗は、武士に質素・倹約(けんやく)を命じ、上げ米(あげまい)の制を定めました。
米の値段の安定に努め、代官などに有能な人材を登用し、新田の開発を進めました。
米の値段の安定に努めたので「米将軍」とも呼ばれていたようです。
そのほか、公事方御定書(くじかたおさだめがき)という裁判の基準になる法律を定め、庶民の意見を聞く目安箱(めやすばこ)を設置しました。
また、キリスト教は依然NGでしたが、関係しない科学技術などの漢訳されたヨーロッパの書物の輸入を認めるようになりました。
吉宗の行った享保の改革(きょうほうのかいかく)によって、財政は一時的に立ち直った形となりました。
貨幣経済の広がり
正徳の治により金銀が海外に流出することを防ぐ目的で長崎での貿易額が制限されたため、木綿(もめん)や生糸(きいと)、絹織物などは輸入する量が大幅に減ってしまいました。
そのため、これらの産物の日本国内での国産化が進められました。
綿の栽培は全国に普及し、綿織物業は大阪周辺のほか、尾張(おわり)<愛知県>などで発達しました。
養蚕も各地で行われ、絹織物の技術が桐生(きりゅう)<群馬県>や足利(あしかが)<栃木県>に伝えられ、西陣織(にしじんおり)と並ぶ質の良い製品ができるようになっていきました。
農業の発達にともなって農村にも変化が訪れてきます。
農具や肥料を購入するなど農民にも貨幣が必要になり、自給自足に近かった農村は変わっていきました。
土地を手放して小作人(こさくにん)になる者や、都市に出かせぎに出る者も多くなり、一方では土地を買い集めて地主となる者が出るなど、農民の中でも貧富の差が拡大していきました。
農村では、農民が作物を自分で製品に加工して問屋(といや)に売る家内(かない)工業が発達してきました。
18世紀ごろになると、商品を買い集める問屋が農民に織機(しょっき)やお金を前貸しして布を織らせ、製品を安く買い取る問屋制家内工業(といやせいかないこうぎょう)が発達しました。
その後、19世紀ごろになると、大商人や地主の中に工場を建設し人をやとって分業で製品を作る者が現れました。
これを工場制手工業(こうじょうせいしゅこうぎょう)<マニュファクチュア>といい、近代工業が発展する基礎になりました。
家内工業→問屋制家内工業→工場制手工業の発展順ですので、違いを理解しましょう。
百姓一揆と差別の強化
18世紀になると、農民を中心とした民衆も団結し反発・反抗するようになってきます。
百姓一揆や打ちこわしなどが各地で行われるようになりました。
百姓一揆は、今でいうストライキの農民版で、多くの農村が団結して、領主に年貢の軽減や不正を働く代官の交代などを要求したり、大名の城下におし寄せたりしました。
からかさ連判状といわれる紙に一揆の中心人物が分からないように、円形に参加者が署名したと言われています。
一方、打ちこわしは、米の買いしめをした商人などを、不正を働いた悪人とみなし、家屋などを破壊する行為を指し、都市部で行われたりしました。
これに対して幕府や藩は、えた身分、ひにん身分の人々に対して、日常生活や服装で、さらに統制を強め、百姓一揆をおさえるために農民と対立させたりしたこともあったようです。
このような中でも、これらの差別された人々は、助け合いながら生活を高めていき、人口の増加も見られました。
田沼意次と寛政の改革
田沼意次の政治
18世紀後半、老中になった田沼意次(たぬまおきつぐ)は、貿易を奨励(しょうれい)し、新しい輸出品の開発に力を入れました。
長崎での貿易を活発にするため、輸出品である銅の専売制を実施し、蝦夷地(えぞち)<北海道>の調査を行い、俵物の輸出を拡大しました。
商工業者が株仲間(かぶなかま)を作ることも奨励し、これに特権をあたえるかわりに営業税を取るようにしたようです。
さらに田沼意次は、印旛沼(いんばぬま)<千葉県>の干拓も始めました。
この時代は商工業が活発になり自由な風潮の中で学問や芸術が発展しましたが、地位や特権を求めて「わいろ」が横行したようです。
また、1782(天明2)年に起こった天明の飢饉(ききん)は、翌年の浅間山(あさまやま)の大噴火などによる凶作も加わり、全国に広がってしまいました。
各地で百姓一揆や打ちこわしが相次ぎ、田沼意次は責任を取らされ老中を辞めさせられてしまったようです。
寛政(かんせい)の改革
田沼の次は、松平です。
1787年に、江戸や大阪で大規模な打ちこわしが起こりました。
天明の打ちこわし(てんめいのうちこわし)といい、当時の江戸や大阪など主要都市を中心に30か所あまりで発生し、石巻、小田原、宇和島などへ波及した打ちこわしの総称です。
打ちこわしとは、少し前にも説明しましたが、江戸時代の民衆運動の形態のうち、不正を働いたとみなされた者の家屋などを破壊する行為のことです。
こうした中で、政権争いをしていた田沼派を退け、新しく老中になった松平定信(まつだいらさだのぶ)は、祖父徳川吉宗(とくがわよしむね)の政治を理想とする改革を始めました。
松平定信が行った一連の政治改革を寛政の改革と言います。
一言でいうと厳しい統制だったようです。
例えば、江戸などに出てきていた農民を故郷に帰し(Uターンの強制のようなイメージ)、凶作やききんに備えるため、各地に倉を設けて米をたくわえさせ、商品作物の栽培を制限したりしたようです。
また、江戸の湯島(ゆしま)に昌平坂学問所(しょうへいざかがくもんじょ)を創り、ここでは朱子学(しゅしがく)以外の学問を教えることを禁じ、試験を行って有能な人材の登用を図りました。
さらに、倹約令を出す一方、旗本や御家人が札差(ふださし)からしていた借金を帳消しにしました。札差は、旗本・御家人の年貢米を金にかえる業者でしたが、金融業も営み、富裕になっていたようです。
しかし、政治批判を禁じたり、出版を厳しく統制し過ぎたようで、松平が行った寛政の改革は当時の人々の反感がとても強かったようです。
こうした中、1792年に、ラクスマンというロシアの使節が蝦夷地<北海道>の根室に来航し、漂流民の大黒屋光太夫(だいこくやこうだゆう)を送り届けます。
ラクスマンが幕府にロシアとの通商を求めてくると、幕府は、長崎で交渉すると回答しました。
1804年、交渉のために長崎へ来たロシアの使節レザノフに対し、幕府は、すでに国交のある朝鮮、琉球(りゅうきゅう)<沖縄県>や貿易をしているオランダ、中国以外の国とは関係を持たないのが国の決まりだとして、ロシアとの通商を断りました。
幕府は、蝦夷地や樺太(からふと)<サハリン>の調査を行い、19世紀前半まで蝦夷地を幕府の直接の支配地としたうえでロシアを警戒しました。
財政難に苦しむ諸藩
地方の諸藩は、17世紀後半(だいたい江戸時代初期で、ちょうど武家諸法度や参勤交代が根付いたころ)から財政が苦しくなり、藩札(はんさつ)と呼ばれる藩独自の紙幣を発行したり、家臣の俸禄(ほうろく)を減らしたりしていました。
18世紀後半(だいたい江戸時代中期で田沼&松平の時代)には、諸藩でも独自改革が行われました。
米沢藩<山形県>は、うるし<漆器(しっき)の塗料>。熊本藩は、はぜ(ろうの原料)などの特産物の生産を奨励し、専売制を採って財政の立て直しを行い成功しました。
新しい学問と化政文化
国学と蘭学(らんがく)
18世紀後半(だいたい江戸時代中期で田沼&松平の時代)には、学問として日本の古典の研究が進められました。
本居宣長(もとおりのぶなが)は、日本古来の伝統を評価する「古事記伝」(こじきでん)を著書・出版し、国学を大成しました。
国学はその後、天皇を尊ぶ思想と結び付き、幕末<江戸時代末期のこと>の尊王攘夷(そんのうじょうい)運動に影響をあたえました。
杉田玄白(すぎたげんぱく)は、ヨーロッパの解剖書(かいぼうしょ)を翻訳(ほんやく)した「解体新書」(かいたいしんしょ)を出版し、オランダ語でヨーロッパの学問や文化を学ぶ蘭学(らんがく)の基礎を築きました。
ほかにもオランダ語の辞書や文法の書物を作ったり、オランダの医学書を翻訳したりする者も現れました。蘭学を学ぶ者は次第に増加していき、その後の日本近代化の基礎が築かれました。
18世紀末、幕府ではヨーロッパの天文学を取り入れた日本独自の暦(こよみ)を作ります。
ちなみに日本の暦は、江戸初期までは中国歴を使用していたようで、江戸中期からはここでいうヨーロッパの天文学を取り入れた日本独自の暦、明治初期以降はグレゴリオ暦の3つの時代に分けられます。
19世紀初めになると、伊能忠敬(いのうただたか)がヨーロッパの技術で海岸線を測量し、17年をかけて日本全国を測量して、正確な日本地図を作りました。
『大日本沿海輿地全図』(だいにほんえんかいよちぜんず)という地図で、別名「伊能図」とも呼ばれています。
化政文化
19世紀の初めの文化は、中心地が上方(かみがた)<江戸時代に京都や大阪を始めとする畿内を呼んだ名称> から江戸に移りました。
おもに第11代将軍の徳川家斉(とくがわいえなり)の時期に、庶民をにない手として発展した文化で、文化(ぶんか)・文政(ぶんせい)年号の化と政をとって、化政文化(かせいぶんか)といいます。
現代でも人気が続いていますが、歌舞伎(かぶき)は舞台や演目が工夫され、落語などを楽しむ寄席(よせ)が数多く造られ、大相撲も人気を集めました。
尚、大相撲は庶民だけでなく第11代将軍の徳川家斉も江戸城に力士をよび観戦したこともあったようで、大人気になったようです。
江戸を中心に発展した庶民をにない手として発展した化政文化は、徐々に地方にも広がっていきました。
浮世絵の技術もこの時代に進化しました。
まず、鈴木春信(すずきはるのぶ)は、錦絵(にしきえ)と呼ばれる多色刷りの版画を始めます。
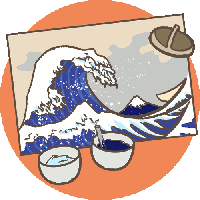
この錦絵が大流行し、東洲斎写楽(とうしゅうさいしゃらく)は人気の歌舞伎役者の絵、喜多川歌麿(きたがわうたまろ)は美人画、葛飾北斎(かつしかほくさい)や歌川広重(うたがわひろしげ)は風景画に優れた作品を残しました。
これらの作品は、その後ヨーロッパの絵画にも大きな影響をあたえました。ジャポニズムといい、オランダ人画家のゴッホもその一人で、歌川広重の浮世絵をまねた油絵を好んで描いたようです。
文学では、幕府を批判したり世相を皮肉ったりする川柳(せんりゅう)や狂歌(きょうか)が流行しました。
また、貸本屋(かしほんや)が発達し、十返舎一九(じっぺんしゃいっく)のこっけい本「東海道中膝栗毛」(とうかいどうちゅうひざくりげ)や滝沢馬琴(たきざわばきん)の「南総里見八犬伝」(なんそうさとみはっけんでん)などの長編小説が多くの人に読まれました。
伝統的な俳諧(はいかい)<俳句(はいく)>では、与謝蕪村(よさぶそん)が絵のように風景を表現したり、小林一茶(こばやしいっさ)は農民の素朴な感情を詠んだりしました。
また、庶民も旅行がしやすくなり、湯治(とうじ)<温泉にはいって療養すること>や観光をかねた寺社参詣(さんけい)が盛んになったようです。
教育の広がり
化政文化の時代、京都や大阪などでは、学者が私塾を開くようになり、武士だけでなく町人や百姓の入門も許されるようになりました。
医学の勉強も大阪の医者であった緒方洪庵(おがたこうあん)が適塾(てきじゅく)を開き、日本全国から弟子が集まるようになりました。
長崎では、オランダ商館の医者シーボルトが医学塾を開き、手術などを行って見せました。
地方の諸藩(しょはん)では、どれだけ有能な人材を育成できるかに藩の将来がかかっていることを明確に認識するようになり 藩校(はんこう)を設け、武士に学問や武道を教え、人材の育成を図りました。
庶民の間にも教育への関心が高まり、町や農村に多くの寺子屋(てらこや)が開かれ、読み・書き・そろばんなどの実用的な知識や技能を教えました。
寺子屋の正確な数は不明ですが幕末になると全国で約1万5千以上も存在していたようです。この寺子屋が江戸時代の人々の高い識字率を支えていました。
外国船の出現と天保の改革
異国船打払令と大塩の乱
19世紀になると、ロシア(前に、松平定信の寛政の改革で、ラクスマンやレザノフとの通商交渉で1804年に断りました)だけでなく、イギリスやアメリカの船も日本に近づくようになります。
1808年には、フェートン号事件というイギリスの軍艦が長崎の港に侵入する事件が起こりました。
幕府は1825年に、異国船打払令(いこくせんうちはらいれい)を出します。
1837年 には、モリソン号事件という漂流民(ひょうりゅうみん)を引きわたし、通商を求めたアメリカの商船を砲撃するという事件も起こりました。
1839年には、蛮社の獄(ばんしゃのごく)という言論弾圧事件が起きます。
モリソン号事件と江戸幕府の鎖国政策を批判した 蘭学者の渡辺崋山(わたなべかざん)と高野長英(たかのちょうえい)が、外国船の打ちはらいを批判する書物を書いたため、幕府によって捕らえられて獄に繋がれるなど罰を受けた他、処刑された事件です。
海外からの脅威に加え、1830年代には、国内でも、天保の大飢饉(だいききん)が全国をおそいます。
百姓一揆や打ちこわしもたびたび起こりました。
元大阪町奉行所の役人で陽明学者(ようめいがくしゃ)の大塩平八郎(おおしおへいはちろう)は、1837年に大塩の乱(おおしおのらん)という反乱を起こします。
奉行所の対応に不満を持ち、弟子など300人ほどでぜいたくな暮らしをしている大商人をおそい、米や金をききんで苦しむ人々にわけようとしました。
大塩の乱自体は、1日でしずめられましたが、全国に知れわたり各地で「大塩門弟」(おおしおもんてい)を名乗る一揆が誘発したことと、役人であった大塩平八郎の反乱に幕府は大きな衝撃を受けました。
天保の改革
天保の大飢饉終息後の1841年には、老中であった水野忠邦(みずのただくに)が、第12代将軍に徳川家慶(とくがわいえよし)の信任を受け、幕府の力を回復させるため、天保の改革(てんぽうのかいかく)を行いました。
倹約令を発令し、町人の派手な風俗を取りしまったり、政治批判や風紀を乱す小説の出版を禁止したりしました。
さらに物価の上昇をおさえるため、営業を独占している株仲間に解散を命じ、江戸に出かせぎに来ていた農民を故郷の村に帰らせました。またまた強制Uターンですね。
こうした中、水野忠邦は、アヘン戦争で清(しん)がイギリスに敗れたことでイギリスの強さを知ります。
異国船打払令という強硬策をやめ、日本に寄港した外国船には燃料のまきや水をあたえるよう命じる一方で、軍事力の強化を目指しました。
銚子から江戸湾までの水路を造るために印旛沼の開発を再開します。
さらに江戸や大阪周辺の農村を幕領(ばくりょう)にしようとしましたが、大名や旗本の強い反対にあい、忠邦は、改革の開始からわずか2年余りで老中を辞めさせられ、天保の改革は失敗となりました。
雄藩(ゆうはん)の成長
主に西日本の諸藩(しょはん)は、天保の大飢饉などで疲弊した財政を立て直すため、独自の改革を行っていました。
薩摩藩<鹿児島県>は、奄美(あまみ)群島で作られる黒砂糖(くろざとう)の専売制や、琉球(りゅうきゅう)を使った密貿易などで経済力をたくわえました。
肥前(ひぜん)藩<佐賀県・長崎県>は陶磁器(とうじき)を専売制にし、ヨーロッパに輸出しました。
長州藩<山口県>は、下関でほかの藩の船に対する金融業を行いました。
また、薩摩藩、肥前藩、長州藩は、外国船に対する軍備を強化し、製鉄用の反射炉(はんしゃろ)を建設して、大砲などを製造しました。
これらの藩は、強化された藩権力を兵制改革にあてて、幕府と対峙する力を蓄えた<幕末の>雄藩と呼ばれました。
中学2年生の【歴史】
開国と近代日本の歩み
★開国と近代日本の歩み★
①欧米の進出と日本の開国
近代革命の時代
ヨーロッパの動向
ヨーロッパでは、17世紀から18世紀にかけて各国が激しく争いました。
17世紀にはオランダが栄え、次はフランスが強国として台頭し、続いてイギリスも急速に国力をつけて、18世紀にはイギリスとフランスが最強国の地位を競って何度も戦争をしました。
またこの時代には、イギリスとフランスで近代革命が起こったり、アメリカ合衆国が独立するなど、それぞれの国で、新しい政治の仕組みや考え方が生まれますので、詳しく見ていきましょう。
イギリス革命
イギリスの政治の中心は1215年に定められたマグナ・カルタに起源をもつ国王と議会による立憲君主制でした。
17世紀半ばの国王は議会を無視した政治を続けたため、こうした専制に反対する議会との間で内戦が起こりました。
キリスト教の一派であるピューリタン(清教徒)たちが、クロムウェルという人物の指導のもとで立ち上がりました。
そして、議会側がクロムウェルの指導で勝利し、国王を処刑して、1649年に国王のいない政治体制共和制を始めました。
イギリス議会で多数を占めるピューリタンたちが国王を倒し共和制を実現した一連の動きをピューリタン革命(または清教徒革命)といいます。
クロムウェルの死後、イギリスは王政にもどります。
しかしながら、再び国王が専制を行ったため、1688年から89年の名誉革命によって議会を尊重する国王が新たに選ばれ「権利章典」が定められました。
権利章典は、国王の権力を制限する形で議会の権利を確認したものです。
ピューリタン革命と名誉革命をあわせてイギリス革命と呼びます。
議会政治のもとでの立憲君主政という政治はイギリスが世界初で、この制度は19世紀から20世紀に、他国にも広がっていくようになりました。
アメリカ合衆国の独立
北アメリカのイギリス植民地は、18世紀に急速に発展しました。
しかしながら、植民地の人々がイギリス本国の議会に代表を送ることは認められていませんでした。
イギリスは、フランスとの戦争の費用が財政を圧迫したために、新税を植民地にかけましたが、植民地側は「代表なくして課税なし」と唱えて反発しました。
イギリスがこれを弾圧したために独立戦争が始まり、植民地側は1776年に独立宣言を発表しました。
アメリカはフランスなどの支援を受けて独立戦争に勝ち、人民主権・連邦制・三権分立を柱とする合衆国憲法を定め、初代大統領に独立戦争の最高司令官を務めたジョージ・ワシントンが選ばれました。
こうして世界初の大統領制が生まれましたが、独立直後のアメリカは、まだ奴隷制が続いており、大陸東部の13州だけを領土とする国だったようです。
余談ですが、独立宣言が行われた日は、7月4日で「独立記念日(インディペンデンス・デイ)」と呼ばれ、毎年アメリカ合衆国の祝日になっています。
また自由の女神像は、この独立戦争を支援したフランス人の募金によって、独立100周年を記念してフランスよりアメリカ合衆国に贈呈されました。
啓蒙思想(けいもうしそう)
17世紀から18世紀のヨーロッパでは、ニュートンなどが天体の運動法則を解明し自然科学が発達しました。
一方で、人間の社会についても啓蒙思想(けいもうしそう)とよばれる新しい考え方が登場しました。
啓蒙思想とは、聖書や神学といった従来の権威を離れ、理性による知によって世界を把握しようとする思想運動のことです。
代表的な思想家として、ロック・モンテスキュー・ルソーなどは、国王の権力の制限を唱え、人民の政治参加の在り方について考えました。
尚、ロックは社会契約説と抵抗権を唱え、モンテスキューは法の精神と三権分立を主張、ルソーは社会契約説と人民主権を主張しました。
こうした啓蒙思想は、本や新聞、雑誌、百科事典などを通じて広まっていき、アメリカ独立宣言や、後のフランス革命に大きな影響をあたえるようになりました。
フランスの絶対王政
17世紀後半からのフランスでは、絶対王政(ぜったいおうせい)が行われていました。
絶対王政とは、議会を開かずに国を治め、国王が政治権力の全てをにぎる政治のことです。
ルイ14世がパリ郊外に建設したベルサイユ宮殿の広大かつ美しさに絶対王政時代のフランスの繁栄と王の権力が象徴されています。
言論は規制され、身分による貧富の差は大きく、第一身分(聖職者)と第二身分(貴族)と第三身分(平民)に分けられ、税の負担は人口の約90%をしめる第三身分(平民)が主になっていただけでなく、約10%の第一身分(聖職者)と第二身分(貴族) は免税などの特権を持ち優遇されていました。
18世紀のフランスは、イギリスと戦争を続けていたため、財政赤字をかかえながらも、有効な対策をとれずにいました。その一方で、フランスの政治と社会を批判する啓蒙思想は、弾圧を受けながらも、一部の貴族や平民に支持されていきました。
フランス革命
こうした絶対王政に不満が広がっていた中、バスチーユ牢獄の襲撃をはじまりとし、共和制を目指すフランス革命が起こりました。
きっかけは、アメリカ独立戦争を支援した戦費の支払いのために、1789年にフランス国王が第一・第二身分にも課税しようとして議会(三部会)を開催したため、パリでも地方でも人々がいよいよ反発したのです。
三部会の平民議員たちは新たに国民議会を作り、身分の特権を廃止し、人権宣言を発表しました。
人権宣言は、人間の自由と平等・国民主権・言論の自由・私有財産の不可侵(ふかしん)などが唱えられており、前文と17か条から成り、近代の人権思想の基礎になりました。
しかし、イタリア王国やスペイン王国などヨーロッパ周囲の王政国家がフランス革命の広がりをおそれ、軍を送って干渉したため、戦争が始まりました。
フランス革命政府は、敵国への協力が疑われた国王を廃位(はいい)したうえ処刑して共和制を始め、徴兵制(ちょうへいせい)で軍事力を強化しました。
また経済統制をするなど、戦争を進めるために政治と社会の仕組みを再び変更しました。
しかし、こうした絶対王政再回帰の動きに反乱する内乱も起こり、不安定な政治が続くうちに、外国との戦争で活躍した軍人のナポレオンが権力をにぎり、革命の終結を宣言して、1804年には皇帝の位に就きました。

ナポレオンは、イギリス以外のヨーロッパ諸国を軍事力で従わせました。さらに自分の一族を周辺国の王にし、ヨーロッパの大部分を支配しました。
また法の下(もと)の平等、経済活動の自由、家族の尊重を定める民法(ナポレオン法典)を制定しました。
「余の辞書に不可能の文字はない」とは、最盛期のナポレオンが日常よく口にした言葉とされています。
ナポレオンは、イギリスも従わせようとし、各国にイギリスとの貿易を禁じました。しかし、これに違反したロシアに攻めこんで敗れてしまったうえ、フランスの支配に反対する各地のナショナリズムの高まりによって敗戦を続け、ナポレオンの支配は1815年に終わりました。
その後のフランスでは、再び革命が起こるなど政治的に不安定な時期が続きます。
しかし、フランス革命は生まれや国籍を問わず、啓蒙思想に基づいて普遍的な人権を理想にかかげる革命だったので、世界中の抑圧に苦しむ人々に希望をあたえる結果を生み出しました。
産業革命と19世紀のヨーロッパ
産業革命
現代は、第4次産業革命(人によっては、すでにその次の第5次)の時代と言われています。
インダストリー4.0とも呼ばれ、ドイツ政府が推進し、アメリカなど欧米各国で急速に人材育成が進む製造業に関する技術革新プロジェクトによって知られるようになり、インターネット技術革新により産業に大きな変革をもたらすと言われるような概念です。
第4次というからには、最初の産業革命以降の4番目の主要な産業時代を指します。
その前の産業革命が存在するわけで、18世紀後半から19世紀に最初の産業革命がイギリスを起点に進展しました。
産業革命の起こった時代背景として、ヨーロッパには大航海時代以降、インドから手織りの綿織物が輸入され、軽さと模様の美しさなどで人気商品となっていたことが挙げられます。
ヨーロッパ各国は、綿織物を輸入に頼ることよりも自国で作ろうと技術改良を進めました。
18世紀後半になると、イギリスにおいて蒸気機関で動く機械を使い始めます。
綿織物は工場で安く大量に生産されるようになり、国内だけでなく大西洋の三角貿易の輸出商品になり、後にはそれ以前の輸入先であったインドに向けても逆に輸出されるようになりました。
蒸気機関が生み出す動力を活かし綿織物だけでなく、製鉄、機械、鉄道、造船、武器などの幅広い産業も急速に発達し始め、イギリスは19世紀に「世界の工場」と呼ばれるようになりました。
このような、工場での機械生産<工場制機械工業>などの技術の向上による経済と社会の仕組みの変化を、<第1次>産業革命といいます。
特に1825年に、イギリスのストックトン・ダーリントン間に開通した蒸気機関車は、この<第1次>産業革命の象徴とされました。
資本主義と社会主義
<第1次>産業革命の結果、資本主義という考え方が社会に広がっていきます。
資本主義とは、生産の元手になる資本を持つ者(資本家)が経営者になり、賃金をもらって働く者(労働者)を工場でやとって、利益の拡大を目的に、競争しながら自由に生産や取引をする仕組みです。
資本主義の広がりによって物が豊かになりました。
その一方で、工場の盛んな都市では労働者があふれて住宅が不足し、公衆衛生の面も不十分な状況でした。
失業も多く、労働者は職業と生活を守るために労働組合を結成しました。
またこのころ、資本主義を批判する社会主義の考えも芽生え、マルクスの著作「資本論」などによって労働者や知識人の間に広まりました。
ちなみにマルクスは、ドイツ・プロイセン王国出身の哲学者ですが、1845年にプロイセン国籍を離脱していて、以降は無国籍者です。
1849年にイギリスに渡った以降は、そのままイギリスを拠点として活動しました。
19世紀のイギリスとドイツ
イギリスは、19世紀に繁栄の時代をむかえました。
他国よりも早く産業革命を実現し、フランスのナポレオンとの戦争にも勝利できたためです。
首都のロンドンは世界最大の都市になり、鉄道網は全国に広げられました。
さらに、1851年にロンドンで世界初の万国(ばんこく)博覧会も開かれました。(ちなみに2025年の万博は、大阪で開催されます。)
イギリスはまた、強力な海軍を後ろだてにして、世界各地に商人や外交官を派遣し、通商や外交関係を広げる一方で、植民地も拡大していきました。
政治面では、議会政治の下で二大政党制が整い、労働者にも選挙権があたえられていきました。
19世紀のヨーロッパでは、イギリス以外の各国でも産業革命が進みました。
電気が普及し化学も発達しました。
また多くの国では、憲法が制定され、議会が開かれて人々の政治参加が実現されました。
同時に、義務教育も普及して「国民」としての意識が強まり、国家としてまとまっていくようになりました。
特にドイツ(プロイセン)の成長は目覚ましく、ビスマルクの指導の下、1871年に統一帝国になり、産業も発達して、イギリスに次ぐ強国になりました。
ビスマルクは、「鉄血宰相(さいしょう)」と呼ばれ、プロイセンの首相として富国強兵を進める一方で、たくみな外交術によって、諸国との戦争に勝ちドイツの統一を実現した人物です。
ドイツではこの頃、ヨーロッパ最大の社会主義政党も誕生しましたが、政府により弾圧されました。ちなみにこの時の政党名は、ドイツ社会民主労働党(1875年から1890年まで存在し、ドイツ社会民主党に改称した政党で、1931年から1945年にも再結成されます)といいます。
ロシアとアメリカの発展
ロシアの拡大
ロシアは17世紀初めまでの間、領土はウラル山脈周辺だけで、他のヨーロッパ諸国とは関係の弱い国でした。
その後ロシアは急速に東西に領土を拡大し、初代ロシア皇帝となったピョートル1世(ピョートル大帝とも呼ばれます)の功績などもありバルト海からシベリアにまで進出して、18世紀には日本の近海にも通商を求めて船隊を派遣するようになりました。
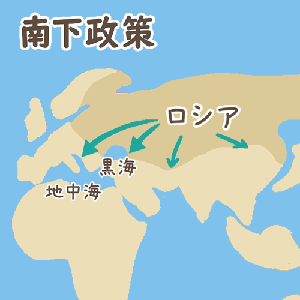
19世紀に入ると、ロシアは積極的な南下政策(なんかせいさく)を採るようになり、黒海や地中海の沿岸、中央アジア、さらには中国東北部へも進出しようとして、同様に中国に勢力をのばそうとしていた日本とも衝突することになります。
ロシアでは、中心地であった西ヨーロッパの産業革命の地理的影響も強くあり、19世紀末から工業が急速に発展しました。
その一方で、皇帝の専制政治が続き 、20世紀初めまで憲法や議会がなく、また身分や貧富の格差が大きいなど、他のヨーロッパ諸国と比べて国としての政治や社会の仕組みについては、後れた面があったようです。
さて次は、ロシアと同時期の18世紀から19世紀に急速に領土を拡大したアメリカの成長をみていきましょう。
アメリカ合衆国の成長
アメリカは、独立戦争を経て1776年7月4日にイギリスの植民地支配から独立しました。
19世紀に入るとヨーロッパから多くの移民を受け入れて人口が急速に増え、農業と工業が発展しました。
最初は、大陸東部の13州だけを領土としていましたが、戦争や土地の購入などによって、領土も急速に西に拡大し、19世紀半ばには太平洋岸に達しました。
アメリカは、さらに太平洋を超えて東アジアにも関心の目を向け、鎖国下であった日本にペリーなどの使節を送って開国をうながすようになりました。
この一方で、19世紀半ばのアメリカは、国内で奴隷制がまだ残っており、特に北部と南部で深刻な対立がありました。
当時のアメリカの経済は、イギリス向けの綿花の輸出が中心でしたが、これは南部での奴隷労働での生産で成り立っていました。
しかし、北部は奴隷制に反対で、南部は奴隷制に賛成だったため、国が西に拡大するにしたがって、新しい州で奴隷制を認めるかどうかが、国を二分する大問題になりました。
こうした南北対立から、1861年に南北戦争が起こりました。
北部、南部ともに多大な被害を出し、約62万におよぶアメリカ史上最大の戦死者を出した後、北部がリンカン大統領の指導の下にこの内戦に勝利しました。
リンカンは、南北戦争中のゲティスバーグでの演説で、「人民の、人民による、人民のための政治」を訴えました。
リンカンは第16代大統領で奴隷解放を実現した「偉大な解放者」としてアメリカ合衆国の歴代大統領の中でも傑出した評価がなされています。
南北戦争終息後のアメリカは、中国や日本などアジアからも移民を受け入れ、工業もいっそう発展していきます。
19世紀末には世界最大の資本主義国になった一方、奴隷の身分からは解放された黒人への人種差別などの問題も残念ながら残っていました。また国際的な政治という面では、ヨーロッパ国々との関わりをあえて避けていた傾向が強かったようです。
中南アメリカでは、大航海時代以来、スペインとポルトガルがすでに広大な植民地を持っていましたが、アメリカ合衆国の独立戦争の影響もあり、19世紀初めにメキシコやブラジル、アルゼンチンをはじめとする多くの国々がスペインやプロトガルから独立しました。
ヨーロッパのアジア侵略
ヨーロッパとアジアの力関係
16世紀から18世紀までのヨーロッパ諸国は、アジアの大国に対して、キリスト教の布教や富の獲得の意欲は持っていましたが、アジアの大国には力ずくではまだまだ勝てなかったようです。
しかし、19世紀以降の産業革命の結果、ヨーロッパはアジアに対し軍事力で優勢になっていきました。アジアの国々に対して戦争をしかけるようになり、相手を従わせ、支配することが可能になっていきました。
当時ヨーロッパは、アジアから茶や絹、綿織物、陶磁器(とうじき)などを輸入していましたが、かわりに工業製品をアジアに輸出しようとし始めました。
中でも、先頭に立って動いたのが、最初に産業革命を起こし19世紀に「世界の工場」と呼ばれ飛躍したイギリスでした。
アヘン戦争と中国の半植民地化
アジア侵略を目指したイギリスは、アジアの大国・清(しん)<中国>に対し、アヘン戦争をしかけました。
まず18世紀までの時代背景として、イギリスの対・清<中国>貿易が大きな赤字だったことがイギリス的には大きな問題でした。
イギリスは、清が欧米との貿易を広州(こうしゅう)1港に制限していて、綿織物などの工業製品が清国内では自由には売れなかったことを原因として考えていました。
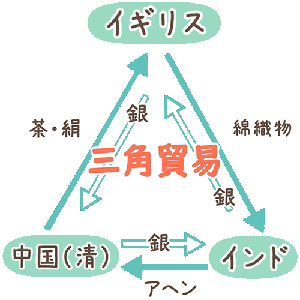
イギリスは、この対中国<清>貿易大赤字問題を解決し貿易を拡大させるための対策として、直接ではなく既に植民地としていたインドを巻きこむ三角貿易を進めました。
イギリスの考えた作戦は、綿織物をインドに輸出し、インドで麻薬の一種であるアヘンを栽培させて清に持ちこんで売り、清から茶などを買うようにしました。
アヘンを吸う習慣が清国内で広まったため、清が厳しく取りしまると、イギリスは1840年に戦争を起こして勝利しました。
この遠まわし的に仕組まれたような戦争をアヘン戦争といいます。
1842年の南京条約という講和条約によって、イギリスは上海など5つの港を開かせ、香港を手に入れ、さらに賠償金を支払わせました。
その翌1843年には、イギリスに領事裁判権を認め、清に関税自主権がない不平等条約を結びました。
領事裁判権とは、外国人が事件を起こした場合に、自国の裁判所ではなく、外国の領事が裁判を行う権利です。
関税自主権とは、自国に輸出入される商品にかける関税を独自に定める権利で、これが認められませんでした。
いずれも、イギリスにとって有利で、清にとっては不利な条件となりました。
その後、清が戦費や賠償金をまかなうために国内で重税を課したこともあり、洪秀全(こうしゅうぜんorホンシウチュワン)が率いる太平天国の乱が各地に広がりました。
太平天国の乱とは、1851年から1864年にわたる近代中国の大農民反乱で、南京を都に太平天国という独立国家を樹立しましたが、結局、郷勇(きょうゆう)とよばれる漢人有力者が組織した私兵集団勢力と外国軍の介入によって滅ぼされた反乱を言います。
この混乱の中で、イギリスはフランスとともに再び清を攻め、貿易のいっそうの自由化やキリスト教の布教を認めさせ、半植民地化を達成させました。
また、アヘン戦争にてアジアの大国清がイギリスに屈服したことは日本へもすぐに伝わり、江戸幕府<水野忠邦の活躍した天保の改革のころにあたります>は欧米諸国に対する警戒を強めました。
インドの植民地化
イギリスがインドに持っていた支配地は、初めはいくつかの港だけでした。
その後18世紀末から19世紀初めにかけて、徐々に支配地域を内陸に大きく広げていきました。
産業革命後には、イギリスの安い綿織物が大量にインドへ流入し、1820年以降は輸出額が逆転するなど伝統的なインドの綿織物業は打撃を受けました。
またイギリスは弱ったインドからさらに税を徴収し、イギリス本国に送りました。
このためイギリスに反感を持つインドの人々が増え、1857年にはインド人兵士のイギリス人上官に対する反乱が各地に広まり、インド大反乱が起こりました。
これを鎮圧(ちんあつ)したイギリスは、実権を失っていたインド皇帝を退位させ、イギリス国王を皇帝に立て、インドを世界に広がる植民地支配の拠点にしました。
東南アジアでは、スペインやオランダが植民地化を進めていましたが、イギリスやフランスも勢力を広げたため、19世紀には東南アジアの大部分がヨーロッパの植民地になりました。
開国と不平等条約
ペリーの来航
イギリスから独立したアメリカは、アヘン戦争後に中国との関わりを強め、太平洋をこえて東アジアとの貿易を望むようになりました。
アメリカ人の中には、鯨油(げいゆ)などを採るために太平洋で捕鯨を行い、日本へ漂流する者もいました。
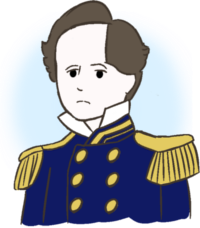
そのためアメリカは、日本を太平洋を横断する航路の中継地にするため、東インド艦隊司令長官ペリーを派遣しました。
ペリーは、1853年、4隻の巨大軍艦を率いて神奈川県の浦賀に来航しました。これらの船が黒かったことから「黒船」と呼ばれています。
幕府の役人は長崎に行くよう求めましたが、ペリーは聞く耳を持たず浦賀にとどまり、日本の開国を求める大統領の国書を幕府に受け取らせました。
翌年に回答することを約束した幕府は、国内の意見をまとめるため先例を破って大名の意見を聞き、朝廷にも報告しました。これをきっかけに朝廷や大名の発言権が強まることになりました。
1853年約束に基づいて再び来航したペリーの軍事的な圧力に屈して、幕府は、日米和親条約(にちべいわしんじょうやく)を結びました。
内容は、静岡県の下田と北海道の函館の2港を開き、アメリカの領事を下田に置くことと、アメリカ船に食料や水、石炭などを供給することを認めました。
こうして長い間続いた鎖国政策はくずれ、開国への道を歩み出しました。
不平等な通商条約
1856年アメリカ総領事ハリスは、開港された下田に来航し、幕府に通商条約を結ぶことを強く求めました。
幕府は、外国との戦争をさけるため、ハリスと交渉して条約案を作成し、朝廷に許可を求めました。しかし、朝廷は、外国との関係を結ぶことを嫌い、条約を結ぶことを認めませんでした。
新しく大老になった彦根(ひこね)<滋賀県>藩主の井伊直弼(いいなおすけ)は、1858年に清がアヘン戦争の敗戦に続き、太平天国の乱に伴う外国軍の仲介でも再びイギリス・フランス連合軍に負けたことを知り、朝廷の許可を得ないで、日米修好通商条約(にちべいしゅうこうつうしょうじょうやく)を締結しました。
日米修好通商条約によって、函館・神奈川・長崎・新潟・兵庫の5港を開港し、開港地に設けた居留地でアメリカ人が自由な貿易を行えるようになりました。
また、幕府との連絡や交渉を行う公使を江戸に置くことも認めました。
条約は、清がイギリスと結んだものと同様にアメリカに領事裁判権(りょうじさいばんけん)を認め、日本の関税自主権(かんぜいじしゅけん)がないなど、日本にとって不利な内容をふくむ不平等条約でした。
次いで幕府は、オランダ、ロシア、イギリス、フランスとも、ほぼ同じ内容の不平等条約を結ぶことになりました。この条約を安政の五か国条約といいます。
これ以後、各国の公使が江戸に着任し、それぞれの開港地では外国人との貿易が始まりました。
尊王攘夷運動と開国の影響
尊王攘夷運動の高まり
幕府が外国の圧力に負け、朝廷の許可を得ずに通商条約を結んだことから、天皇を尊ぶ尊王(そんのう)論や外国の勢力を排除しようとする攘夷(じょうい)論が日本国内で高まりました。
尊王論と攘夷論とは結び付き、幕府の政策に反対する尊王攘夷運動(そんのうじょういうんどう)が盛んになりました。
大老・井伊直弼(いいなおすけ)は、1858年から1859年にかけて実施された安政の大獄(あんせいのたいごく)という弾圧にて幕府の政策に反対する大名、公家、尊王攘夷派の藩士を処罰し、これをおさえようとしました。
この安政の大獄では、長州藩士出身の指導者で私塾「松下村塾」にて、のちの明治維新で重要な働きをする多くの若者に思想的影響をあたえた吉田松陰(よしだしょういん)も、幕府の対外政策を批判したことで、江戸で処刑されました。
しかし翌1860年 、井伊直弼は、桜田門外の変という襲撃事件で反発を強めていた水戸藩の元藩士たちに暗殺されてしまいました。
そのため幕府は、尊王攘夷運動を逆に認め、朝廷との結び付きを強めることによって権威を取りもどそうとする公武合体策(こうぶがったいさく)に転換し、天皇の妹を14代将軍徳川家茂(とくがわいえもち)の夫人にむかえました。
開国の経済的影響
外国との自由な貿易の開始によって、日本の経済は大きな変化と影響を受けました。
外国からは、毛織物・綿織物・武器・艦船(かんせん)などが輸入され、日本からは、生糸(きいと)・茶などが輸出されました。最大の貿易港は横浜で、相手国はイギリスが中心でした。
開国した当初、外国との金銀の交換比率の違いから、金貨<小判>が大量に国外に持ち出されました。
幕府は、これを防ぐため、改鋳(かいちゅう)によって小判の質を落として金の流出を防ぎましたが、物価は急速に上昇し、菜種油(なたねあぶら)などの輸出品だけでなく、生活必需品が不足して値上がりしてしまいました。
貿易は、これまでの日本の伝統産業にも大きな影響をあたえました。
生糸は、貿易商人に買いしめられ、大きく値上がりし、このため東日本を中心に、生糸の生産が盛んになりました。
イギリス産の安くて良質な綿織物や綿糸の輸入は、国内の生産地や綿織物経営に打撃をあたえましたが、綿織物業者の中には、輸入した安い綿糸を使って、逆に輸入綿織物に対抗する者も現れました。
世直し一揆と「ええじゃないか」
外国との貿易や貨幣の改鋳(かいちゅう)によって米や生活用品が値上がりしたため、生活に行きづまる民衆が増え、幕府への不満は高まっていくようになりました。
民衆は、借金の帳消しや売りわたした耕地の返還、生活用品の値下げなどの「世直し」を求め、江戸や大阪周辺では大規模な世直し一揆や打ちこわしが起こりました。
また「ええじゃないか」といって人々が熱狂する騒ぎが各地で流行しました。
その目的は定かではないようですが、「ええじゃないか」の囃子言葉(はやしことば)と共に政治情勢が歌われたことから、世直しを訴える民衆運動であったと一般的には解釈されています。
これに対し、倒幕派が国内を混乱させるために引き起こした陽動作戦だったという噂を紹介するものもありよくわかっていません。
結果、このような民衆の動きが、幕府の権威を低下させることにつながっていきました。
江戸幕府の滅亡
倒幕(とうばく)への動き
1863年に、尊王攘夷運動(そんのうじょういうんどう)の中心であった長州藩<山口県を中心とした地域>が朝廷を動かして、幕府に攘夷の実行を約束させました。
攘夷とは、少し前にでてきましたが、外国の勢力を排除しようとする考え方でしたよね。
そして同年、長州藩は、自らが進んで関門海峡(かんもんかいきょう)を通る外国船を砲撃し、海峡を封鎖しました。
攘夷運動の高まりをおそれた幕府は、朝廷の支持を取り付け、京都から攘夷を主張する公家(くげ)や長州藩士を追放しました。
1864年、長州藩は、京都での主導権を取りもどすため、京都を攻めましたが、御所(ごしょ)を守る会津藩・薩摩藩などと戦って敗れました。
ちなみに池田屋事件で有名になった近藤勇や沖田総司を中心とした新撰組(しんせんぐみ)はこの時の話です。
舞台となった事件後の池田屋は、尊王攘夷派志士をかくまっていたとして、池田屋主人の池田屋惣兵衛が捕縛され獄死。池田屋も7か月間の営業停止となり、その後、親類により近在で営業を再開したが、のちに廃業し、現存しないようです。
幕府は、その後も諸藩に命じて長州藩に出兵して、幕府に従わせました。
同じ時期、イギリス・フランス・アメリカ・オランダ4国の艦隊は、連合して長州藩に報復の攻撃を行い、下関砲台を占領しました。
欧米の軍事力を実感した長州藩の木戸孝允(きどたかよし)などは、列強に対抗できる強い統一国家を造るため、幕府を倒そうと考えるようになりました。
幕府に従う姿勢を見せていた長州藩では、下関で長州藩士の高杉晋作(たかすぎしんさく)が兵を挙げ、木戸孝允とともに長州藩の実権をにぎりました。
薩摩藩でも、生麦(なまむぎ)事件の報復のため起こった薩英(さつえい)戦争でイギリス艦隊に鹿児島を攻撃されると、西郷隆盛(さいごうたかもり)や大久保利通(おおくぼとしみち)が実権をにぎり、イギリスに接近して軍備を強化しました。
1866年、土佐藩<高知県>出身の坂本龍馬(さかもとりょうま)は、薩摩藩と長州藩の間を仲介し、薩長同盟(さっちょうどうめい)を結ばせました。
同年、幕府は再び長州藩を攻めましたが、出兵した幕府側藩の戦意は低く、各地で敗れた幕府は、将軍徳川家茂(とくがわいえもち)の死を理由に停戦しました。
こうしていよいよ260年余りも続いた江戸幕府滅亡へのカウントダウンが始まっていきました。
大政奉還と王政復古
第15代将軍となった徳川慶喜(とくがわよしのぶ)は、土佐藩のすすめで政権を朝廷に返す大政奉還(たいせいほうかん)を行い、1867年、幕府はほろびました。
慶喜は、幕府にかわる新政権の中で主導権をにぎろうとしましたが、同年、西郷隆盛や公家の岩倉具視(いわくらともみ)などが、朝廷を動かして王政復古の大号令(おうせいふっこのだいごうれい)を出し、天皇を中心とする政治にもどすことを宣言しました。
また、徳川家の政治的な影響力を除くため、慶喜に官職や領地の返上を命じました。
1868年、これに不満を持つ旧幕府軍と新政府軍との間で鳥羽(とば)・伏見(ふしみ)の戦い<京都市>が起こり、新政府軍が勝利しました。
新政府は、西郷隆盛と旧幕府軍の勝海舟(かつかいしゅう)の会談により江戸城をあけわたさせ、その後も軍を進めて、翌年には函館<北海道>の五稜郭(ごりょうかく)で旧幕府軍を最終的に降伏させ、国内を平定しました。
こうした旧幕府軍と新政府軍との戦いを戊辰戦争(ぼしんせんそう)といいます。
さあ、次回はいよいよ明治維新と近代国家日本の始まりです。
★開国と近代日本の歩み★
②明治維新
新政府の成立
明治維新
ペリー来航以降、日本社会は大きく変化し始め、さらに江戸幕府を倒して成立した新政府も、欧米諸国をモデルにして、さまざまな改革を進めました。
明治維新(めいじいしん)といい、江戸時代の幕藩(ばくはん)体制の国家から近代国家へかわっていく際の、政治・経済・社会の一連の変革をいいます。
1868年3月 新政府は、新しい政治の方針として五箇条の御誓文(ごかじょうのごせいもん)を宣言し、全ての政治は人々の話し合いによって決めること、知識を世界に求めて天皇の統治の基礎をふるい起こすことなどが、定められました。
続いて、江戸を東京に改称(かいしょう)し、年号を慶応から明治に改めました。人々は、新しい政治を「御一新(ごいっしん)」と呼んで期待したようです。
藩(はん)から県へ
新政府の大きな課題は、中央政府が地方を直接治める中央集権国家を造り上げることでした。
幕府はなくなりましたが、大名を領主とする藩はまだ残っていました。
新政府は、1869(明治2)年、版籍奉還(はんせきほうかん)を行い、藩主に土地<版(はん)>と人民<籍(せき)>を政府に返させました。
しかし藩の政治は元の藩主がそのまま担当したので、改革の効果はあまり上がらなかったようです。また新政府は限られた直接の支配地から厳しく年貢を取り立てたため、人々の不満は増し、一揆が頻繁に起こるようになりました。
そこで新政府は、1871年に廃藩置県(はいはんちけん)を行いました。
廃藩置県とは、藩を廃止(はいし)して県を置き、各県には県令(けんれい)<後の県知事>を、東京、大阪、京都の3府には府知事を中央から派遣して治めさせました。
同時に中央政府では、倒幕の中心勢力であった、薩摩・長州・土佐・肥前の4藩の出身者や少数の公家が政府の実権をにぎるようになりました。
このため、後に藩閥政府(はんばつせいふ)と呼ばれるようになります。
閥(ばつ)とは、出身や利害などを同じくする者が結成する排他的な集まりのことで、ここでは少数の出身藩などが、新政府の要職をほぼ独占していたという批判的なニュアンスが込められています。
身分制度の廃止
新政府は天皇の下に国民を一つにまとめようと、皇族以外は全て平等であるとし、また移転や職業選択・商業の自由を認めました。
平民も名字(みょうじ)を名乗り、華族(かぞく)や士族と結婚することが認められました。士族は、その後、帯刀が禁止されました。
1871年には、「解放令(かいほうれい)」も布告されました。
これまで、えた身分やひにん身分として差別されてきた人々に関して、呼び名を廃止し、身分や職業も平等とするという内容です。
しかし実際には、残念ながら、職業・結婚・住む場所などの面で差別は根強く続いたようです。これに対して、「解放令」をよりどころにしながら、差別からの解放と生活の向上を求める動きが各地で起こるようになりました。
明治維新の三大改革
三大改革
新政府は、廃藩置県によって中央集権国家の基礎を築いたうえで、欧米諸国にならった近代化のためのさまざまな改革をさらに推し進めました。
特に、三大改革である「学制」「兵制」「税制」の三つの改革は、近代化政策の基礎となり、国民の生活にも多大な影響をあたえました。
学制の公布
三大改革の一つ「学制」についてみていきます。
1872(明治5)年に、新政府は、学制を公布しました。

学制とは、小学校から大学校までの学校制度を定めたものです。特に小学校での教育が重視され、満6歳になった男女を全て通わせることが義務になり、全国各地で小学校が建設されました。
授業料は、家庭の負担だったようで、初めは入学する児童はそれほど多くなかったようです。
また、学校の建設費も地元の人々が負担したため、小学校が不満の対象になることもありましたが、1876年に長野県松本市に建てられた旧開智(かいち)学校のように地元の人々が資金を出し合って立派な校舎を建てることもありました。
政府は、さらに東京大学をはじめとする各種の高等教育機関を作り、教師としてお雇い外国人を採用するとともに、多くの日本人留学生を欧米に派遣して、欧米の新しい科学や技術を取り入れることに努力しました。
徴兵令(ちょうへいれい)
三大改革の一つ「兵制」についてみていきます。
政府は、江戸時代までは武士という身分に限られていましたが、国民を兵とする統一的な軍隊を新たに創ろうとしました。
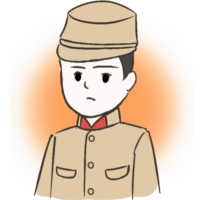
1873年に徴兵令(ちょうへいれい)が出され、満20歳になった男子は、士族と平民の区別なく兵役の義務を負うことになりました。
しかし、兵になる義務を新たに負った農民が、徴兵反対の一揆を起こすこともあったようです。
また、最初は多くの免除規定があったため、実際に兵役に就いたのは、免除規定に当てはまらない平民の二男、三男たちがほとんどでした。
尚、1889年には、それまでの免除規定が廃止され、「国民皆兵(かいへい)」が制度的に確立されました。
地租(ちそ)改正
三大改革の一つ「税制」についてみていきます。
新政府にとって、税制を整えて国家の財政を安定させることも重要な課題でした。
政府は、まずは国民に土地の所有権を認めたうえで、1873年より地租改正(ちそかいせい)を実施しました。
地租改正の中身は、
①土地の所有者と価格(地価)を定め、地券を発行する、
②収穫高ではなく、地価を基準にして税をかける
③税率は地価の3%とし、土地の所有者が現金で納める
などでした。
地租<土地にかかる税>は全国統一の税になり、国家の歳入<年間の収入>の大半をしめ、財政を安定させました。
しかし政府は、江戸時代の年貢から収入を減らさない方針を採ったので、税の負担はほとんど変わらず、各地で地租改正反対の一揆が起こるようになりました。
このため政府は、1877年に地租を地価の3%から2.5%に引き下げ歩みよりました。
富国強兵と文明開化
富国強兵
富国強兵(ふこくきょうへい)とは、欧米諸国に対抗するため、経済を発展させて国力をつけ、軍隊を強くすることを目指す新しい国づくりのための政策です。
具体的に政府は「強兵」を実現するため、徴兵制により軍隊を創る一方で、「富国」を実現するため殖産興業(しょくさんこうぎょう)政策を進め、産業を育てることで経済の資本主義化を図りました。
殖産興業政策
「富国」を実現するための殖産興業(しょくさんこうぎょう)とは、一般的には、明治政府が西洋諸国に対抗し、鉄道網整備、機械制工業、資本主義育成により国家の近代化を推進した諸政策を指します。
狭義では明治政府による新産業の育成政策を指すようです。
明治政府は、経済の発展の基礎になる社会インフラとして、交通や通信の整備を進めました。
1872(明治5)年に新橋・横浜間に鉄道が開通し、その後、神戸・大阪間、大阪・京都間、小樽・札幌間など、主要な港と大都市とを結ぶ鉄道が次々開通しました。
沿岸では蒸気船の運航も始まるようになりました。
通信では、江戸時代に活躍した飛脚(ひきゃく)にかわる郵便制度や電信網が新たに整えられました。
また、日本の輸出の中心であった生糸の増産や品質の向上を図るため、群馬県の富岡製糸場(とみおかせいしじょう)などの官営模範工場(かんえいもはんこうじょう)を造りました。
そして、外国の優れた新しい技術を各地に広めました。
尚、今現在、富岡製糸場は、「フランスの器械製糸技術を導入した日本初の本格的製糸工場」「和洋技術を混交した工場建築の代表」ということのほか、製糸・養蚕技術の発展への貢献などの理由で、2014年に世界遺産にも登録され世界的な観光名所の一つになっています。
また、富岡製糸場を建設した中心人物は、近代日本の創造者ともよばれている渋沢栄一(しぶさわえいいち)という人物です。
渋沢栄一は、2024年上半期(4月~9月)をめどに発行される新1万円札の肖像として採用される予定ですが、富岡製糸場の建設をはじめ日本初の公的な証券取引機関である、東京株式取引所(現在の東京証券取引所)や多くの企業を設立し、日本経済の発展に力をつくしたと言われています。
文明開化
文明開化(ぶんめいかいか)とは、近代化を目指す政策を進めるうえで、その土台になる欧米の文化も盛んに取り入れ、都市を中心に伝統的な生活が変化し始めた現象を言います。
文明開化によって、日本人の衣食住は、次第に欧米風に変化していきました。
文明開化は、開港して海外との交通の窓口になった、横浜や神戸などの外国人居留地から広がっていきました。
具体的には、役所や学校をはじめ、れんが造りなどの欧米風の建物が増えて、道路には馬車が走り、ランプやガス灯がつけられるように変化しました。
洋服やコート、帽子が流行し、牛肉を食べることが広がるなど、衣服や食生活の変化も始まりました。
暦(こよみ)も、それまでのものにかわって欧米と同じ太陽暦(たいようれき)が採用され、1日を24時間、1週間を7日とすることになりました。こうした新しい制度や文化は、役所や学校、工場、軍隊などを通じて、次第(しだい)に人々の間に広まっていきました。
ちなみにハイカラは文明開化の時代や明治時代に流行した言葉ですが、語源は「high collar(=高い丈の襟)」からきていて、欧米から帰国した人もしくは欧米風の文化を好む人が高い丈の襟のシャツを着ていたことに由来すると言われています。
新しい思想
明治時代になると文明開化の中で新しい思想も広がっていきました。欧米の近代化を生み出した自由や平等などの思想です。
具体的な代表例をイメージするとわかりやすいと思いますが、慶應義塾大学の創設者であり、現在の一万円紙幣の表面の肖像に採用されている福沢諭吉(ふくざわゆきち)の「学問のすすめ」の中には、「天は人の上に人をつくらず、人の下に人をつくらず」という言葉があり、社会に自由や平等などの新しい思想の広がりに対し、強い影響を与えました。
また、中江兆民(なかえちょうみん)は、自由民権運動の理論的指導者であり、第1回衆議院議員総選挙における当選者の一人です。
「東洋のルソー」とも呼ばれ、フランスの啓蒙思想家ルソーの思想を日本へ紹介し、青年に大きな影響をあたえたと言われています。
明治時代はキリスト教の信仰も事実上黙認され、次第に広まっていきました。
またこうした新しい思想の社会への広がりを後押ししたものは、活版印刷技術の発展もあります。日刊新聞や雑誌が発行されるようになり、大きな役割を果たしました。
近代的な国際関係
ぶつかる二つの国際関係
近代的な欧米諸国での国際関係は、条約に基づいた関係でした。
それまで、アジアの国際関係は、中国の皇帝に周辺諸国が朝貢(ちょうこう)し、支配者としての地位を認められるという関係でした。
欧米諸国は、中国などのアジア諸国に対し、近代的な国際関係を結ぶよう求めてきました。
ただし、欧米諸国どうしは対等な関係を結んでいましたが、19世紀にアジア諸国と結んだ関係は、植民地にしたり、個別に不平等条約を結んだりすることで、欧米諸国が優位に立つ不平等関係<対等でない関係>でした。
日本も、ほかのアジア諸国と同様に、欧米諸国と不平等条約<日米修好通商条約や安政の五か国条約など>を結んでいました。
しかし、アジア諸国の中ではいち早く、そうした不平等条約を改正して対等な関係を築こうとする一方で、朝鮮などのアジア諸国に対しては、不平等な関係を結ぼうとしました。
岩倉使節団
幕末に欧米諸国と結んだ不平等条約<日米修好通商条約や安政の五か国条約など>の改正は、新明治政府にとって大きな課題でした。
政府は、廃藩置県(はいはんちけん)の直後、岩倉具視(いわくらともみ)を全権大使とする使節団を欧米に派遣しました。
この岩倉使節団(いわくらしせつだん)は、木戸孝允、大久保利通、伊藤博文など、政府有力者の約半分が参加するなど大規模に行われました。
残念ながら、法の整備など近代化政策がまだ不十分だったこともあって、当初の目的であった不平等条約の改正交渉は不成功に終わりました。
そうした中で、岩倉使節団は欧米の政治・産業、社会状況の視察に重点を移し、2年近く欧米を回ったようです。
近代化を目指すには、国力の充実が必要であると痛感して帰国した使節団は、こうした経験を基に日本の近代化を推進していくようになります。
清や朝鮮との関係
明治時代の新政府は、朝鮮に新しく国交を結ぶよう求めました。しかし、朝鮮はこれまでの慣例と異なるとして断ります。
新政府は、1871<明治4>年、朝鮮の朝貢先である清と対等な内容の条約・日清修好条規(にっしんしゅうこうじょうき)を結ぶことで、朝鮮との交渉を進めようとしましたが、やはりうまくいきませんでした。
こうした中、政府内には征韓論(せいかんろん)という考えが高まります。征韓論とは、話し合いでなく武力で朝鮮に開国をせまる考え方です。
1873年<明治6>年、使節として西郷隆盛を朝鮮に派遣することがいったん決定されましたが、岩倉使節団に参加し国力の充実が先だと考えて大久保利通などは朝鮮への派遣を延期させました。
その結果、政府は分裂し、西郷隆盛や板垣退助などは政府を去りました。こうした政府内の分裂は、征韓論政変と呼ばれ、後の政府への反乱につながっていきます。
その後も、日本は朝鮮と国交を結ぶ交渉を続けましたが、うまくいきませんでした。
日本政府は1875年の江華島(こうかとうorカンファド)事件を口実に、翌年朝鮮と日朝修好条規(にっちょうしゅうこうじょうき)を結び、朝鮮を力で開国させました。
条約の内容は、日本が欧米諸国からおし付けられた不平等条約を、そのまま朝鮮に当てはめるようなもので、日本のみが領事裁判権を持つなど不平等なものだったようです。
国境と領土の確定
樺太・千島交換条約
欧米の近代的な国際関係では、国境線ははっきり引かれていましたが、アジアの伝統的な国際関係では、国境線はあいまいなままでした。
日本は、アジア諸国の中でいち早く近代的な国際関係を目指していたため、国境線や領土を確定させることは重要な課題となっていました。
幕末に日本がロシアと結んだ日露和親条約では、樺太(からふと)<サハリン>はどちらの領土であるかあいまいなままでした。
そこで1875(明治8)年 に政府はロシアと、樺太・千島交換条約を結びました。
ロシアに樺太の領有を認める一方、千島(ちしま)列島の全てを日本の領土にすることで、両国の国境を明確に定めました。
また、太平洋地域では、いくつかの国が小笠原諸島の領有権を主張していましたが、1876年に日本の領有を確定させました。
北海道の開拓とアイヌの人々
ロシアと国境問題をかかえていた政府は、蝦夷地(えぞち)の開拓を進めました。 政府は蝦夷地を北海道に改めます。
北海道に開拓使という役所を置いて統治を強化するとともに、農地の開墾(かいこん)、鉄道や道路の建設など、欧米の技術を取り入れた開拓事業を行いました。
この時、開拓の中心になったのは、屯田兵(とんでんへい)と呼ばれる人々でした。
屯田兵は、初めは生活が苦しくなった士族が中心でしたが、やがて平民にも広がり、各地から移民団が北海道にわたりました。
なお、屯田兵とは、もともと中国の制度に由来し、兵士を遠隔地へ派遣し、平常は農業を営むかたわら軍事訓練を行い、いざ戦争が始まったときには軍隊の組織として戦うことを目的とした土着兵のことをいうようです。
開拓が進むにつれて、先住民のアイヌの人々は土地や漁業をうばわれるようになります。
さらには、アイヌ民族の伝統的な風習や文化などを否定する同化政策が進められるようになりました。ちなみに同化政策とは、自国の人々と同化させようとする政策です。
沖縄県の設置と琉球の人々
琉球王国は、薩摩藩に事実上支配されながら、清にも朝貢(ちょうこう)するなど、日清の両方に属する関係を結んでいました。
1872年に日本政府は琉球王国を琉球藩としました。
さらに1879年、日本政府は軍隊の力を背景に、琉球の人々の反対をおさえ、琉球藩を廃止して沖縄県を設置しました。
琉球処分(りゅうきゅうしょぶん)と呼ばれ、明治政府が琉球王国を日本近代国家に組み入れた政治過程をさします。明治政府自身が「処分」といっているように,一方的に強権をもって断行したものであったようです。
清は朝貢していた国を失ったことで、日本に強く抗議しました。この琉球処分をめぐる日清間の対立は、日清戦争で台湾が清から日本へゆずりわたされることで自然消滅するまで続いたようです。
琉球処分で沖縄は日本領に編入されました。
また、それまでの土地制度や租税制度など古い慣行はしばらく維持されました。
しかし、沖縄の人々に対しても、アイヌの人々と同じように徐々に本土の風習や文化にあわせさせる同化政策が採られるようになっていきました。
自由民権運動の高まり
自由民権運動と士族の反乱
征韓論(せいかんろん)政変の後、大久保利通が明治政府の中心人物となります。
大久保利通は、西郷隆盛、木戸孝允と並んで「維新の三傑」とも称されていて、後の内閣制度発足前のリーダーとなります。
大久保は、新たに内務省を設置して内務卿(ないむきょう)になりました。内務省は、警察や地方自治、さらに殖産興業に関する政策を進めました。
征韓論政変にて政府を去った板垣退助(いたがきたいすけ)や江藤新平(えとうしんぺい)などは、1874(明治7)年、民撰議院設立の建白書(みんせんぎいんせつりつのけんぱくしょ)を政府に提出します。
板垣などは大久保の政治を専制政治であると非難し、議会の開設を主張しました。これが、国民が政治に参加する権利の確立を目指す自由民権運動(じゆうみんけんうんどう)の出発点となります。
この後、板垣は高知で立志社(りっししゃ)を結成し、運動を進めていきました。
一方、この自由民権運動と重なりながら展開したのが、士族の反乱でした。
改革で特権を奪われたことに不満を持つ「不平士族」たちも、大久保の政治への非難を強め、西日本を中心に各地で反乱を起こしました。
なかでも1877年に征韓論政変にて板垣と同じく政界を去っていた西郷隆盛を中心として鹿児島の士族などが起こした西南戦争は最も大規模なものでしたが、近代的装備化された政府軍によって鎮圧(ちんあつ)されました。
西郷隆盛も、最後は鹿児島の城山に立てこもって戦いここで自害しました。また、大久保利通も西南戦争の翌年1878年に東京で暗殺されてしまいました。
高まる自由民権運動
西南戦争後、旧薩摩、長州藩出身者などからなる藩閥(はんばつ)政府への批判は言論によるものが中心になりました。
政府は「新聞紙条例」や「集会条例」を出して、自由民権運動の集会や言論に対して介入、弾圧しました。
1878年に地方制度が大きく改革され、府や県にも議会が作られるようになります。
地主や商工業者などが議員になることで、政治への参加意識が高まっていきました。
1880年には、全国の代表者が大阪に集まって、国会期成同盟(こっかいきせいどうめい)を結成しました。国会期成同盟は、国会の開設を求める政治結社です。
この運動は、自主的に憲法草案を作成する方向へと進み、多くの草案が民間で作成されました。
植木枝盛(うえきえもり)や中江兆民(なかえちょうみん)は欧米の思想を基に民権論を主張し、自由民権運動に大きな影響をあたえました。
ちなみに植木枝盛が作成した私擬憲法「東洋大日本国国憲按」は、最も民主的・急進的なとして知られ、時代を超え第二次世界大戦後に制定された現行日本国憲法制定時にも参考にされた間接的な源流憲法としての評価も高いようです。
国会の開設をめぐる対立
国会の開設や憲法を求める運動の高まりに対して政府では、国会と憲法の内容や、開設、制定の時期について意見が分かれます。
大隈重信(おおくましげのぶ)は、国会の早期開設などの急進的な主張をしました。
こうした中、1881年に北海道の開拓使(かいたくし)の施設や財産を関係者に安く売りわたそうとする事件が起こり、民権派は政府を激しく攻撃しました。
伊藤博文(いとうひろふみ)などは、民権派との結び付きが強い大隈が背後にいると考え、大隈を政府から追い出すとともに、10年後に国会を開くことを約束しました。
これを「国会開設の勅諭(ちょくゆ)」といいます。
この後、自由民権運動は、国会開設に備えて政党の結成へと進みます。
板垣を党首とする自由党が結成され、政府から追い出された大隈を党首にして立憲改進党(りっけんかいしんとう)も結成されました。
余談ですが、大隈重信は、早稲田大学の創設者で、初代総長も勤めました。
立憲制国家の成立
憲法の準備
政党の結成に進んだ自由民権運動も、政府の弾圧や、東日本の各地で民権派の関係する激化(げきか)事件が起こったことで、活動はほとんど休止状態になりました。
激化事件とは、不況に対する農民たちの不満から、 農民たちが政府に抗議するために日本各地起こした暴動事件の総称です。
福島事件、加波山(かばさん)事件、秩父(ちちぶ)事件、大阪事件などいろいろ事件が起きました。
一方、国会を開設する前に政府が行う必要がある最大の仕事は、憲法の制定です。
伊藤博文は自らヨーロッパへ調査に行き、ドイツやオーストラリアなどのヨーロッパ各地での憲法について学びました。
日本に戻ってからは憲法制定の準備を進め、1885(明治18)年に内閣制度(ないかくせいど)を定めます。
伊藤は自ら初代の内閣総理大臣に就任しました。
また、伊藤が中心になって憲法の草案を作成し、審議(しんぎ)を進めました。
立憲制国家の成立
大日本帝国憲法は、1889年2月11日、天皇が国民にあたえるという形で発布されました。
この憲法では、天皇が国の元首として統治すると定められました。
天皇の権限として、帝国議会の召集・衆議院の解散・陸海軍の指揮・条約の締結・戦争の開始/終了などが明記されました。
内閣については、大臣は、議会ではなく天皇に対して、個々に責任を負うとされました。
議会は、衆議院と貴族院の二院制でした。
衆議院は、国民が選挙した議員で構成され、貴族院は、皇族や華族、天皇が任命した議員などで構成されました。
議会の権限にはさまざまな制限がありましたが、予算や法律の成立には議会の同意が必要だったので、内閣は政策を進めていくうえで、議会の協力を必要としました。
国民は「臣民」とされ、議会で定める法律の範囲内で言論・出版・集会・結社・信仰の自由などの権利が認められました。
憲法に続いて、民法や商法なども公布され、法制度が整備されました。
憲法発布の翌1890年には教育勅語(きょういくちょくご)も出されました。
道徳の根本、教育の基本理念を教え諭すという建前で出された勅語<天皇が直接国民に発する言葉>で、戦前までは国民の精神的なよりどころとされました。
帝国議会の開設
2016年に、18歳以上に引き下げられている選挙権ですが、最初の選挙ではまだまだ制約が結構ありました。
衆議院議員の選挙権があたえられたのは、直接国税を15円以上納める満25歳以上の男子のみだったようで、有権者は総人口の1.1%(約45万人)しかいなかったようです。
いろいろ制約はありましたが、まずは1890年に帝国議会が開かれ、特に衆議院においては、国民が国家の政治に参加する道が開かれるようになりました。
そして最初の衆議院議員選挙では、自由民権運動の流れをくむ政党(民党)の議員が多数をしめるようになりました。
こうして議会政治が始まり、日本はアジアで最初の近代的な立憲制国家の道を歩むことになりました。
★開国と近代日本の歩み★
③日清・日露戦争と近代産業
欧米列強の侵略と条約改正
列強と帝国主義
19世紀後半、欧米諸国では資本主義が急速に発展し、製鉄や機械、鉄道などの産業が成長し、その中で力をつけた資本家が経済を支配するようになりました。
資本主義の発展とともに、欧米列強にはイギリス、アメリカのほかにフランスやドイツ、ロシアなどが加わりました。
これら欧米列強は、資源や市場を求めてアジアやアフリカ、さらには太平洋の島々へと進出していき、軍事力によりこれらの地域のほとんどを植民地としていきました。
こうして、世界の広い範囲は欧米列強によって分割されました。
このような動きを帝国主義といいます。
尚、帝国主義とは、一つの国家または民族が自国の利益・領土・勢力の拡大を目指して、政治的・経済的・軍事的に他国や他民族を侵略・支配・抑圧し、強大な国家をつくろうとする運動・思想・政策のことをいいます。
条約改正の実現
国際的に欧米列強と対等な地位を得るために、日本では、幕末に結んだ不平等条約の改正が最も重要な課題でした。
それを実現するため欧米的な法律の制定など近代化政策を推し進めました。
アメリカは、条約改正にいち早く応じて、1878(明治11)年に関税自主権の回復で合意はしましたが、イギリスなどが反対し実現はされませんでした。
その後、外務卿(きょう)<大臣>であった井上馨(いのうえかおる)は、鹿鳴館(ろくめいかん)で舞踏会(ぶとうかい)を開くなどの欧化政策(おうかせいさく)を採りながら、条約改正交渉に臨みました。
井上や、続いて外務大臣になった大隈重信(おおくましげのぶ)による交渉では、領事裁判権撤廃のかわりに、外国人を裁く裁判に外国人裁判官を参加させるという条件が出され、国内からの激しい反対で失敗してしまいました。
イギリスも条約改正には最も後ろ向きでしたが、大日本帝国憲法の発布やノルマントン号事件などの世論の反発を受けて、徐々に交渉に応じるようになりました。
日清戦争直前となる1894年には、陸奥宗光(むつむねみつ)外相は日英通商航海条約を結び、領事裁判権の撤廃に成功しました。そしてほかの欧米列強とも、同様の改正が実現しました。
東アジアの情勢
明治の頃、朝鮮半島では、日本と清の勢力争いが広がっていました。
日本は、日朝修好条規を結ぶことで朝鮮に清との朝貢関係を断ち切らせたと考えていました。
逆に、清は朝鮮に対する影響力を欧米諸国と植民地との関係のように強化しようとしていました。
1880年代後半以降、朝鮮では日本の勢力が後退する一方、清の勢力が強くなると、日本は清に対抗するため、軍備の増強を図っていきました。
さらに、ロシアのシベリア鉄道建設など、欧米列強の東アジア進出に対抗して、日本も朝鮮に進出しなければ危険であるという主張が、日本国内で強まってきました。
日清戦争
日清戦争
1894(明治27)年、朝鮮で、甲午農民戦争(こうごのうみんせんそう)が起きました。
甲午農民戦争とは、民間信仰を基にした宗教である東学(とうがく)を信仰する団体が組織した農民が、朝鮮半島南部一帯で反乱をいいます。
関与者に東学の信者がいたことから東学党の乱とも呼ばれています。
農民軍は、腐敗した役人の追放といった政治改革や、日本や欧米など外国人の排除を目指しました。
甲午農民戦争/東学党の乱の鎮圧のため、朝鮮の政府が清に出兵を求めたことに対抗して、日本も朝鮮に出兵しました。
日本と清の軍隊が衝突し、1894年8月、日清戦争に発展しました。
日本は戦いを優勢に進め、1895年4月、下関条約が結ばれました。
この講和条約で清は、①朝鮮の独立を認め、②遼東(りょうとうorリアオトン)半島、台湾、澎湖(ほうこorホンフー)諸島を日本にゆずりわたし、③賠償金(ばいしょうきん)2億両(テール:当時の日本円で約3億1000万円)を支払うことなどが定められました。
日本は、領有した台湾の住民抵抗を武力でおさえ、強い権限を持つ台湾総督府(そうとくふ)を設置して、植民地支配を進めていきました。
三国干渉と加速する中国侵略
日清戦争で下関条約が結ばれた直後に、ロシアはドイツやフランスとともに、日本が獲得した遼東半島を清に返還するよう勧告してきました。
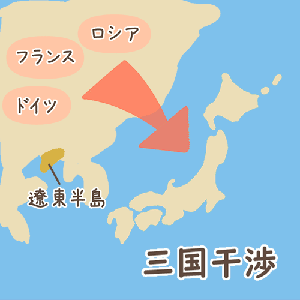
三国干渉(さんごくかんしょう)といいますが、対抗できる力のなかった日本はこれを受け入れました。
日清戦争での清の敗北によって、古代から続いていた中国を中心とする東アジアの伝統的な国際関係はくずれました。
朝鮮は清からの独立を宣言し、1897年に国名を大韓帝国(だいかんていこく)<韓国>に改めました。
清の弱体化を見た列強は競って、港湾(こうわん)の租借(そしゃく)権や鉄道の敷設(ふせつ)権、鉱山の開発権など、さまざまな利権を清から手に入れて、それぞれ独占的な勢力範囲を作っていきました。
20世紀始めのこの欧米列強と日本の中国侵略の動きを列強の中国分割といいます。
ロシアは、三国干渉後に日本が返還した遼東半島の旅順(りょじゅんorリュイシュン)と大連(だいれんorターリエン)を、ドイツは、山東省の膠州(こうしゅう)湾を、香港を根拠地としていたイギリスは九竜半島や威海衛を、フランスは、広州湾を租借しました。
租借(そしゃく)とは、期限付きで借りるという意味ですが、清の支配がおよばないという点では、領土に近いものでした。
日清戦争後の日本
三国干渉の後、日本国民の間にはロシアへの対抗心が高まりました。
臥薪嘗胆(がしんしょうたん)というロシア対抗のスローガンも唱えられました。
政府も、大規模な軍備の拡張を中心に国力の充実を図りました。
日清戦争で清から得た賠償金も大部分が軍備の拡張や工業化のために使われました。
こうした政策を行うためには、議会で大規模な予算を承認してもらう必要がありました。
藩閥(はんばつ)政府も、それまで対立してきた政党(民党)の協力も得なければならず、政党の力は強まりました。
藩閥の伊藤博文も1900年、自ら立憲政友会(りっけんせいゆうかい)を結成しました。
立憲政友会は、戦前の帝国議会において日本最初の本格的政党内閣を組織した政党で、明治後期から昭和前期の代表的な中心政党となりました。
日露戦争
義和団(ぎわだん)事件
清では、列強の中国進出に反発して、外国の勢力を排除しようとする運動が盛んになりました。
1899(明治32)年に「扶清滅洋(ふしんめつよう)<清を扶(たす)けて外国勢力をうち滅ぼす>」を唱えた義和団の蜂起(ほうき)は、短期間に中国北部一帯に広がりました。
翌1900年、北京にある各国の公使館を包囲し、清政府はこの動きを受けて列強に宣戦布告しました。
1899~1900年の列強の進出に反対した中国民衆の一連の排外運動を義和団事件(ぎわだんじけん)と言いますが、結局、英米仏露日など8ヵ国連合軍が北京を奪回し、義和団を鎮圧しました。
一方、ロシアは満州に出兵し、事件の後も大軍を満州にとどめました。
満州と隣合う勧告を勢力範囲として確保したい日本と、清での利権の確保に日本の軍事力を利用したいイギリスは、1902年に日英同盟を結び、ロシアに対抗しました。
戦争の危機がせまる中で、社会主義者の幸徳秋水(こうとくしゅうすい)やキリスト教徒の内村鑑三(うちむらかんぞう)などは開戦に反対しましたが、ほとんどの新聞は開戦論を主張して世論を動かしました。
政府はロシアとの交渉をあきらめて、1904年2月、ロシアとの開戦にふみ切り、日露戦争が始まりました。
日露戦争
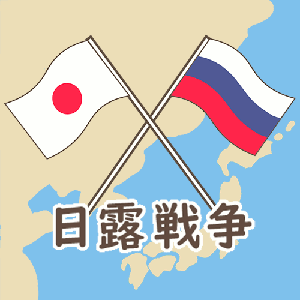
日本軍は苦戦を重ねながらも戦争を進め、イギリスやアメリカも、戦費の調達などの面で日本を支援しました。
しかし日本の戦力は限界に達し、ロシア国内でも専制政治に対する不満から革命運動が起こるなど、両国とも戦争の継続が困難になりました。
1905年5月、日本が日本海海戦で勝利したことを機に、アメリカの仲介によって日本とロシアとの間で講和会議が開かれ、9月にはポーツマス条約が結ばれました。
ポーツマス条約でロシアは、以下の権利を日本に認めました。
①韓国における日本の優越権
②旅順(りょじゅんorリュイシュン)や大連(だいれんorターリエン)の租借(そしゃく)権、長春(ちょうしゅんorチャンチュン)以南の鉄道利権
③北緯50度以南の樺太(からふと)<サハリン>の領有権
④沿海州(えんかいしゅう)・カムチャッカ半島周辺での日本の漁業権
戦争中の増税といった負担や、戦争による犠牲に苦しむ国民は、ロシアから賠償金を得ることを強く求めました。
しかし、ポーツマス条約で賠償金が得られないことが分かると、国民は激しく政府を攻撃し、東京では日比谷焼き打ち事件 のような暴動にまで発展しました。
日露戦争後の日本
日本は、日露戦争での勝利によって、新たな列強として国際的な地位を固めました。
国民の中には、帝国主義国の一員になったという大国意識が生まれ、アジア諸国に対する優越感が強まりました。
一方、日露戦争での日本の勝利は、インドやベトナムなど、欧米列強の植民地であったアジアのさまざまな民族に刺激をあたえ、民族運動は活発化しました。
しかし、日本は新たな帝国主義国としてアジアの民族に接するようになっていくのでした。
韓国と中国
韓国の植民地化
韓国は、日露戦争の最中から、日本による植民地化の圧力にさらされていました。
1905<明治38>年、日本は、韓国の外交権をうばって保護国にし、韓国統監府(とうかんふ)を設置しました。また、初代の統監として伊藤博文が就任しました。
1907年には韓国の皇帝が退位させられて、軍隊も解散させられました。
韓国国内では義兵運動というこうした日本の帝国主義に対する抵抗運動が広がり、日本によって解散させられた兵士たちは農民とともに立ち上がりました。
義兵運動は、日本軍に鎮圧されましたが、日本の支配に対する抵抗はその後も続けられました。
1910年、日本は韓国併合(かんこくへいごう )を行いました。
韓国は「朝鮮」と呼ばれるようになり、首都の「漢城(かんじょう)」<ソウル>も「京城(けいじょう)」と改称されました。
また朝鮮総督府(ちょうせんそうとくふ)を設置して強い権限を持たせました。
武力で民衆の抵抗をおさえ、植民地支配を推し進めました。学校では朝鮮の文化や歴史を教えることを厳しく制限し、日本史や日本語を教え、日本人に同化させる教育を行いました。韓国の植民地支配は1945<昭和20>年の日本の敗戦まで続きました。
満鉄(まんてつ)の設立
日露戦争後、日本は満州の南部を勢力範囲にしていました。
これは、日本軍が日露戦争中に既に占領していたことや、日露戦争の講和条約であるポーツマス条約でもロシアから旅順や大連の租借権などさまざまな権利を獲得できたためです。
日本は半官半民の南満州鉄道株式会社(みなみまんしゅうてつどうかぶしきがいしゃ)<略称は、満鉄>という大日本帝国の特殊会社を設立しました。
鉄道事業を中心に、炭鉱の開発や製鉄所の建設、沿線での都市の建設など広範囲にわたる事業を展開し、日本軍による満州経営の中核となり、満州での利権を独占していくようになりました。
そのような中で日本は、満州への経済進出を進めようとしていたアメリカと、次第に対立するようになっていくのでした。
中華民国(ちゅうかみんこく)の成立
中国では、三民主義を唱えた孫文を中心に、清をたおして漢民族の独立と近代国家の建設を目指す革命運動が盛り上がりました。
孫文の唱えた三民主義とは、「民族の独立(民族主義)・政治的な民主化(民権主義)・民衆の生活の安定(民生主義)」 のことだそうです。
1911年、武昌(ぶしょうorウーチャン) <武漢(ぶかんorウーハン)>で、ある事件が起きます。
そう、コロナウィルス事件・・・ではなく、独立を目指し軍隊が反乱を起こしました。
この武漢発の革命運動が全国に広がり、多くの省が清からの独立を次々宣言していきました。
翌1912年には、各省の代表者からの支持により孫文が革命政府の臨時大統領になりました。
孫文は、アジアで最初の共和国である中華民国を建国し、新たに南京を首都と定めました。
この清でおきた共和革命を辛亥革命(しんがいかくめい)といいます。
辛亥革命の後、清の実力者だった袁世凱(えんせいがいorユアンシーカイ)が、皇帝を退位させ、清は滅亡しました。
ただし、孫文の臨時政府が軍事的に弱体だったこともあり、孫文は袁世凱に臨時大総統の地位をゆずりわたりました。
袁世凱は、首都を南京から北京に移し、革命勢力をおさえて、1915年には自ら皇帝になることを宣言するくらい独裁的な政治を行いました。
ただし、中国国内や当初傍観(ぼうかん)していた日本政府からも反発が強く翌1916年には取り消ししました。
しかし、一度無くなった袁世凱の権威は取り戻すことができず、同1916年6月に失意のうちに病死しました。袁世凱の死後は、中国は軍閥(ぐんばつ)時代に突入します。
ちなみに軍閥時代とは、1916年から1928年にかけて中国が各地に勢力を持つ軍閥によりバラバラに支配される内戦状態となっていた時期をさします。
産業革命の進展
産業の発展
日本における産業革命の時代は、だいたい1880年代後半といわれています。紡績(ぼうせき)、製糸(せいし)などの軽工業を中心に産業が発展しました。
紡績業では大工場が次々に造られて、1890(明治23)年には国産の綿糸生産量が輸入量を上回りました。
また、日清戦争後には輸出量が輸入量を上回りました。綿糸の主な輸出先は朝鮮や中国などのアジア諸国でした。製糸業は、主にアメリカ向けの輸出によって発展し、日露戦争後には世界最大の輸出国になりました。
ちなみに製糸と紡績は、どちらも明治期の主要産業でしたが、製糸は、蚕(かいこ)のまゆを原料に絹糸をつくる、紡績は、綿花を原料に綿糸をつくることだそうです。
工場の機械の動力源である石炭の採掘は、九州北部の筑豊(ちくほう)地域<福岡県>や北海道で進みました。
重化学工業では、日清戦争後に清から得た賠償金を基に官営の八幡製鉄所(やわたせいてつしょ)が建設され、1901年に操業を開始しました。初めは生産量が低い状況が続きましたが、後の重化学工業発展の基礎になっていきました。
また、産業が発展する一方で、日本の公害問題の原点とされている足尾(あしお)銅山鉱毒事件などの社会問題も起こるようになりました。足尾銅山鉱毒事件では、田中正造(しょうぞう)さんという方が活躍します。気になった方は、ぜひ詳しく調べてみてね。
交通の発達
紡績業や製糸業などの産業の発展は、交通機関の発達も大きな影響を与えていました。
鉄道分野では、1889年に官営の東海道線が全線開通しました。
民営鉄道も官営を上回る発展を一時見せましたが、軍事や経済上の必要から、1906年に主要な民営鉄道が国有化されました。
国有化されると国が管理することによって安定して物やサービスが提供されるという利点があります。ただし、競争がなくなるため、サービスなどが向上しないという欠点がでてくることもあります。(JRも昔は国営でしたが、現代では「民営化」されています)
また、陸地だけでなく海外航路の発達も貿易の発展を支えました。
資本家と労働者
資本主義の発展とともに労働者が増加しました。
紡績業や製糸業の労働者は、大半が女子(工女)で、賃金は低く、紡績で1日12時間の昼夜二交替、製糸で14から18時間の厳しい労働をしていたようです。
一方、男子の労働者は、多くが鉱山や運輸業で働いていました。
日清戦争後に労働組合が結成され始め、労働争議という労働条件の改善を求める活動が増加しました。
このため、政府は、集会、結社の自由を制限する一方、1911年に、12歳未満の就業禁止、労働時間の制限などを定めた工場法を制定しました。
しかし、実際にはさまざまな例外規定があり、労働者の置かれた状況は残念ながらなかなか改善しませんでした。
一方、資本家は三井、三菱、住友、安田などの日本の経済を支配する財閥に成長していきました。
産業革命の発展にともない、金融、貿易、鉱業など、さまざまな業種に進出していくようになりました。
地主と小作人
農業においては、都市人口の増加と鉄道などの交通の発達にともない、農作物の商品化が進みました。
また、製糸業の発展で養蚕(ようさん)やくわ(桑)<蚕(かいこ)のえさとなる作物>の栽培が盛んになりました。
資本主義の発展によって、全体的に人々の生活は徐々に豊かになっていきましたが、少しの土地しか持っていない農民や、小作人になった人々においては、子どもを工場に働きに出したり、副業を営んだりしてなんとか生活を続けていた状態でした。
一方、地主は生活が苦しくなった農民から農地を買い集めて経済力をつけたり、株式投資や、新たに企業を作ったりして、資本主義との結び付きをさらに強めていくようになりました。
近代文化の形成
日本の美と欧米の美
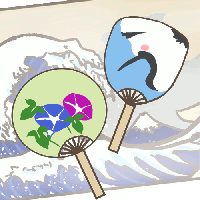
19世紀末、日本の文化面での課題は、欧米式文化を取り入れつつ、いかに日本の新しい文化を創出していくかということでした。
美術では、ジャポニズムという、日本の美術が欧米の美術に影響をあたえたこともありました。
オランダ人画家のゴッホもその一人で、歌川広重(うたがわひろしげ)の浮世絵をまねた油絵を、好んで描いていました。
さらにアメリカ人のフェノロサが岡倉天心(おかくらてんしん)と協力して日本の美術の復興に努めました。ちなみに岡倉天心は、1887年に創立された東京美術学校(現在の東京芸術大学)の事実上の初代校長を務めました。
日本の伝統の価値は、明治維新の時期にいったんは否定されましたが、徐々に見直されるようになりました。
また、欧米の美術の手法を取り入れた近代の日本美術を切り開いた主な人物と代表作は以下の通りです。
■ 日本画
横山大観(よこやまたいかん)
<代表作:「無我」(むが)>
狩野芳崖(かのうほうがい)
<代表作:「悲母観音(ひぼかんのん)像」>
■ 彫刻
高村光雲(たかむらこううん)
<代表作:「老猿(ろうえん)」>
その一方で、欧米の美術そのものも、日本に導入されました。
フランスに留学した黒田清輝(くろだせいき)<代表作:「湖畔(こはん)」>が印象派の明るい画風を紹介し、ロダンに師事した日本近代彫刻の父とも呼ばれる荻原守衛(おぎわらもりえ)<代表作:「女」>は欧米風の近代彫刻を制作しました。
音楽では、滝廉太郎(たきれんたろう)が「荒城の月(こうじょうのつき)」や「花」などを作曲して、洋楽の道を開きました。
新しい文章
文学では、それまでの文語表現にかわって、話し言葉(口語)のままで文章を書くといった新たな文体を作り出すことが重要でした。
これを言文一致といい、二葉亭四迷(ふたばていしめい)が小説「浮雲(うきぐも)」で使用したのをきっかけに、口語表現は新しい表現方法として広まり、文語表現に取ってかわっていきました。
余談ですが、二葉亭四迷という名前は当然ペンネームで、本名は長谷川辰之助(はせがわたつのすけ)だそうです。「くたばってしまえ」という言葉から、自ら名付けたそうです。これは、文学を認めない父親に言われた言葉、あるいは自分自身への叱咤激励でもあり、卑下(ひげ)して名付けたと言われています。
日清戦争の前後には、個人の感情などを重視するロマン主義が主流になります。
短歌の与謝野晶子(よさのあきこ)、小説の樋口一葉(ひぐちいちよう)など女性の文学には、社会の現実を直視する自然主義が主流になる一方で、夏目漱石(なつめそうせき)と森鴎外(もりおうがい)は、欧米の文化に向き合う知識人の視点から小説を発表していきました。
それぞれの代表作は、以下の通りです。
与謝野晶子
代表作:「君死にたまふことなかれ」「みだれ髪」
樋口一葉
代表作:「たけくらべ」「十三夜」「にごりえ」「おおつごもり」
夏目漱石
代表作:「吾輩は猫である」「坊っちゃん」
森鴎外
代表作:「雁」「舞姫」「高瀬舟」「山椒大夫」
学校教育の普及
明治初期に学制が制定され、各地に小学校が建設されました。その結果、小学校の就学率は、1891(明治24)年に50%をこえるようになりました。
さらに、1907年には97%に達して、義務教育の期間も3、4年から6年に延長されました。
こうして、国民への教育の基礎が固まっていきました。また、小学校以外にも、中等・高等教育も拡充(かくじゅう)され、女子への教育も重視されるようになりました。
教育の広がりの中で、優れた科学者が多く現れ、19世紀末から日本人による世界的に最先端の研究が行われるようになりました。
細菌学では、北里柴三郎(きたさとしばさぶろう)が破傷風(はしょうふう)の血清療法(けっせいりょうほう)、野口英世(のぐちひでよ)が黄熱病(おうねつびょう)の研究などで功績を残しました。
そのほか原子物理学などの分野でも、多くの日本人科学者が世界の歴史に名を残しました。
中学2年生の【歴史】
二度の世界大戦と日本
★二度の世界大戦と日本★
①第一次世界大戦と日本
第一次世界大戦
列強(れっきょう)の動向
19世紀末の欧米諸国は、地球上のあらゆる所で植民地を広げ、アジア・アフリカ・太平洋地域の大半も植民地化されました。しかし欧米諸国が世界を支配した一方で、ヨーロッパの中でも対立が起こっていました。
19世紀末にドイツが新たな強国として台頭すると、フランスとロシアは同盟を結んで対抗しました。
イギリスはロシアの東アジアへの進出を警戒して日英同盟を結びましたが、ロシアが日露戦争に敗れると、こんどはロシアと協商を結んで関係を改善しました。
イギリスは、さらにフランスとも協商を結び、三国協商(さんごくきょうしょう)が成立しました。三国協商の三国とは、イギリス・フランス・ロシアですが、日本やセルビアは、この三国協商側に立ちました。
その一方で、ドイツはオーストリアと同盟関係にあり、さらにイタリアも加わって三国同盟(ドイツ・オーストリア・イタリア)が結ばれました。
こうして20世紀初めのヨーロッパの国際関係は、三国同盟と三国協商との間で「武装した平和」と呼ばれる緊張が続いていました。
【三国協商】
イギリス・フランス・ロシア(+日本・セルビア)
【三国同盟】
ドイツ・オーストリア・イタリア
第一次世界大戦
こうした列強の間の対立に、民族の対立が加わりました。
バルカン半島では、オスマン帝国(トルコ)が衰退するのにともない、スラブ民族の独立運動が盛んになり、「ヨーロッパの火薬庫」と呼ばれていました。
スラブ民族とは、東ヨーロッパに住む、ロシア人やセルビア人などの人々です。こうした中、南下政策を採っていたロシアが独立運動を支援し、反対に、オーストリアは運動をおさえようとしながら、それぞれバルカン半島進出をめざしました。
1914(大正3)年、オーストリアの皇太子夫妻が、サラエボでスラブ系のセルビア人に暗殺されるという事件が起きました。
オーストリアはセルビアに宣戦布告し、間もなく各国も参戦して、ドイツ、オーストリア、オスマン帝国(トルコ)を中心とする同盟国と、イギリス、フランス、ロシアを中心とする連合国(協商国)とに分かれて、第一次世界大戦が始まりました。
この時、イタリアは領土をめぐってオーストリアと対立して、三国同盟から離脱し、連合国側で参戦しました。
日本は日英同盟を理由に連合国側で参戦し、1917年にはアメリカも連合国側に加わるなど、戦争は世界中を巻きこみ、4年余り続きました。
<第一次世界大戦>
【同盟国側】
ドイツ・オーストリア・トルコ
【連合国側】
イギリス・フランス・ロシア・セルビア・イタリア・アメリカ・日本
総力戦とその結果
アメリカの参戦によって連合国側が優勢になり、1918年に第一次世界大戦は終わりました。
この戦争は、ざんごう(塹壕)戦で機関銃が大量に用いられたため、死傷者は莫大な数に上りました。
ざんごう(塹壕)とは、戦争において敵の銃砲撃から身を守るために陣地の周りに掘る穴または溝のことをいいます。
ざんごう戦とは、当事国同士が戦場に長大なざんごう(塹壕)を築城し、互いに相手の塹壕を突破できずに長期に渡って戦線が膠着した状況のことで、俗に第一次世界大戦を指します。
さらに新兵器の戦車・飛行機・毒ガス・潜水艦なども被害を拡大しました。
特に主戦場のヨーロッパでは、大量の兵士と物資を前線に送るため、各国が国民、経済、資源や科学技術を総動員して、総力戦となり国力を使い果たす結果となりました。
総力戦には、労働者や女性が兵器の製造やバスの車掌に動員されたり、さらに、植民地の人々も貢献したため、戦後にはこうした人々の要求が無視できなくなっていきました。
ロシア革命
ロシア革命
社会主義は、資本主義がもたらした社会問題を解決しようとして生まれた思想です。
国境をこえた労働者の団結と理想社会を目指す運動になって、各国に広がっていきました。
ロシアでも、政府が弾圧をおこなっていたにもかかわらず、社会主義勢力は拡大していきました。
第一次世界大戦が総力戦として長引き、民衆の生活が苦しくなると、ロシア内で戦争や皇帝の専制に対する不満が爆発しました。
1917(大正6)年に「パンと平和」を求める労働者のストライキや兵士の反乱が続き、かれらの代表会議<ソビエト>が各地に設けられました。
ソビエトとは、ロシア語で「会議」という意味です。当初は労働運動などを指導しましたが、後に革命の中心組織になっていきました。
皇帝ニコライ2世が退位して議会が主導する臨時政府ができましたが、政治は安定せず、社会主義者レーニンの指導の下、ソビエトに権力の基盤を置く史上初の社会主義政府ができました。
レーニンは、帝国主義を批判し、マルクスの主張を発展させて、労働者と農民の独裁を唱え、社会主義の世界革命を目指しました。
この一連の革命運動をロシア革命といいます。
ソ連の成立
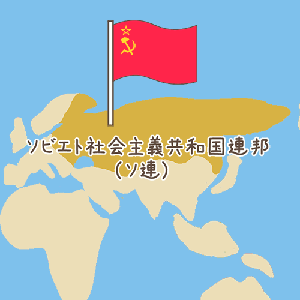
ロシアの革命政府は、銀行・鉄道・工場など重要な産業を国有化し、地主の土地を没収して農民に分配するなど社会主義の政策を実行しました。
一方で、第一次世界大戦においてソビエトは、各国に、無併合・無賠償・民族自立の即時講和を呼びかけたり、連合国側であったソビエトは、1918年に同盟国側のドイツと単独で講和を結んで、第一次世界大戦から離脱しました。
ロシア革命により、各国で社会主義の運動が高まりました。資本主義に不満を持っていたり、戦争に反対していた人々に支持されたからでした。
しかし、イギリス、フランス、アメリカ、日本などの資本主義国は、ロシア革命政府の外交方針に反対しました。
さらに社会主義の影響の拡大をおそれて、ロシア革命への干渉戦争を起こし、シベリア出兵を行いました。特に日本は、シベリアに領土を得ることも目的にしていたため、シベリアに大軍を派遣しました。
革命政府は労働者と農民を中心に軍隊を組織して外国からの干渉戦争に勝利し、国内の反革命派も鎮圧しました。
そして1922年にはソビエト社会主義共和国連邦(ソ連)が成立しました。しかしソ連は、国際社会から国としてはしばらくの間認められませんでした。
独裁と計画経済
ロシア革命を指導した政党は、名前を共産党に改めました。共産主義(きょうさんしゅぎ)の実現を目標としていたためでした。
共産党は他の国にも設立され、国際的な機関もソ連共産党を頂点として結成されました。
しかし、ソ連以外では社会主義革命は実現しませんでした。このためレーニンの後をついだ次の指導者スターリンは、ソ連一国での共産主義化を優先しました。
スターリンは、1928(昭和3)年からは五か年計画を始めていきます。五か年計画の中では、重工業の増強と農業の集団化を強行しました。
この計画経済によって、ソ連は国力を確実にのばしていきました。スターリンは、五か年計画の成功によって権力を固め、反対派を弾圧して個人崇拝を強め独裁者化しました。
国の強硬な方針に批判的な人々は、追放されたり処刑されたりして、多くの犠牲者が出ました。
スターリンの死後は、このような独裁化を「スターリニズム」または「スターリン主義」と呼ぶようになり、指導者に対する個人崇拝、軍事力や工作活動による暴力的な対外政策、秘密警察の支配を背景とした恐怖政治や大規模な粛清(しゅくせい)などを特徴とする全体主義として批判されています。
国際協調の高まり
ベルサイユ条約と国際連盟
第一次世界大戦は、1918年、アメリカの参戦により優勢になった連合国の勝利で終わりました。
翌1919年にパリ講和会議が開かれました。パリ講和会議では、イギリス、フランスなどの戦勝国が戦争の責任をドイツにおし付け、またドイツの弱体化を図ろうとしました。
講和条約であるベルサイユ条約では、ドイツは領土が縮小され、植民地を失い、巨額の賠償金や軍備縮小を約束させられました。
パリ講和会議において、民族自決の原則も唱えられ、東ヨーロッパで多くの小国が独立しました。
参考までにこの時、民族自決によって独立国となった国は以下の通りです。
エストニア・オーストリア・チェコスロヴァキア・ハンガリー・フィンランド・ポーランド・ラトビア・リトアニア・ユーゴスラヴィア
一方で、アジアとアフリカの植民地支配は続いたため、これらの地域では独立運動が高まりました。こうした運動は第二次世界大戦後の植民地支配からの解放へとつながっていくのです。
また、アメリカのウィルソン大統領の提案<十四か条の平和原則>を基にして、世界平和と国際協調を目的とする国際連盟が発足しました。
国際連盟はスイスのジュネーブに本部を置き、常任理事国にはイギリス・フランス・イタリア・日本がなりました。アメリカは国内の反対で加入できず、紛争を解決するために行う制裁手段も限られていたため、当時の国際連盟の影響力は大きくありませんでした。
日本は、ベルサイユ条約でドイツが持っていた中国の山東省(さんとうしょう)の権益をひきつぎ、国際連盟から委任される形で、太平洋地域の植民地の統治権を獲得しました。
この時、新渡戸稲造(にとべいなぞう)が、国際的に活躍し、1920年から26年まで国際連盟の事務次長を務めました。
国際協調の時代
第一次世界大戦終結後の1920年代は、国際協調の時代です。第一次世界大戦で力を弱めたヨーロッパ諸国にかわって、アメリカが世界経済の中心になりました。
また政治面でも、国際連盟には加入しなかったものの、アジア・太平洋地域で発言力を強めていきました。
1921年から翌22年には、アメリカの呼びかけでワシントン会議が開かれ、海軍の軍の制限と、太平洋地域の現状維持や、中国の独立と領土の保全を確認しました。
また、ワシントン会議でアメリカ、・イギリス・フランス・日本の間で四か国条約が結ばれ、日英同盟は解消されました。
しばらくして、ドイツも国際連盟への加盟が認められました。
大衆の時代
1920年代の欧米諸国では、普通選挙による議会政治が普及しました。女性も多くの国で選挙権を得て、民主主義の新しいにない手になりました。
職業を得て社会に進出する女性も増え、各国で労働者の権利の拡大を求める運動も高まりました。
ドイツは、1919年に当時の世界で最も民主的とされたワイマール憲法を制定し、労働者の基本的権利の保護、社会福祉政策の導入などを定め、この憲法とともに、共和国として再出発しました。
イギリスでは、1924年、初の労働党内閣が成立しました。
1920年代のアメリカでは、ニューヨークにはすでに超高層ビルが建てられていたり、雑誌・ラジオ・映画・自動車が大量生産されて、都市の大衆は、これらの商品を購入し、新しい生活と文化を楽しむようになりました。
こうした繁栄は、ヨーロッパや日本にも広がっていきました。
アジアの民族運動
中国の反帝国主義運動
第一次世界大戦にて、欧米列強のアジアへの影響力が弱まると、1915年、日本は中国に対して二十一か条の要求を示し、大半を半強制的に認めさせました。
その中には、日本が大戦中に占領した山東(さんとう)省の権益をドイツから引きつぐことや、旅順(りょじゅん)・大連(だいれん )など、日本が日露戦争で獲得した満州の権益の期限延長や、内容の拡張などが盛り込まれていました。
しかし、これは主権を侵すものだとして、中国の強い反発を受けました。
大戦後、中国は山東省の権益の返還を要求しました。しかし、パリ講和条約で要求が拒絶されると不満が爆発しました。
1919年5月4日の北京での学生集会をきっかけに反日運動が起こり、帝国主義に反対する全国的な五・四運動(ごしうんどう)へと発展しました。
この運動をきっかけに、孫文(そんぶん)は中国国民党(国民党)を結成し、1921年に結成された中国共産党と協力して、国内の統一を目指しました。
日本は、ベルサイユ条約では山東省のドイツ権益を引きつぎましたが、1921年から開かれたワシントン会議の結果、これを中国に返還しました。
武力よりも経済による進出を重視する政策を選択しました。しかし、中国ではいまだ日本の植民地支配の下であった旅順・大連など、満州の権益の回収を求めて、各地で日本製品の不買運動が続けられました。
朝鮮の独立運動
朝鮮では、日本の植民地支配の下に置かれていましたが、民族自決の考えの影響を受けて、1919年3月1日、独立を目指す知識人や学生などが、京城(けいじょう)<ソウル>で日本からの独立を宣言する文章を発表し、「独立万歳(ばんざい)」をさけんで人々は デモ行進を行いました。
これに刺激されて、独立運動は短期間で朝鮮半島全体に広がりました。
これを三・一独立運動(さんいちどくりつうんどう)といいます。
朝鮮総督府は、武力でこうした動きを鎮圧しました。
三・一独立運動後、朝鮮総督府は、統治の方針を転換し、朝鮮の人々に政治的な権利を一部認めるなどしましたが、日本への同化政策は進められたため、独立運動は継続されました。
インドの民族運動
アジアやアフリカでは、ロシア革命やパリ講和会議における東ヨーロッパなどでの民族自決の考えの影響を受けて、民族の独立を目指す運動が高まりました。
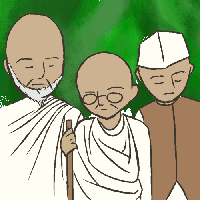
イギリスの植民地支配に苦しんでいたインドでも、第一次世界大戦後に自治を認めるという約束をイギリスが守らなかったため、ガンディーの指導によって、「塩の行進」とよばれる非暴力・不服従の大規模な抵抗運動が行われました。
ガンディーは、インドにおける民族独立運動の最高指導者で、人々からマハトマ(偉大な魂)・ガンディーと呼ばれ、現在でも尊敬されている人物です。
第二次世界大戦後の1947年、インドは独立を達成しますが、イスラム教徒とヒンドゥー教徒との宗教をめぐる対立から、ガンディーは、1948年に暗殺されました。
大正デモクラシーと政党内閣の成立
第一次護憲運動
日露戦争前後の政治は、藩閥(はんばつ)、官僚(かんりょう)勢力と立憲政友会とが交互に政権を担当していました。
しかし1912年、立憲政友会の内閣が倒され、藩閥の桂太郎が首相になると、新聞や知識人は、藩閥を倒し、憲法に基づく政治を守ることをスローガンとする運動を起こしました。
これを第一次護憲運動(だいいちじごけんうんどう)といいます。
民衆もこれを支持して数万人の民衆が国会議事堂を取り巻き、桂内閣の退陣を迫るなど運動が盛り上がったため、桂内閣は退陣しました。
大戦景気と米騒動
日本経済は第一次世界大戦によって、大戦景気とよばれる好況を迎えました。
工業製品の輸出が、連合国やその植民地、アメリカ向けに大幅に増えた一方、大戦で欧米からの輸入が止まったことから、重化学工業を中心に国内で新たな産業がおこり、工業国としての基礎が築かれました。
なかでも鉄鋼の分野は生産量が大きく増加しました。
しかし民衆の生活は、好況にともない物価が上がったため逆に苦しくなりました。
さらに1918(大正7)年、シベリア出兵を見こした米の買い占めから、米の値段が大幅に上がると、米の安売りを求める暴動事件である米騒動が全国に広がっていきました。
政府は軍隊を出動させて鎮圧するなど大きな騒動に発展しました。
本格的な政党内閣の成立
1918年の米騒動で、藩閥の寺内正毅(てらうちまさたけ)内閣が退陣すると、原敬(はらたかし)が内閣を組織しました。
原は、それまでの首相と違い、華族ではなかったことから「平民宰相(さいしょう)」と呼ばれ親しまれました。
原内閣は、陸軍・海軍・外務の3大臣をのぞいて、それ以外はすべて衆議院第一党(最も議員の数が多い政党)の立憲政友会の党員で組織された本格的な政党内閣の誕生となりました。
原は、1919年に選挙法を改正して選挙権を持つのに必要な納税額をそれまでの10円以上から、3円以上に引き下げましたが、普通選挙に対してはタイミングがまだ早いとして後ろ向き(消極的)でした。
大正デモクラシーの思想
大正時代のとくに第一次世界大戦後は、政党政治が発展したため「大正デモクラシー」と呼ばれ、民主主義(デモクラシー)が強く唱えられた時代でした。
大正デモクラシーの思想を広めるうえで、大きな役割を果たした人物が二人います。
一人目は、吉野作造(よしのさくぞう)という政治学者です。
吉野は、民本主義(みんぽんしゅぎ)を唱え、政治の目的を一般民衆の幸福や利益とし、一般民衆の意向に沿って政策を決定すべきことを主張しました。
制度面でも普通選挙と政党内閣制の必要性と実現を説きました。
二人目は、美濃部達吉(みのべたつゆき)という憲法学者です。
美濃部は、天皇機関説を唱え、主権は国家にあり、天皇は国家の最高機関として憲法に従って統治するという憲法学説を主張しました。
美濃部達吉の主張は、政党内閣制に理論的な根拠をあたえました。
二人に共通しているのは、政党内閣制の正当性を主張している点になります。
広がる社会運動と普通選挙の実現
社会運動の広がり
第一次世界大戦後、労働運動や農民運動、女性運動などの社会運動が活発になり、社会主義の思想も広まるようになりました。
労働運動では、第一次世界大戦中の経済発展によって労働者が大幅に増加したという時代背景もあり、ストライキなどの労働争議(ろうどうそうぎ)も多く発生しました。
大戦前から存在し、渋沢栄一からの援助も受けていた友愛会は、当初は労働者の相互扶助を目的とした共済組合のようなものでしたが、徐々に労働組合の全国組織へと発展していきました。
1920<大正9>年には、日本初のメーデーを主催し、最低賃金制や8時間労働制などを要求しました。友愛会は、翌1921年には日本労働総同盟に改称されました。
尚、メーデー(May Day=5月の日)は、日本だけでなく世界各地で毎年5月1日に行われる労働者の祭典のことを言います。
農村でも、小作争議(こさくそうぎ)が頻繁に発生し、小作料の減額などを求め活動するようになりました。1922年には、日本農民組合が全国組織として結成されました。
社会主義運動も活発化していきました。1920年には、日本社会主義同盟が結成され、ロシア革命の影響もあり共産主義への関心が急速に高まりました。
1922年には、日本共産党が結成されましたが、この時はまだ非合法のものでした。
解放を求めて
社会運動の活性化の影響もあり、まだまだ部落差別に苦しんでいた被差別(ひさべつ)部落の人々も、部落解放運動を進めました。
部落解放運動とは、政府にたよらず、自らの力で人間としての平等を勝ち取り、差別からの解放を目指す運動です。
全国水平社(ぜんこくすいへいしゃ)が1922年に京都で結成され、部落解放運動は全国に広がっていきました。
同様に、まだまだ差別に苦しんでいたアイヌ民族の解放運動も北海道で発生し、1930(昭和5)年には北海道アイヌ協会が結成されました。
北海道アイヌ協会は、日本社会への同化政策に反対し活動しました。
女性運動と男子普通選挙の実現
女性運動も、まだまだ残っていた女性差別からの解放を目指し起こるようになりました。
平塚らいてう(ひらつからいちょう)は、「新しい女」を目指し、女性だけで構成された文芸集団である青鞜社(せいとうしゃ)を結成して女性の解放を唱え、1920年には新婦人協会を設立し、女性の政治活動の自由、女子高等教育の拡充、男女共学などを求める運動を広めました。
また、女性が政治に参加する権利を求める選挙権運動も本格化するようになりました。
一方、第一次世界大戦後には普通選挙の実現を目指す動きが高まりました。
1924年、政党勢力は第二次護憲運動を起こし、新たに憲政会党首の加藤高明(かとうたかあき)を首相とする連立内閣が成立しました。
加藤内閣は、1925年に普通選挙法を成立させました。
これは、納税額による制限を廃止し、満25歳以上の男子に選挙権をあたえる内容の法律でした。普通選挙法によって有権者は約4倍に増加し、広く国民の意向が政治に反映される道が開かれました。
しかし、選挙権は女性にはまだ認められませんでした。
また、普通選挙法と同1925年に治安維持法(ちあんいじほう)が制定されました。
治安維持法の制定により、共産主義に対する取りしまりが強化されました。
新しい文化と生活
教育の広がり
小学校の義務教育は、明治時代末期にほぼ実現し、大正時代には、これを受けて中等・高等教育が広がるようになりました。
中学校や高等女学校(現在の高等学校)への進学率が高まり、大学や専門学校も数が増えて、多くの知識人が誕生するようになりました。
小学校では、徐々に生徒の個性を大切にし、自主性重視の自由教育運動も行われるようになりました。
大衆文化の発展
大正時代には、都市の発展と知識人の増加にともない、活字文化が広まるようになりました。
発行部数が100万部をこえる新聞も登場したり、週刊誌や月間総合雑誌の発行部数も急速にのびていきました。
1冊1円の文学全集<円本>や、さらに低価格の岩波文庫などが出版され、活字文化の大衆化に大きな役割を果たしました。
子ども向け雑誌も発行されるようになり、ヨーロッパ風の童謡や童話も大衆へ広まるようになりました。
国産の映画(この頃は活動写真と呼んでました)も製作され、多くの観客を集めました。
ちなみに梅屋庄吉(うめやしょうきち)が設立した映画の会社「日活」は、日本活動写真株式会社の略で、1920年代の映画の発展に重要な役割を果たしました。
また蓄音機(ちくおんき)やレコードが普及した影響により、歌謡(かよう)曲が全国的なブームとなりました。
ラジオ放送も、1925<大正14>年に東京・名古屋・大阪ではじめられ、全国に普及していきました。
こうしたメディアの発達にともない、コンテンツである大衆小説・映画・歌謡曲や、野球などのスポーツが大衆娯楽として定着していくようになりました。
ちなみに阪神甲子園球場が完成したのも1924年でこの時代です。
新しい思想や文化
学問や芸術にも新たなトレンドが生まれました。
学問では、独創的な研究者が現れました。
■西田幾多郎(にしだきたろう)・・・哲学者。東洋と西洋の哲学(てつがく)を統一しようとした。
■柳宗悦(やなぎむねよし)・・・思想家。民芸運動を行う。
(民芸運動とは、日常的な暮らしの中で使われてきた民衆の道具に美しさを見出し、活用する日本独自の運動です。「民芸」とは、民衆的工芸の意味です。)
文学では、優れた作家や作品も多数発表されました。
■志賀直哉(しがなおや)・・・白樺派を代表する小説家のひとり。「小説の神様」と呼ばれる。代表作:「暗夜行路」「和解」「小僧の神様」「城の崎にて」など
■谷崎潤一郎(たにざきじゅんいちろう)・・・小説家。「文豪」「大谷崎(おおたにざき)」 と呼ばれる。代表作:「刺青」「痴人の愛」「卍(まんじ)」
■芥川龍之介(あくたがわりゅうのすけ)・・・小説家。代表作:「羅生門(らしょうもん)」「地獄変」(古典文学から題材をとった短編小説)/「蜘蛛(くも)の糸」「杜子春(とししゅん)」(子ども向けの短編小説)
■小林多喜二(こばやしたきじ)・・・日本のプロレタリア文学の代表的な小説家。代表作:「蟹工船(かにこうせん)
美術では、洋画の岸田劉生(きしだりゅうせい)や竹久夢二(たけひさゆめじ)などが活躍しました。
音楽では、童謡に多くの作品を残した野口雨情(のぐちうじょう)をはじめ、日本で最初の職業オーケストラを組織した洋楽の山田耕作(やまだこうさく)や、邦楽<筝曲(そうきょく)>の宮城道雄(みやぎみちお)などが新風をふきこみました。
都市の生活
ガス・水道・電気などの生活インフラの普及によって、都市部では欧米風の生活様式が広まりました。
「文化住宅」と呼ばれる欧米風の外観や応接室を持った住宅が流行し、ライスカレー・トンカツ・コロッケなどの洋食が広まりました。
洋服は最初は男性に広まりましたが、バスガールや電話交換手などといった働く女性が増加し、都市部では高等女学校の制服にセーラー服が採用されたことなどから、女性にも広まり始めました。
さらに、ひざ丈のスカートに帽子といった先端的な衣服の女性が東京の銀座などの街に現れ、モダン・ガールと呼ばれました。
但し、1920年代に実際に洋装をしていた人は、人口の約1%程度だったようです。
★二度の世界大戦と日本★
②世界恐慌と日本の中国侵略
世界恐慌とブロック経済
世界恐慌と大不況
第一次世界大戦後の平和と繁栄は、世界恐慌(せかいきょうこう)により突如終わりを迎え、世界的な大不況の時代を迎えることになります。
1929(昭和4)年10月、世界経済の中心だったアメリカのニューヨーク株式市場で株価が大暴落しました。
銀行が信用を失い、人々がいっせいに預金を引き出そうとする取り付け騒ぎが起き、多くの銀行が倒産して恐慌になりました。
結果的に、資金を借りられなくなった多くの企業が倒産し、失業者が増えたために物が売れなくなり、それがさらに倒産を増やすという悪循環が発生しました。
アメリカの失業率は、この時最大で25%に達したようです。こうして、恐慌は深刻な不況を生み出しました。
またアメリカは、多くの国に資金を貸していたので、恐慌は世界中に広がり、ほかの国々にも深刻な不況をもたらす形となりました。
アメリカのニューディール政策
アメリカは、ルーズベルト大統領の指揮で、恐慌に対する対策として、1933年からニューディール<「新規まき直し」という意味です>という政策を始めました。
国内の農業や工業の生産を調整し、公共事業を積極的に行って失業者を助け、労働組合を守りました。
ニューディール政策によりアメリカ国内では国民の購買力が上向き、経済が回復する方向に向かったため、民主主義の政治も続けられました。
この一方で、アメリカは保護貿易という自国産業優先の政策を強化したため、輸出入の貿易は大幅に減ってしまいました。
アメリカは、当時世界最大の貿易国であり、この保護貿易はアメリカへの輸出が重要だった国々にとって大打撃となってしまいました。
ブロック経済
世界恐慌の対策として、主要国はブロック経済という自国を中心に排他的な経済圏を作って対立しました。
イギリスは、大不況の中で、本国と植民地との関係を密接にし、オーストラリアやインドなどとの貿易を拡大しつつ、その他の国の商品に対する関税を高くしました。
フランスも、同じように植民地が多かったのでブロック経済を採りました。
これに対して、イタリア、ドイツ、日本は、植民地が少なかったので、自らのブロック経済圏を作ろうとして、新たな領土の獲得を目指すようになっていきました。
このように各国は、10年ほど続いた深刻な大不況に対して、それぞれ自国第一の政策を追求していったため、国際連盟などによってできあがっていた国際協調体制は大きくゆらぐようになりました。
一方、ソ連は、五か年計画による独自の経済政策を採っていたため、他の主要国のような世界的大不況の影響を受けることなく成長を続け、アメリカに次ぐ第二位の工業国となっていました。
欧米の情勢とファシズム
ファシズム
ヨーロッパでは第一次世界大戦後、民主主義が発展した一方で、ファシズムと呼ばれる政治運動も登場していました。
ファシズムは、全体主義という個人よりも民族や国家を重視した考え方で 民主主義を否定し、対外的には武力による侵略を主張しました。
このファシズムは、イタリアで生まれ、ドイツで最も勢力を強めました。
イタリアのファシズム
イタリアのファシズムの中心は、ムッソリーニという人物です。
イタリアは、第一次世界大戦の戦勝国ではありましたが、戦争による被害が大きく、経済はしばらく混乱していました。
ファシスト党を率いていたムッソリーニは、領土問題や共産主義の拡大に対する国民の不満をうまくあおりながら、1922(大正11)年に首相になりました。
ムッソリーニは、ファシスト党以外の政党を禁止して独裁を行い、さらに言論や集会の自由を制限しました。
また、世界恐慌の後に経済が行きづまると、エチオピアを侵略し、1936(昭和11)年にエチオピアを併合しました。
併合とは、国際法上で、ある国が他の国の領土の全部または一部を合意によって自国のものとすることをいいます。
今回は、イタリアがエチオピアを自国のものとしたということになります。
イタリアのエチオピア侵略は国際的に非難されましたが、ドイツは逆にイタリアに接近し、両国は関係を深めていくようになりました。
ドイツのファシズム

日本の某有名アイドルグループが、2016年に開催したハロウィンイベントの新衣装で、ワシの紋章を付けた帽子や黒いマントが、ナチス・ドイツの軍服を連想させるとして世界中からネットで批判を浴びた出来事がありました。
ナチスの軍服は洗練されていてマニアもいるぐらいですが、海外の特にヨーロッパの人々はよい印象を持たない人が多いです。
ナチスは、正式には「国民社会主義ドイツ労働者党」という政党の略名です。ドイツのファシズムは、このナチスとヒトラーにより推し進められました。
ドイツは、第一次世界大戦の敗戦国で、講和条約であるベルサイユ条約が戦勝国からおし付けられたものと考えられていました。
また、賠償金が重い負担になって、ドイツ経済は混乱の中にありました。
こうした中で、ヒトラーの率いるナチスは、ベルサイユ条約に対する国民の不満をあおりました。
また、その不満を人種的な差別へ向けさせるように、ユダヤ人を迫害(はくがい)し、共産主義者などを攻撃しながら、ドイツ民族の優秀さをアピールする宣伝活動によって国民の注目を集めました。
1929年より始まった世界恐慌による深刻な不況をうまく利用し、ナチスは混乱の中で勢力を大きくのばしていき、1932年には第一党になりました。
翌1933年にヒトラーはドイツ首相となり、ほかの政党を解散させ民主的なワイマール憲法も停止して独裁を確立させました。
また、ドイツは国際連盟から脱退し、国際的な批判にも関わらずドイツ軍を強化しました。
ドイツでは公共事業と軍需(ぐんじゅ)産業によって経済は回復しました。そのかわり軍事大国となり、国民の自由はうばわれ、秘密警察が国民を監視し統制する全体主義の国家へと変貌していきました。
また、ファシズムは、イタリアやドイツだけでなくスペインなどほかの国々でも勢力を強めていきました。
スペインでは、ドイツやイタリアが介入した内戦の結果、ファシズムの影響を強く受けた政府が成立しました。
昭和恐慌と政党内閣の危機
政党政治の進展と行きづまり
世界恐慌の少し前、日本では1924<大正13>年、第二次護憲運動により憲政会<後の立憲民政党>党首の加藤高明(かとうたかあき)内閣が成立し、翌1925年には普通選挙法や治安維持法が制定されていました。
それ以降は、憲政会と立憲政友会が交互に政権を運営しました。
「憲政の常道(けんせいのじょうどう)」と呼ばれ、二大政党の党首が内閣を組織する慣例が行われていきました。
1928<昭和3>年には、男子普通選挙による初の衆議院議員選挙が実施されて、労働組合や農民組合が支持する社会主義政党も議席を獲得しました。
しかし、経済や外交などで困難に直面するようになり、政党政治は、行きづまるようになっていきました。
昭和恐慌
第一次世界大戦後、日本の経済は、慢性(まんせい)的な不況が続いていました。
さらに追い打ちをかけるように1923年(大正12年)9月1日に 関東大震災(かんとうだいしんさい)が発生しました。
国内経済は大打撃を受け、その後の混乱などから1927年には金融恐慌(きんゆうきょうこう)が起こり、多くの銀行が休業に追いこまれたりしました。
1930年に入るとアメリカから始まった世界恐慌は、日本にも影響をおよぼし、昭和恐慌(しょうわきょうこう)と呼ばれる深刻な大不況が発生しました。
都市では多数の企業が倒産し、失業者があふれてしまいました。
農村でも、同1930年の豊作により米やまゆなどの農産物の価格が暴落したため、生活が苦しくなっていました。
さらに翌1931年の大凶作に見まわれた東北地方と北海道では、飢饉が起こりるなどさらに苦しくなっていきました。
社会的な問題として、女性の「身売り」が借金のために行われたり、学校に弁当を持っていけない「欠食児童」が発生するようになりました。
こうした中、労働争議や小作争議も激化していき、経済に多大な影響力を持つ財閥への批判が集中しました。さらに、財閥と結託(けったく)して汚職(おしょく)や政争をくり返す政党への不信感が人々の間で高まっていきました。
難航する外交
中国では、1916年の袁世凱の死後、各地の軍閥が分かれて支配していました。
1925年に孫文が亡くなると、国民党の新しい指導者になった蒋介石(しょうかいせき)が中国国内の統一を進めるようになりました。
1927年に国民政府が南京に作られ、不平等条約の撤廃を目指す民族運動の高まりを背景に、日本などの列強が持つ中国での権益の回収を主張しました。
また、国民党へ協力していた中国共産党を弾圧し、1927年に中国内で内戦(国民党VS共産党)を開始し、1937年の日中戦争開始まで続きました。
一方、蒋介石の率いる国民政府軍が北京に接近してくると、危機感を持った現地の日本軍<関東軍>は、満州の直接支配を目指しました。
1928年、満州の軍閥で統治者であった張作霖(ちょうさくりん)を爆殺(ばくさつ)してしまいました。
しかし、張作霖の子で後継者の張学良も程なく日本軍に爆殺されたという事件の真相を知って激怒し、中国国民政府と和解して日本と対抗する政策に転換しました。
結果、日本は満洲への影響力を弱める結果となりました。これが、後の満州事変の背景の1つとなります。
立憲民政党の浜口雄幸(はまぐちおさち)内閣は、中国全土をほぼ統一した中国国民政府との関係改善を目指す一方で、軍備を縮小して国民の負担を減らすため、イギリスやアメリカなどと協調して、1930年にロンドン海軍軍縮条約を結びました。
しかし、一部の軍人や国家主義者は、これを大日本帝国憲法に定められた天皇の権限<陸海軍の指揮、条約の締結や戦争の開始、終了(講和)など>の侵害であると強く批判しました。
浜口首相は東京駅でおそわれて重傷を負い辞任に追いこまれました。
余談ですが、浜口首相は、日本の首相で初めて当時の最新メディアであったラジオを通じて国民に直接自身の政策を訴えた首相のようです。
満州事変と軍部の台頭
満州事変と日本の国際的な孤立
いよいよ満州事変が起こります。
満州事変はどのようにして起こり、日本の政治はどのように変化していったかを見ていきましょう。
張作霖の爆殺事件後、中国において日本が持つ権益を取りもどそうとする動きがさらに強まると、危機感を強めた関東軍は1931<昭和6>年9月18日に、柳条湖事件を起こしました。
奉天(ほうてん)郊外の柳条湖(りゅうじょうこ)で日本の所有する南満州鉄道の線路を爆破し、関東軍はこれを中国軍による犯行と発表<実は自作自演>することで、満州における軍事展開およびその占領の口実として利用しました。
この一連の動きを満州事変(まんしゅうじへん)と呼びます。
満州の主要地域を占領した関東軍は、1932年3月、清の最後の皇帝であった溥儀(ふぎ)を元首とする満州国(まんしゅうこく)の建国を宣言しました。
日本が支配した満州国には、軍事的な目的もあって、日本からの移民が進められました。
一方の中国は、国際連盟に対し、日本の軍事行動を侵略であると訴えました。
1933年に開かれた国際連盟の総会で、リットン団長を中心とする調査団の報告により、満州国の建国を認めず、日本軍の占領地からの撤兵を求める勧告を採択しました。日本は、これに反発し国際連盟を脱退しました。
1936年にはワシントン、ロンドンの軍縮条約の期限も切れ、日本は国際的に孤立していきました。
このような中で、日本は同1936年、共産主義勢力の進出に対抗するという理由で、ファシズムで台頭していたドイツと日独(にちどく)防共協定を結び、ファシズム諸国に接近していきました。
軍部の発言力の高まり
日本国内では、満州事変について大多数の新聞が軍の行動を支持し、昭和恐慌に苦しんでいた民衆も歓迎したようです。
こうした中、政党や財閥を打倒して、強力な軍事政権を作り、国家を造り直そうという動きが軍人や国家主義者の間で活発になりました。
1932年5月15日ある事件が発生しました。
五・一五事件(ごいちごじけん)という、海軍の青年将校などが首相官邸をおそい、犬養毅(いぬかいつよし)首相を暗殺した事件です。
この事件によって、政党内閣の時代が終わりを迎え、軍人が首相になることが多くなりました。
また、1936年2月26日にも事件が起こります。
二・二六事件(ににろくじけん)という、陸軍の青年将校が大臣などを殺傷し、東京の中心部を占拠した事件です。
こちらは、しばらくして鎮静化させられましたが、この事件以降、軍部は政治においても発言力をさらに強め、軍備の増強を推進していきました。
経済の回復と重化学工業化
日本の経済は、世界恐慌で重大な打撃を受けましたが、諸外国と比べた場合、いち早く不況から立ち直っていました。
軍需(ぐんじゅ)品の生産と政府の保護によって特に重化学工業が発展し、軽工業の生産額を上回るようになりました。
重化学工業では新しい財閥が急成長し、朝鮮や満州にも進出するようになりました。
また、綿製品などの輸出が増加し、ブロック経済を採用していたイギリスなどとの間で、貿易摩擦が深刻化していきました。
日中戦争と戦時体制
日中戦争の開始と長期化
満州国建設後、日本は、さらに中国北部に侵入しました。
中国では、国民政府<国民党>と共産党との内戦が続いていましたが、抗日(こうにち)運動が盛り上がる中、毛沢東(もうたくとう )を指導者とする共産党は、蒋介石(しょうかいせき)を指導者とする国民党に協力を呼びかけ、1936<昭和11>年に内戦を停止しました。
1937年7月、盧溝橋(ろこうきょう)事件 が起こります。この事件は、北京郊外の盧溝橋付近で起こった日中両国軍の武力衝突事件です。
これをきっかけに、日中戦争が開始されました。戦火は中国中部の上海にも拡大し、全面戦争に発展しました。
この状況を受けて、最終的に内戦中だった国民党と共産党は日本との戦争のために再び協力し合うことを決め、抗日民族統一戦線が成立しました。
1937年末、日本軍は首都南京を占領しました。その過程で、南京事件という女性や子どもなど一般の人々や捕虜をふくむ多数の中国人を殺害したと言われています。
南京事件は「南京大虐殺」とも呼ばれ、多くの被害者が出たようですが、被害者の具体的数については、いまだに確定できていないようです。
しかし、国民政府は、占領された南京から首都をまずは漢口(かんこう)、次に重慶(じゅうけい)へと移し、アメリカやイギリスなどのバックアップを受けながら、戦争を継続しました。
強まる戦時体制
日中戦争が長引くにつれ、軍部からの要求により、日本政府は軍事費を増大させ、戦時体制を整備していきました。
1938年、国家総動員法(こっかそうどういんほう)が近衛文麿(このえふみまろ)内閣により制定されました。
政府は議会の承認がなくても、労働力や物資を戦争へと動員できるようになりました。
1940年には近衛が総力戦のために「挙国一致(いっち)」の体制を作る運動を開始し、政党は解散して、新たに公事結社として大政翼賛会(たいせいよくさんかい)という政治結社が結成されました。
また、労働組合なども解散させられたようです。
戦時体制下で国民生活のコントロールも強化されました。節約を訴えるスローガンが並び、「ぜいたくは敵だ」「ガソリン一滴は血の一滴」「欲しがりません勝つまでは」などが叫ばれたようです。
軍需品の生産が優先され、農村でも労働力や肥料が徐々に足りなくなっていきました。国民に対する生活必需品の供給量が少なくなり、1940年には砂糖とマッチが切符制になり、翌1941年には、米が配給制へ、更に1942年には衣料品が切符制になりました。
また隣組(となりぐみ)という町内会などのさらに下の地域組織を官主導で整え、約10戸を単位として住民を相互に監視させ、政府のコントロールと戦争への動員を支えました。
言論の自由や文化へのコントロールも強化され、自由主義的な思想や学問に対しても圧力が加えられました。
朝鮮では、日本の植民地として皇民化政策(こうみんかせいさく)が推進されました。
皇民化政策とは、強制的に日本語を話させたり、神社への参拝や、姓名を日本式に改めさせる創氏改名などのそれまでの同化政策をさらに強化した政策です。
さらに、1938年には、志願兵制度が作られるなど、朝鮮の人々も戦争に動員されました。
同じく日本の植民地であった台湾においても皇民化政策や戦時動員が行われ、戦時体制が強まっていきました。
さて、次章はいよいよ第二次世界大戦の始まりとなります。
★二度の世界大戦と日本★
③第二次世界大戦と日本
第二次世界大戦
第二次世界大戦の始まり
第二次世界大戦の始まりは、ドイツがきっかけでした。その頃ヨーロッパでは、ヒトラー率いるナチス・ドイツが、東ヨーロッパなど東方侵略を進めていました。
ドイツは、東方侵略によりオーストラリア、チェコスロバキア西部を併合した後、対立していたソ連と独ソ不可侵条約を締結し、1939(昭和14)年9月に、ポーランドに侵攻を行いました。
このドイツのポーランド侵攻に対して、お互いに援助し合う条約を結んでいたイギリスとフランスが、ドイツに宣戦布告を行いました。
こうして第二次世界大戦が始まったのです。
戦争の拡大
ドイツは 、翌1940年に、デンマーク、ノルウェーといった北ヨーロッパや、オランダ、ベルギーなど西ヨーロッパの国々を攻撃しました。
さらにフランスの首都パリを占領し、フランスも降伏させました。イギリス本土も、ドイツ軍の空襲により激しく攻撃されました。
イタリアは、ドイツのヨーロッパでの優利な戦況を見て、ドイツ側として参戦しました。
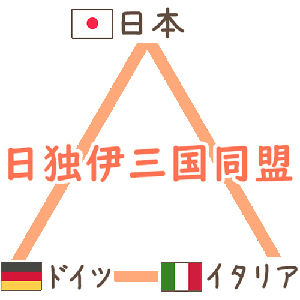
1940年9月、ドイツ、イタリアは、日中戦争中であった日本と日独伊三国同盟(にちどくいさんごくどうめい)を結び、枢軸(すうじく)国として結束を強化しました。
スターリン率いるソ連は、この間に独ソ不可侵条約での秘密の取り決めにより、ポーランド東部やバルト三国などを軍事力で併合しました。
しかし、ドイツは独ソ不可侵条約を破棄しソ連に侵攻しました。1941年6月の出来事でした。
アメリカは、まだ参戦していませんでしたが、イギリスやソ連に武器などの援助をおこなっていました。
1941年8月、アメリカのルーズベルト大統領とイギリスのチャーチル首相は、大西洋憲章を発表して、戦後の平和構想とファシズムへ対決する決意を示しました。
このようにしてヨーロッパでは、ファシズムによる枢軸(すうじく)国と反ファシズム連合国の戦いという構図がはっきり示されるようになり、戦争が拡大していきました。
尚、枢軸国という呼称は、1936年に成立したドイツとイタリアの提携関係が「ベルリン・ローマ枢軸」と呼ばれたことに由来しているようです。
ドイツの占領政策
ドイツをはじめとする枢軸国は、ヨーロッパ大陸の大部分を支配下に収め、ひどい占領地政策を行ったようです。
反対する人々を弾圧したり、物資を力ずくで取り上げたり、占領地の住民を本国に強制的に連行し、工場などでキツイ仕事に従事させたりするなど、まさにやりたい放題したようです。
さらに、ドイツは、徹底的にユダヤ人を差別し、アウシュビッツなど、各地の強制収容所に送りつけ、徹底的に働かせ、そして最後は殺してしまったようです。
ヨーロッパ各地では、こうしたドイツのひどい占領政策に対して、ドイツへの協力拒否や、武力などによるレジスタンスという抵抗運動が活発化しました。
太平洋戦争の開始
日本の南進
日中戦争が長期化していた日本は、ドイツがイギリスやフランスなどに優勢な状況になっていたことを受け、近衛(このえ)内閣の指揮により、イギリスやフランスなどの植民地が多い東南アジアに武力による南進を開始しました。
中国への支援路となっていた援蒋(えんしょう)ルートを断切する目的と、石油やゴムなどの資源を獲得しようとしたのです。
援蒋ルートとは、重慶にいた蒋介石を支援するべく、フランス領インドシナなどからアメリカやイギリスが支援を行っていた支援路のことで、とても重要でした。
1940(昭和15)年9月、日本は、フランス領インドシナ北部に軍を進め、そして日独伊三国同盟を締結しました。
翌1941年4月には、日本の北方の安全を確保するために日ソ中立条約を結び、同1940年7月にフランス領インドシナ南部へも進軍しました。
こうした軍国主義的動きと同期し、日本は「大東亜共栄圏(だいとうあきょうえいけん)」の建設を唱えました。それは、日本の指導の下、欧米の植民地支配を打ち破り、アジアの民族だけで繁栄を目指すという新たなパラダイムでした。
日米交渉の決裂
日本が軍事的な侵略行動を取る中で、日米関係は悪化していきました。
近衛内閣は、アメリカとの戦争を回避のために1941年4月から日米交渉を続けていましたが、軍の要求などもあって、フランス領インドシナなどへの南進をストップしませんでした。
日本がフランス領インドシナの南部へ軍を進めたため、アメリカは石油などの輸出禁止にふみ切りました。その後、イギリスやオランダも同じ行動をとりました。
戦争になくてはならない石油を断たれた日本では、日本を経済的に封鎖する「ABCD包囲陣」を打破するには早期にアメリカと開戦するしかないという意見が高まりました。
尚、「ABCD包囲陣」とは、第2次世界大戦の開始前,アメリカ <America>、イギリス <Britain>、中国<China>、オランダ領東インド <Dutch East Indies>が提携して日本の軍国主義に対抗した包囲陣をさし,4国の頭文字をとってこのように呼ばれていました。
日米交渉の中でアメリカが、中国およびフランス領インドシナからの全面撤兵などを日本へ要求したことを受け交渉決裂と判断し、近衛内閣の次の内閣である東条英機(とうじょうひでき)と軍部は、アメリカとの戦争を最終的に決断しました。
太平洋戦争の始まり
1941年12月8日、太平洋戦争が始まりました。
日本軍は、アメリカ海軍基地があるハワイの真珠湾をだましうちとも見なされる奇襲攻撃を行い、イギリス領マレー半島にも上陸しました。
日本だけでなく、日独伊三国同盟を結んでいたドイツとイタリアも、アメリカに宣戦布告を行いました。
こうして、ドイツのポーランド侵攻をきっかけにヨーロッパで始まった第二次世界大戦は、日独伊などの枢軸(すうじく)国と米英ソ中などの連合国が争う世界規模の戦争へと拡大してしまいました。
日本軍は、東南アジアから南太平洋にかけての広大な地域を短期間で占領し、いったんは順調な滑り出しに見えました。しかし、1942年6月のミッドウェー海戦の敗北によって日本軍の勢いは失せ、太平洋戦争は長期戦へと突入しました。
尚、太平洋戦争は、当時の日本政府は「大東亜戦争」と呼んでいたり、最近では「アジア・太平洋戦争」とも呼ばれています。
戦時下の人々
国民の動員
日本は、総力戦としての太平洋戦争を全ての国力を投入して戦いました。戦争長期化にともない、国民の戦争への動員はいっそう強化されていきました。
成人男子は、多くの人々が兵士として戦場に動員されました。
また、学徒出陣(がくとしゅつじん)も行われました。学徒出陣とは、1943年に兵力不足を補うため、それまで戦争にいくのを猶予されていた20歳以上の文科系大学生を在学途中で徴兵し出征させたことを言います。
労働力不足を補うため、中学生・女学生・未婚(みこん)の女性も勤労動員として、軍需(ぐんじゅ)工場などで働かされました。
空襲(くうしゅう)が激しくなると、都市の小学生は、農村に集団で疎開(そかい)するなども行われました。
軍需品の生産が優先され、兵器用金属として、鍋(なべ)・釜(かま)・寺の鐘(かね)までもが、供出させられました。
このように戦争の影響は国民生活の隅々にまで及びました。
一方、食料をはじめとする生活必需品の生産は停滞し、必要十分な量の配給は行われませんでした。国民は、どんどん苦しくなる生活に耐えながら戦争に協力しました。
戦争に対する国民の意識は、新聞・雑誌などのマスメディアや、小説家・芸術家たちによって浸透していきました。
但し、政府により情報がコントロールされ、正しい戦況は国民には知らされていませんでした。
植民地と占領地
日本は、植民地や占領地においても、戦争への総動員を行いました。
強制的に日本に連行された朝鮮人や中国人の多くが、鉱山や工場などでひどい条件のもとで労働させられたようです。
こうした動員は男性だけでなく、女性にもおよび、戦地で働かされた人もいたようです。
戦争末期には、徴兵制が朝鮮や台湾でも行われました。
日本軍は 占領地とした東南アジアでも、強制労働させたり物資を奪ったりしました。
また、日本語教育などを強要しました。そのため、「大東亜共栄圏」を主張していた日本に対する現地の住民の期待は失望へと変わり、各地で抵抗運動が行われました。
日本軍は、抗日(こうにち)的と見なした人々を厳しく弾圧し、犠牲者が多数でました。
総力戦と犠牲者
第二次世界大戦は、第一次世界大戦以上の世界規模の総力戦になりました。
戦場とそれ以外の境界線がますますわからなくなり、都市への空襲をはじめ、敵国の経済力にダメージを与えたり、敵対する国民の戦意を無くさせる戦術が、世界各国で実行されました。
第二次世界大戦での死者は、全世界で5000万人以上と推計され、軍人よりも民間人のほうが多かったといわれています。
死者だけでなく、負傷者・行方不明者なども多数に上り、物的被害も甚大(じんだい)になりました。
戦争の終結
ドイツとイタリアの降伏
ヨーロッパでもアジア・太平洋でも、開戦直後は枢軸(すうじく)国が戦争を有利に展開しました。
しかし、1942(昭和17)年の後半から連合国が巻き返すようになり、巨大な経済力と軍事力を有するアメリカが主導し、ドイツや日本を追いつめていきました。
ヨーロッパでは、1943年2月、ソ連軍がドイツ軍をスターリングラードで破り、同1943年9月にはアメリカ・イギリス軍がイタリアを降伏させました。
1944年8月にはドイツに占領されていたフランスのパリが解放されました。
ドイツは、東西から攻めこまれ、1945年5月に首都ベルリンの陥落の後、降伏しました。
空襲と沖縄戦
日本も、1943年2月にガダルカナル島の敗北のあと、ジリ貧となっていきました。
1944年7月にはサイパン島が陥落し、東条内閣は退陣しました。
しかし、日本の指導者は、勝利の見通しが無くなった後も、戦争を継続させました。
アメリカ軍と決戦を行い、大損害をあたえることによって、有利な条件で講和条約を結びたいと考えたからです。その結果、犠牲者がものすごく増えてしまいました。
サイパン島の陥落をきっかけにして、日本本土への空襲が激しくなりました。
アメリカ軍は、最初は軍需工場を主な攻撃ターゲットにしていましたが、1945年3月の東京大空襲(とうきょうだいくうしゅう)から、焼夷弾(しょういだん)による都市の無差別爆撃を本格的に開始しました。
1945年3月、アメリカ軍が沖縄に上陸しました。
日本軍は、特別攻撃隊を用いたり、中学生や女学生まで兵士や看護要員として動員したりして激しく抵抗しました。
民間人を巻きこむ激しい戦闘によって、沖縄県民の犠牲者は、当時の沖縄県の人口のおよそ4分の1に当たる12万人以上になったようです。その中には、日本軍によって集団自決に追いこまれた住民もいました。
日本の降伏
1945年7月、連合国はポツダム宣言を発表し、日本に対して軍隊の無条件降伏や民主主義の復活、強化などを要求しました。
しかし、日本は、すぐにはそれを受け入れませんでした。
そしてアメリカは、原子爆弾(原爆)を8月6日に広島、9日には長崎に投下し、2つの県は一瞬で廃墟(はいきょ)になりました。
また、ソ連が、アメリカ・イギリス両国と結んだヤルタ会談での秘密協定に基づき、8月8日に日ソ中立条約を破って日本へ宣戦布告し、満州や朝鮮に侵攻してきました。
ようやく日本は、ポツダム宣言を受け入れて降伏することを決め、8月15日に、昭和天皇がラジオ放送<玉音(ぎょくおん)放送>で国民に敗戦を知らせました。
こうして、長かった第二次世界大戦が終わりました。ちなみに、玉音放送とは、天皇の肉声を放送することをいいます。
中学2年生の【歴史】
現代の日本と世界
★現代の日本と世界★
①戦後日本の発展と国際社会
占領下の日本
敗戦後の日本
終戦日は1945年8月15日ですが、少し前の7月に連合国より発表されたポツダム宣言に基づき、敗戦後の日本の領土は、本州、北海道、九州、四国とその周辺の島々に限定されました。
日本は、軍隊を占領地から撤退させ、日清戦争以降に植民地としていた朝鮮や台湾なども全て解放しました。
沖縄・奄美(あまみ)群島・小笠原諸島は 、日本固有の領土でしたが、本土とは分離され、アメリカ軍による直接統治が行われました。
また、北方領土(ほっぽうりょうど)は、1945年8月9日に日ソ中立条約に違反して日本に対して参戦したソ連は、終戦直後、軍隊を上陸させました。
ソ連は、9月初めまでに北方四島<歯舞(はぼまい)群島、色丹(しこたん)島、国後(くなしり)島、択捉(えとろふ)島>を全て不法占拠し、翌1946年には一方的にソ連領に編入し、日本人を強制的に退去させました。
敗戦後、占領地や植民地にいた軍人と民間人が、日本に帰国してきました。しかし、復員や引きあげは順調には進まず、「中国残留日本人孤児」や「シベリア抑留(よくりゅう)」などの問題が発生しました。
また日本からは、多くの朝鮮人や中国人が自国へ戻りました。その一方で、後に日本国籍を失いながらも、帰国先の混乱などを理由に日本に留まることを選択した朝鮮の人々も数多くいました。
国民の苦難
戦争は、日本の国民生活に甚大なダメージをもたらしました。空襲により多くの人々が住む場所を失い、工場も破壊されました。
学校教育は、空襲による校舎の焼失などの理由から、青空教室という屋外で授業を行ったりしました。
また、教科書からは軍国主義的な記述を削除する指示が出され、それまでの教科書を墨で黒く塗りつぶした墨ぬり教科書が使われました。
鉱工業生産は日中戦争直前の3分の1以下にまで減り、急激な物価上昇がおこりました。
さらに復員や占領地や植民地から引きあげてきた人々も多く一気に人口が増え、失業者があふれかえるようになりました。
日本国内は深刻な食料不足に陥りました。配給制の米なども十分には配られず、栄養失調になる人が増えました。
都市の住民は、わざわざ農村に買い出しに行ったり、都市の駅前の焼け跡などに非合法にできた闇市(やみいち)に出かけたりして、なんとか食いつないでいきました。
戦後の大混乱の中でも、日本国民はあるかぎりの力を出し尽くしてがんばって働き、経済の復興を目指しました。
占領の始まりと非軍事化
戦後、日本の本土は、アメリカ軍を中心とする連合国軍によって占領されました。
そして、GHQ=連合国軍最高司令官総司令部の指令に従って、日本政府が政策を実施する、間接統治の方法が採用されました。
GHQの下で、戦後改革が行われました。
尚、GHQの最高司令官がマッカーサーです。GHQといえば、日本では、第二次世界大戦後に日本の占領政策に当たった連合国軍最高司令官総司令部を指す事が多いですが、総司令部<General Headquarters>の一般的な略称です。
GHQによる占領政策の基本方針は、日本が再び連合国の脅威にならないよう、非軍事化を徹底することでした。
軍隊を解散させ、極東国際軍事裁判(=東京裁判)を行い、戦時中に要職にあった人々を公職から追放しました。
極東国際軍事裁判とは、1946年から1948年にかけて行われた裁判で、東条英機元首相など28名が「平和に対する罪」を犯したA級戦犯(戦争犯罪人)として起訴され、病死者などを除く25名が有罪判決を受けました。
これとは別に、戦争中に残虐行為をしたとされるB・C級戦犯の裁判も、世界各地で行われたようです。
昭和天皇も、1946(昭和21)年に「人間宣言」を発表し、天皇が神であるという考え方を否定しました。GHQの強い意向に従ったものです。
民主化と日本国憲法
民主化
非軍事化と同じくらいGHQは占領政策の基本方針として、民主化を重要視しました。日本政府も、大正デモクラシーの実経験などを基盤に、積極的に民主化を進めていきました。
政治においては、治安維持法が廃止され、政治活動の自由が認められました。
また、選挙権は、それまで満25歳上の男子に限定されていましたが、満20歳以上の男女にあたえられました。1946年4月、満20歳以上の男女による初めての衆議院議員選挙が行われ、39人の女性の国会議員も誕生しました。
経済においては、財閥解体が行われ、また、労働組合法(労働者の団結権を認める法律)や労働基準法(労働条件の最低基準を定める法律)が制定されました。
農村においては、農地改革が行われました。
地主が持つ小作地を政府が強制的に買い上げて、小作人に安く売りわたしたのです。
この農地改革によって、経済的にも社会的にも農村の平等化が進み、その結果、多くの自作農が生まれました。
日本国憲法の制定
民主化の中心政策として進めたのが憲法の改正でした。
日本政府は初めにGHQの指示を受けて改正案を作成しましたが、大日本帝国憲法を少し修正したレベルのものにすぎませんでした。
GHQは、徹底した民主化を目指していたため日本の民間団体の案も参考にしながら、自ら草案を作成しました。日本政府は、GHQ草案を受け入れ、それを基に改正案を作成しました。
そして、帝国議会の審議を経て、日本国憲法が1946(昭和21)年11月3日 に公布され、翌1947年の5月3日から実際に施行されました。
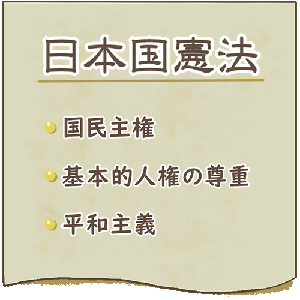
民主化を目指す新憲法の日本国憲法は、三つを基本原理としました。
三つの基本原理は、国民主権・基本的人権の尊重・平和主義です。
天皇は、統治権がなくなり、国と国民統合の象徴とされました。そのかわり、国会が国権の最高機関となり、内閣が国会に責任を負う議院内閣制が導入されました。
日本国憲法の制定にともない、地方自治法や教育基本法などが作られました。
また、民法が改正され、1898年に施行された旧民法では戸主を中心とする家制度や男性優位の原則でしたが、1948年に施行された新民法では個人の尊厳と両性<男女>の本質的平等に基づく新たな家族制度が定められました。
政党政治と社会運動の復活
民主化に向けた動きは、政府だけでなく国民の間からも高まりました。
日本社会党<社会党>や日本自由党が結成され、日本共産党が再建されるなど、戦時中に挙国一致体制をつくるため大政翼賛会に合流し、抑圧され解散していた政党が、活動を再開しました。
各政党は、新憲法に定められた議員内閣制の下で、政党政治が復活しました。
労働組合法の制定や国民生活の悪化を背景として、労働組合も数多く組織され、賃金の引き上げなどを要求しました。
また、部落解放運動も再び盛り上がりをみせ、北海道アイヌ協会も再結成されるようになりました。
冷戦の開始と植民地の解放
国際連合と冷戦の始まり
1945(昭和20)年10月、連合国は、二度の世界大戦への反省から、国際連合(国連)を設立させました。
国連には、安全保障理事会(世界の平和と安全を維持する機関)がつくられ、アメリカ・イギリス・フランス・ソ連・中国が常任理事国になりました。
しかし、連合国間の平和と安全へ向けた協調は、長続きしませんでした。
ソ連が東ヨーロッパ諸国を支配したのに対抗して、アメリカが西ヨーロッパ諸国を支援し、アメリカを中心とする資本主義の西側と、ソ連が率いる共産主義の東側の、二つの陣営に分裂したからです。
その象徴としてドイツは、1949年、東ドイツ・西ドイツと別々に独立しました。
また、軍事同盟として、西側は、1949年に北大西洋条約機構(NATO)、東側は、1955年にワルシャワ条約機構(WTO)を結成しました。
尚、現在WTOといえば、世界貿易機関(WTO=World Trade Organization)が一般的ですのであわせて覚えておいてね。
両陣営の対立は、新たな世界大戦が発生しかねないほどの状況で、実際の戦争と対比して、冷たい戦争(=冷戦)と呼ばれました。
二大中心大国であるアメリカとソ連両国は核兵器をふくむ軍備拡張を競い合い、冷戦下における世界は、核戦争の危険ととなり合わせでした。
新中国の成立と朝鮮戦争
冷戦は、東アジアにも影響を与えました。
中国では、日本の敗戦後、国民党と共産党との間で内戦が再発しました。この内戦で東側の共産党が勝利して、1949年に毛沢東(もうたくとう)を主席とする中華人民共和国(中国)が成立しました。
朝鮮は、日本の敗戦で植民地支配から解放はされましたが、北緯38度線を境にして、南をアメリカ、北をソ連に占領されました。
1948年、南に西側の大韓民国(韓国)、次いで北に東側の朝鮮民主主義人民共和国(北朝鮮)が成立しました。
1950年には、北朝鮮が武力統一を目指して韓国に侵攻し、朝鮮戦争が始まりました。
韓国をアメリカ中心の国連軍が、北朝鮮を中国の義勇軍がそれぞれ支援して長期化したため、1953年に北緯38度線付近を軍事境界線とする休戦協定が結ばれました。
植民地支配の終わり
第二次世界大戦後には、アジアやアフリカで多くの国々が列強の植民地支配から解放されました。
植民地支配を行ってきた国々が、第二次世界大戦を経て国力が弱まり、さらに独立運動が活発化した結果、多くの植民地が独立を達成しました。
アジアでは、1949年までにインドネシア・フィリピン・インドなどが独立しました。
アフリカでは1960年に17か国が独立を達成し、「アフリカの年」と呼ばれました。
しかし、独立後も紛争や飢餓に悩まされる国が多く、南北問題という、北半球に多い豊かな先進工業国と南半球に多い貧しい発展途上国の経済格差問題も未解決のまま残されています。
独立の回復と55年体制
占領政策の転換
東西冷戦が激しくなると、アメリカは、東側陣営への対抗策として、日本を西側陣営の強力な一員にしようと考えるようになりました。
GHQの占領政策は、非軍事化と民主化よりも経済復興を重要視する方向に転換され、労働運動の抑制や、商品価格などのコントロールの撤廃が実施されました。
1950(昭和25)年、朝鮮戦争開始にともない、日本本土や沖縄のアメリカ軍基地が使用され、大量の軍需物資が日本で調達されました。
日本経済は特需景気(とくじゅけいき)と呼ばれ、好景気になり、経済復興が早まりました。
また、朝鮮戦争に在日アメリカ軍が出兵すると、GHQの指令で警察予備隊が作られ、それが徐々に強化されて、1954年には、自衛隊(じえいたい)と発展していきました。
平和条約と安保条約
アメリカは、占領の長期化が反米感情を高めることをおそれたため、日本との講和条約締結を急ぎました。
1951年、吉田茂(よしだしげる)内閣は、アメリカなど48か国とサンフランシスコ平和条約を結びました。
しかし、この講和会議に中国は招かれず、インドやビルマ(ミャンマー)は出席を拒否し、ソ連などは出席はしたものの、条約には調印しなかったようです。
また東南アジアには、日本が経済上の理由から賠償を軽減されたことに不満を持ち、調印した条約の承認を遅らせた国や、承認を行わなかった国もあり、講和が完全には実現しませんでした。
サンフランシスコ平和条約と同時に、吉田内閣はアメリカと日米安全保障条約(日米安保条約)を結びました。これによって、占領終結後もアメリカ軍基地が日本に残る理由を正当化しました。
1952年4月28日、サンフランシスコ平和条約が発効し、日本は主権と独立を取り戻しました。しかし、沖縄や小笠原諸島は、その後もアメリカによる直接統治がしばらく続けられました。
自民党長期政権と安保条約改定
1954年にアメリカの水素爆弾(水爆)の実験で第五福竜丸が被ばくした事件をトリガーにして、日本国内では原水爆(げんすいばく)禁止運動が全国に拡大しました。
また、社会党などの革新勢力がアメリカの冷戦政策を批判し、日米安保条約や自衛隊にも反対を唱えました。
アメリカの冷戦政策を支持する保守勢力は、社会党などの革新勢力の動向に危機感をいだいて、1955年に自由民主党(自民党)を結成しました。
与党第一党の自民党は、野党第一党であった社会党と対立を続けながら、38年間の長期にわたって政権を運営し続けました。
これを55年体制といい、1955年に成立した体制なのでこのように呼ばれています。
自民党と社会党の対立のピークは、1960年の日米安保条約の改定です。
岸信介(きしのぶすけ)内閣は、アメリカとの関係をより対等にし、強化することを目指して、新しい日米安保条約を結びましたが、それに対して安保闘争(あんぽとうそう)という大規模なデモ隊が国会議事堂を取り囲むなど激しい反対運動が起こりました。
ちなみにこの安保闘争の時の岸信介首相は「昭和の妖怪」とも言われた人物で、安倍晋三首相の祖父です。詳しくは、調べてみてください。
緊張緩和と日本外交
緊張緩和の進展
冷戦下における国際的な緊張は、1950年代半ばから少しずつ緩和されていきました。
アジア・アフリカなど列強の植民地支配から独立した国々の多くは、インドなどの提案で29か国が参加し、インドネシアのバンドンで1955(昭和30)年に開催されたアジア・アフリカ会議に代表されるように、平和共存を主張しました。
1962年、キューバ危機が米ソ間の核戦争が起こる瀬戸際で解決されると、緊張緩和が本格化しました。
西ヨーロッパ諸国は、経済統合を進め、1967年にヨーロッパ共同体(EC)を設立しつつ、1970年代前半には東ヨーロッパ諸国との関係改善に努めました。
中国とソ連の支援を受ける北ベトナムやその指導の下で結成された南ベトナム解放民族戦線と、アメリカが戦ったベトナム戦争の際には、世界各地で反戦運動が行われました。
アメリカが中国との関係を改善し、1973年にベトナムから撤兵すると、緊張緩和はアジアにも拡大していきました。
広がる日本の外交関係
日本は、1951年に結んだサンフランシスコ平和条約で西側陣営の一員として独立を回復しました。
1950年代半ばから冷戦下における緊張緩和が進む中、残課題とされていた東側陣営やアジア諸国との外交関係を築いていきました。
1956年、日ソ共同宣言が調印され、ソ連との国交が回復しました。
ただし、この時日本は、北方領土について日本固有の領土であると主張しましたが、ソ連が認めなかったため、平和条約については締結することはできませんでした。
この時の内閣は、鳩山一郎(はとやまいちろう)首相です。
同1956年、日本はソ連のバックアップもあり国連に加盟し、ようやく国際社会に復帰できました。
日本と東南アジア諸国の間にあった賠償問題は、おおむね1950年代末までに解決されたようです。
また、韓国とは、1965年に日韓基本条約(にっかんきほんじょうやく)を締結しました。
日本政府は、日韓基本条約で韓国政府を唯一の朝鮮半島における政府として認めました。
中国とは、1972年に日中共同声明によって国交を正常化し、1978年には日中平和友好条約を締結しました。
この時の内閣は、田中角栄(たなかかくえい)首相でした。その後、中国の経済発展にともなって、日本と中国の関係性は高まっていきました。
沖縄の日本復帰
1951年に結んだサンフランシスコ平和条約において、日本側からみた問題点の一つは、沖縄がアメリカの直接統治下に残されたままということでした。
1950年代当時は、アメリカ軍事基地建設のために多くの土地を明け渡すなど、沖縄では多数の権利が制限されていました。それでもなお、沖縄の人々は、沖縄の日本復帰を求める運動をねばり強く続けていきました。
1972年5月沖縄が日本に復帰しました。
この時の内閣は、佐藤栄作首相です。佐藤栄作は、1965年から「沖縄が復帰しない限り戦争は終わらない」と主張し、アメリカ政府と交渉を進め、沖縄の復帰を実現させました。
その功績をたたえ、後にノーベル平和賞を受賞しています。

この時の過程で、非核三原則が国の基本方針になりました。
非核三原則とは、核兵器を「持たず」「つくらず」「持ちこませず」という考え方です。
しかし、沖縄におけるアメリカ軍基地は、多くの県民の期待通りにはいかず、復帰後もあまり縮小しませんでした。2020年代に入った今でもまだ沖縄島の約15%がアメリカ軍施設として残っています。
日本の高度経済成長
高度経済成長
日本の経済は、朝鮮戦争特需もあって1950年代半ばには、戦前の水準までほぼ回復させました。このあとは、高度経済成長の時代を迎えます。
高度経済成長とは、1955年から73年までの間を指し、平均年10%程度の経済成長を続けました。
1960年の安保闘争で、岸内閣の退陣の直後に成立した政府も経済成長を積極的に促進していきました。
この時の内閣は、池田勇人(いけだはやと)首相で、スローガンに「所得倍増」をスローガンにかかげ国民の意識も高め後押ししました。
高度経済成長期の産業の主軸は、なんといっても重化学工業でした。技術革新が進み、鉄鋼や造船などが発達しました。
重化学工業の発達にともない、主なエネルギー源はそれまでの石炭から石油にかわりました。製鉄所や石油化学コンビナートが、太平洋や瀬戸内海の沿岸を中心とする各地に建設されていきました。
1968年、日本の国民総生産(GNP)は、トップは当然アメリカでしたが、資本主義国の中ではその次の第2位になりました。また、海外との自由貿易も拡大し、日本経済は国際化進んでいきました。
国民生活の変化と公害
テレビ・洗濯機・冷蔵庫などの今ではあたりまえの家庭電化製品や自動車が普及し、スーパーマーケットが広がったのは、高度経済成長期です。
高度経済成長期のおかげで、日本国民は所得が増え、暮らしぶりがよくなりました。
東京や大阪や名古屋といった大都市郊外には、自宅用の浴室や水洗トイレなどを備えた団地が建設ラッシュされました。
新幹線や高速道路が開通し、1964年には東京オリンピック・パラリンピックが開催されました。
しかし、高度経済成長は、いろいろな社会問題も発生しました。農村においては、過疎化が進み人口が流出してしまいました。逆に都市では、人口が過密になり交通渋滞、住宅不足、ごみ問題などが発生しました。
公害問題も深刻化しました。
工場がフル稼働することによって、大気汚染や水質汚濁などの公害問題が起こりました。
被害を受けた住民は、各地で公害反対運動を起こしました。
実際に行われた四大公害裁判では、新潟水俣病、四日市ぜんそく、イタイイタイ病、水俣病で、公害を発生させた企業にそれぞれ勝訴しました。
日本政府も公害問題に対する必要性をせまられ、1967年には、公害対策基本法を制定し、1971年には環境庁(現在の環境省)を設置するなどの対策をとりました。
経済大国日本
高度経済成長期は、1955年から73年までの間を指しますが、終わりを迎えた1973年には何があったのでしょうか?
ずばり!石油危機(オイル・ショック)です!

石油危機とは、1973年、聖地エルサレムなどをめぐってユダヤ人とアラブ人が争うパレスチナ問題を背景に、第四次中東戦争が発生し、石油価格が大幅に上昇したことをいいます。
この影響で、先進工業国の経済は不況となり、日本でも高度経済成長が終わってしまいました。
しかし、日本企業は、石油危機の不況下でも、経営合理化や省エネルギー化を推進し、不況をいち早く乗りきっていきました。
そして、それまでの高度経済成長期を支えた重化学工業の鉄鋼・造船などにかわって、新たに自動車や電気機械などの輸出が伸張(しんちょう)し、貿易黒字が増加しました。
その結果、アメリカなどとの貿易摩擦が大きな問題となるとともに、国際社会から新たに経済大国としての役割を要求されるようになっていきました。
マスメディアと現代の文化
戦後の文化とマスメディア
戦後の日本では、GHQの占領政策下ではありましたが、これに反しない範囲内で、言論の自由が回復されました。
多くの新聞や雑誌が復刊、創刊され、「中央公論」や「世界」などの月刊総合雑誌がその代表例です。それらの紙媒体を通じて、西ヨーロッパをモデルとする近代化の必要性が唱えられ、知識層を中心に強い影響をあたえていきました。
大衆の娯楽としては、映画が特に人気を集めていきました。
1950年に公開された黒澤明(くろさわあきら)監督の「羅生門(らしょうもん)」などが世界的な高評価を受けました。
ラジオは、NHKが開始していましたが、1951(昭和26)年には民間放送が始まりました。ラジオ文化は、映画とともに1950年代中ごろに最も盛り上がりをむかえました。
テレビと高度経済成長期の文化
映画・ラジオに続いて、1953年にはテレビ放送が開始されました。さらに、1950年代末には、テレビが家庭に急速に普及し始め、新たに「週刊新潮」の創刊や、週刊誌ブームが起こり、週刊の漫画誌や女性誌などが広まっていきました。
高度経済成長期は、テレビの時代でもありました。
人々はテレビが映し出す豊かな生活にあこがれ、コマーシャルをみて購買意欲を高めました。
テレビは、大多数の家庭でリビングに置かれ、家族の団らんの中心として大活躍しました。
娯楽もスポーツや芸能など、テレビで楽しむことがトレンドとなりました。
この時代の国民的なテレビヒーローは、プロ野球の長嶋茂雄(ながしましげお)や王貞治(おうさだはる)、大相撲の大鵬(たいほう)などで、大人気でした。
また、日本全国の人々がテレビの映像や音声を通じて、同じ内容の情報を同時に得るようになり、国民の考え方が均質化していきました。
さらに、高度経済成長によって人々の生活水準は向上し、高校と大学への進学率も上昇した結果、多くの国民が「中流意識」を持つようになっていきました。
文学面でも、伝統的で芸術性を重要視する純文学と、娯楽性の高い大衆小説との中間的な作品が増えました。
推理小説では、松本清張(まつもとせいちょう)や、歴史小説では、司馬遼太郎(しばりょうたろう)などが人気となりました。
また、純文学でも優れた作品が数多く発表され、1968年に川端康成(かわばたやすなり)、1994年に大江健三郎(おおえけんざぶろう)などがノーベル文学賞を受賞しています。
近年では、宮崎駿(みやざきはやお)監督のアニメ映画に代表されるように、日本の漫画とアニメは国際的に高い評価を受けて、人気となっています。
インターネットの発達
マスメディアは、特定の送り手が不特定多数に向けて一方向で情報を伝える手段で、新聞やテレビなどを指します。
マスは、英語のmassからきていて日本語訳では「大衆」と訳され、マスメディアは大衆メディアという意味です。
1990年代後半からはマスメディアにかわってインターネットが普及し、文字・音・声・画像などの大量の情報を、国境をこえて高速で双方向的にやり取りできるようになりました。
その結果、「Amazon」に代表されるようなインターネット・ショッピングの発達をはじめ、社会に大きな変化をもたらしています。
★現代の日本と世界★
②新たな時代と日本と世界
冷戦後の国際社会
冷戦の終結
1979年、ソ連がアフガニスタンに侵攻しました。これをきっかけとして東西両陣営の対立が再燃しました。
ソ連は、経済が停滞しつつあった時に、軍事費の負担増などによって国力がさらに低下してしまいした。
そこで、1985年にソ連でゴルバチョフ政権が誕生しました。
ゴルバチョフ政権は、アメリカなどの西側陣営の国々と関係を改善するとともに、共産党の独裁体制や計画経済の見直しを推進しました。
残念ながら、国内における政治と経済の立て直しは両方ともうまくいかなかったようです。
このような中、民主化運動が周辺の東ヨーロッパ諸国において高まり、1989年に共産党政権が次々にたおされていきました。

また、同1989年11月に冷戦の象徴であったドイツのベルリンの壁が取りこわされ、米ソの首脳が冷戦の終結(れいせんのしゅうけつ)を宣言しました。
翌1990年、東西ドイツが統一し、1991年にはソ連が解体されました。
冷戦の終結を迎えソ連が解体された結果、アメリカだけが唯一の世界規模で軍事行動を行える超大国となっていきました。
国際協調への動き
冷戦後、国際協調の動きも高まり、それまで十分に機能していなかった国連は、ほぼ全世界を代表する国際機関としての役割が期待されるようになりました。
また、1975年からは、サミットと呼ばれる主要国首脳会議が開催されています。
2008年からは、サミットに参加する8か国<G8(ジーエイト)>に加え、新興国の中でも経済成長が著しい中国・インド・ブラジルなどを加えたG20サミットも開催されています。
さらに、地域統合の動きも進んでいます。
1993年、ECは、域内の市場統合を完成させたうえで、ヨーロッパ連合(EU)に発展しました。
EUは、冷戦の終結にともない民主化した東ヨーロッパに拡大するだけでなく、政治統合も推進しています。
一方で、現在はイギリスがEUから離脱する動きもあり、新たな動きを見せています。
ヨーロッパに比べて、アジア・太平洋の地域統合はあまり進展していません。
しかし、1989年に発足したアジア太平洋経済協力会議<通称:APEC(エイペック)>など、地域協力の枠組みがゆるやかなスピードで作られてきています。
現在では、TPPという環太平洋パートナーシップ協定など、環太平洋地域の国々による経済の自由化を目的とした、多角的な経済連携協定の成立を目指す動きも出てきています。
相次ぐ地域紛争
地域統合が進む一方で、民族や宗教や文化のちがいや国家間の対立などを理由に、旧ユーゴスラビアの内戦をはじめ各地で地域紛争が発生しています。
核兵器に代表される大量破壊兵器の拡散や、一般市民を巻きこむテロリズムも発生しています。
その地域紛争の焦点の一つは中東地域です。
1991年にイラクがクウェートに侵攻して湾岸戦争が勃発(ぼっぱつ)し、2001年には、アメリカが同時多発テロを理由にアフガニスタンを攻撃しました。
アメリカ同時多発テロとは、2001年9月11日にイスラム教過激派にハイジャックされた民間飛行機が、ニューヨークの高層ビルやワシントンD.C.の国防総省に突入した一連のテロを指します。
その後、2003年にはイラク戦争が発生しました。また、パレスチナ問題も未解決のまま残されています。
このような地域紛争を解決するためには、国連の平和維持活動(PKO)の役割はかけがいのないものです。
また、紛争や災害で傷ついた人々に対して緊急医療援助活動を行う国境なき医師団のように民間の非政府組織(NGO)も活躍しています。
変化の中の日本
冷戦後の日本
冷戦後の世界においては、国連に代表されるように国際的な組織の枠組みを通して地域紛争の解決を目指す動きが高まりました。
日本においても、経済面の援助だけでなく、世界平和の面でも国際貢献を求められるようになりました。
そのため、1992年には、国連平和維持活動(PKO)に自衛隊の部隊を初めて派遣し、その後も世界平和への国際貢献を継続しています。
しかし、日本も属する東アジアにおいても冷戦が生み出した。
韓国と北朝鮮、中国と台湾といった旧東西ドイツのような分断状況がいまだ残されたままです。
北朝鮮は、核兵器の開発を進め、日本拉致問題なども未解決のままで、国交正常化の動きも進んでおりません。
また、中国や韓国そしてロシアといった日本の近隣諸国との間には、領土問題が続いております。
日本は、日米安保条約に基づいて、アメリカとの同盟関係を強化してきています。
しかし、日本国内にも、アメリカの軍事行動への協力やアメリカ軍基地をめぐって複数の異なる意見があるのも事実です。
55年体制の終わり
1955年に結成された自由民主党(自民党)は、野党第一党の社会党と対立しながら、38年間にわたって与党として長期政権を運営しました。
長期政権は、政治の安定や経済成長を実現させたました。
一方で長期政権のデメリットとして、政治家・官僚・企業が深く結び付いて汚職(おしょく)事件や癒着(ゆちゃく)といったスキャンダルを生み出し、批判が強まりました。
また、冷戦の終結により、保守勢力(自民党)と革新勢力(社会党)との対立構造を弱体化させました。
1993年、衆議院の選挙制度などを変える政治改革をかかげて非自民連立内閣が成立しました。
この非自民連立内閣は、細川護熙(ほそかわもりひろ)を首相とする内閣で、自民党と共産党を除く8党派から構成されました。
こうして、38年もの間続いた自民党を与党(よとう)、社会党を野党第一党とする55年体制が終わりを迎えました。
その後、自民党は再び政権に復帰しましたが、自民党単独で内閣を組織する力はなく、いろいろな政党と連立政権を作ったりして政権運営を行いました。
2009年、マニフェスト(選挙公約)を掲げた民主党の勢いもあり、非自民の政権交代が起こりました。
しかし、2012年には再び自民党が公明党と組んで連立政権を作るなど、安定しない政治が続いています。
バブル経済崩壊後の経済
バブル経済とは、1986年から1990年頃にかけて日本で発生した株価や地価など資産価格の急激な上昇と、それに伴う好景気のことをいいます。
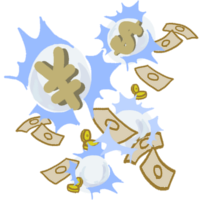
株価や地価が経済の実体をこえて上昇する急激な膨張(ぼうちょう)ぶりとのちの崩壊が、「あわ」がふくらんでしぼむ様子によく似ていることから、「バブル経済」とよばれるようになりました。
当時は誰もが「あたりまえ」「これが日本の実力」と信じて行動していたようですが、このバブル経済は、1991年に崩壊しました。
バブル崩壊後、日本では失われた10年ともいわれる長期にわたる平成不況の下で、企業の倒産が増加し、失業者が多くなりました。
平成不況とは、バブル景気後に訪れた以下の平成時代の大不況の通称を指します。
<第一次平成不況(バブル崩壊)>
1991年3月~1993年10月までの32か月間
<第二次平成不況(金融危機)>
1997年~1999年1月までの20か月間
<第三次平成不況(ITバブル崩壊)>
2000年12月~2002年1月までの14か月間
日本政府は経済活性化を目的として、経済活動に対する規制の緩和(かんわ)、国営事業の民営化などを推進しました。
しかし、貧富の格差や都市と地方の格差を結果的に拡大させてしまったといわれているようです。
その後、景気はいったん回復しましたが、2008年の世界金融危機(2007年-2010年)によって、再び深刻な不況が発生しました。
世界金融危機とは、2007年に顕在化(けんざいか)したサブプライム住宅ローン危機を発端としたリーマン・ショックと、それに連鎖(れんさ)した一連の国際的な金融危機を言います。
また、生産コスト削減を目的とした工場の海外移転による産業の空洞化や、財政赤字も大きな問題になっています。
そして2020年は、新たに世界的なコロナ・ショックの時代を迎えています。
持続可能な社会に向けて
日本社会の課題
「地震・雷・火事・親父(じしんかみなりかじおやじ)」は、昔から日本で恐ろしいものと考えられているものを順番にならべたものです。
ちなみに地震・雷・火事はそのままですが、親父は、台風をさすと言われています。その中でもトップの地震はとても恐ろしいものです。
1995年の阪神・淡路大震災や2011年の東日本大震災は、日本へ深刻な被害をもたらしました。
私たちに防災やエネルギー面での課題に気づきをあたえてくれた一方で、地域の絆(きずな)とボランティア活動の重要性を教えてくれました。
被災地の復興や防災対策などをこれまで以上に進めるとともに、一人一人が積極的に社会に参画して助け合う日本を創造していくことが必要になってきています。
新しい助け合う日本を創造していくうえで、まず重要なのは、人権の尊重です。
部落差別の撤廃(てっぱい)は、国や地方公共団体の責務であり、国民全員が取り組むべき身近な課題です。
アイヌの人々や、在日韓国・朝鮮人、外国人労働者などに対する差別や偏見をなくすことも、国民ひとりひとりが取り組むべき未解決の大きな課題です。
また、少子高齢化社会の急速な進展にともない、女性、子ども、高齢者、障がい者の権利を守り、経済成長とともに、安心して生活できるための社会保障制度を築き上げていくことも重要になってきます。
そのためにも、選挙の際に投票に行くなど、国民ひとりひとりが積極的に政治に参加し、民主主義を活性化することが必要と言われています。
社会ごとを自分ごとに、そして自分ごとを社会ごとに考えていく習慣が今後ますます求められてきます。
グローバル化の進展
現在は、交通網の発達やインターネットの普及などにより、世界の一体化=グローバル化が急速に進展しています。
経済活動は国境を超えて日常的に行われ、情報はインターネットや衛星放送などで世界中へ瞬時に伝達されます。
こうした中で感染症対策は、新型コロナで一気に重要性が高まりましたが、他にも平和、環境、資源、食料、といった課題は、一国だけでは解決できなくなってきています。
私たちは日本国民としての意識は当然ながら、それにプラスして地球に生きる人間(地球市民)としての意識を持つことが求められています。
グローバル化が進展していく中、日本は、国連などの国際機関に協力するとともに、平和主義をかかげる憲法の理念を尊重しながら、国際貢献にも取り組んでいます。
特に、戦争による唯一の被爆国としての経験をもとに、核兵器の廃絶をはじめとする軍縮には積極的に取り組んできました。
地球環境の問題も重要です。地球温暖化は、海面の上昇や農作物の不作など、世界各地で深刻な問題を発生させています。
そこで、1997年12月の京都議定書の採択に見られるような国際的な取り組みにも参加し、地球温暖化の原因とされる二酸化炭素などの温室効果ガスの排出削減に向けて取り組んでいます。
歴史を学んで
歴史は過去の出来事の振り返りですが、重要なのは、戦争など過去の失敗を再び起こさないように、しっかり過去を学ぶとともに、今と未来へ目を向けて役立てることが重要になってきます。
皆さんの世代だけでなく、50年後、100年後の将来の世代の日本と世界の幸福を見すえた「持続可能な社会」を実現することが求められています。
中3で学習する公民的分野は、より具体的な実現方法を考えるうえでもきっと役に立つと思いますので、こちらもしっかり学んで下さい。
以上で、中学2年の歴史の範囲は、終了です。
何度か読み返したり、もっと詳しくしりたいなんて気分になったら、教科書などでも確認してみてね。じゃ、お疲れさまでした。
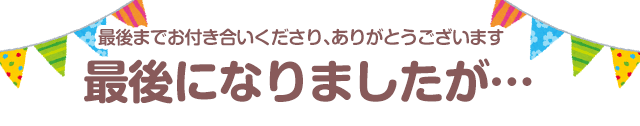
このページでは、中学2年生の社会で押さえておきたい重要ポイントについて説明させていただきましたが、他にも“絶対に取りこぼしてはいけない基本”はたくさんあります。
中学生から暗記量が一気に増える「社会」は、地理も歴史も”興味のあるなし”によっても大きく差が付く教科ですね。
「社会にニガテ意識がある…」
「社会なんて大っキライ!」
「暗記のやり方がわからない…」
そんなお子さんは今すぐ対策をしていかないと、学年が上がるにつれて暗記量が増えていき、どんどん勉強が大変になってしまいます。

私たち家庭教師のジャニアスでは、“社会の楽しさ”“暗記の仕方”を教えてたくさんのお子さんに点数アップ、成績アップの結果を出してきました。
今なら!無料の体験授業で勉強のやり方から丁寧に教えていますので、この機会に一度試してみませんか?
もちろん、体験授業を受けていただいたからといって、ご入会への無理な勧誘は一切ありませんのでご安心ください。
体験授業でお会いできることをスタッフ一同、楽しみにしています。
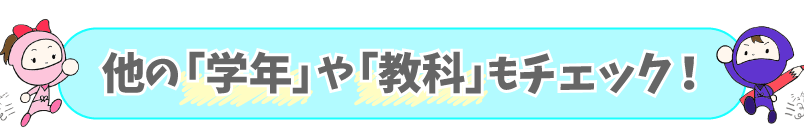
今ご覧になっているページは
社会(中2)です。
▼ よく見られているページ ▼

家庭教師のジャニアスでは下記の地域にお住いの方に家庭教師を紹介しております。下記に含まれていない地域にお住まいのご家庭でも、家庭教師を紹介できる場合もございますので、お気軽にお問い合わせください。
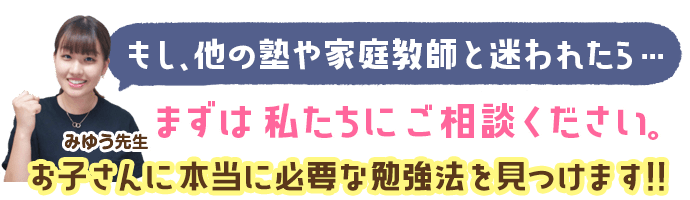
私たちジャニアスは、どんなに効果がある勉強法でもお子さんに合わない・
続けることができなければ「意味がない」と考えています。

塾や家庭教師選びにご苦労されているご家庭も多いと思いますが、ジャニアスの体験授業は、「やる気のきっかけにしたい」「今の塾と比べてみたい」「今すぐは考えてないけど家庭教師がどんなモノかを見てみたい」などのような、気軽な気持ちで受けていただけたらと思います。
もちろん、体験を受けたからといって、無理に入会を勧めるようなことは一切ありませんので、安心してくださいね(^^)